テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
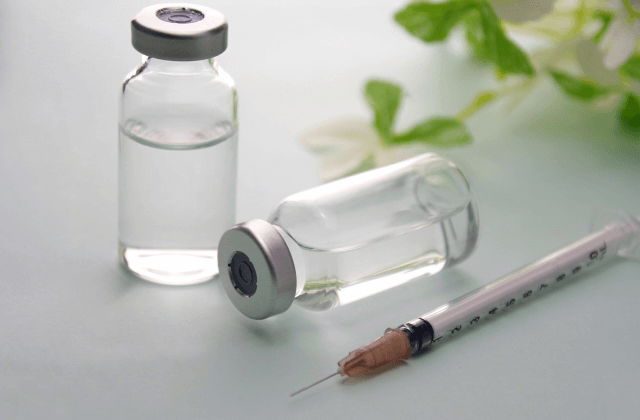
医薬品が開発されるまでの流れとは?
まだ記憶に新しい、世界を席巻したCOVID-19(新型コロナウイルス) 。こうしたウイルスの脅威、あらゆる疾病の診断・治療・予防に必要なモノ、それは医薬品です。コロナ禍でのワクチン開発、認可、一般接種が異例の速さで行われたことは説明するまでもありませんが、一般的な医薬品開発はどんなプロセスで進むかご存じでしょうか?
新薬誕生までのプロセスを具体的にみていくと、
1.基礎研究 :2~3年
新薬のための新たな物質・成分の発見や合成のための研究
2.非臨床試験:3~5年
薬物の有効性や安全性を確認するため、動物を用いた試験研究
3.臨床試験:3~7年
薬物の有効性や副作用の調査を含む安全性について、人で試験
(この試験は「治験」といい、以下3ステップで進められる)
・第Ⅰ相試験:健康な成人を対象
・第Ⅱ相試験:少数の患者を対象
・第Ⅲ相試験:多数の患者を対象
4.承認申請・製造販売:1~2年
厚生労働省・医薬品医療機器総合機構(PMDA)の承認審査を経て、
有効性や安全性が確認されると、厚生労働大臣が製造・販売を許可
5.製造販売後調査:6ヶ月~10年
治験では得ることのできない効果や副作用等について、販売後も調査や試験
新薬はその実用まで、早くて約10年、長い場合は18年以上の期間を要し、費用的にはだいたい200~300億円かかるといわれています。
また、基礎研究で探した新薬候補が実際に発売できる確率は2万~3万分の1といわれ、開発は年々難しさを増しているとのこと。「承認取得」の難度も上昇しつつあり、開発期間と所要コストは増加傾向にあり、製薬メーカー各社はこうした課題に直面しているのが実状です。
医薬品ができるまで
日本における新薬は、例年40~50種類ほど開発され、一般的に処方・投与されるといわれています。新薬の開発は基礎研究からはじまり、さまざまな研究や試験を経て、認可・実用されます。新薬誕生までのプロセスを具体的にみていくと、
1.基礎研究 :2~3年
新薬のための新たな物質・成分の発見や合成のための研究
2.非臨床試験:3~5年
薬物の有効性や安全性を確認するため、動物を用いた試験研究
3.臨床試験:3~7年
薬物の有効性や副作用の調査を含む安全性について、人で試験
(この試験は「治験」といい、以下3ステップで進められる)
・第Ⅰ相試験:健康な成人を対象
・第Ⅱ相試験:少数の患者を対象
・第Ⅲ相試験:多数の患者を対象
4.承認申請・製造販売:1~2年
厚生労働省・医薬品医療機器総合機構(PMDA)の承認審査を経て、
有効性や安全性が確認されると、厚生労働大臣が製造・販売を許可
5.製造販売後調査:6ヶ月~10年
治験では得ることのできない効果や副作用等について、販売後も調査や試験
新薬は誕生してからも
新薬は認可製造販売されてからも、調査や臨床試験が続きます。臨床研究は、性別、年齢、人種、合併症、他医薬品との組み合わせによる影響といった情報を集めることで、より確かな治療方法を確立するために不可欠なプロセスなのです。新薬はその実用まで、早くて約10年、長い場合は18年以上の期間を要し、費用的にはだいたい200~300億円かかるといわれています。
また、基礎研究で探した新薬候補が実際に発売できる確率は2万~3万分の1といわれ、開発は年々難しさを増しているとのこと。「承認取得」の難度も上昇しつつあり、開発期間と所要コストは増加傾向にあり、製薬メーカー各社はこうした課題に直面しているのが実状です。
<参考サイト>
・厚生労働省:一般的な医薬品の開発の基本的な流れ
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0421-4c_0002.pdf
・厚生労働省:一般的な医薬品の開発の基本的な流れ
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/04/dl/s0421-4c_0002.pdf
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










