テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
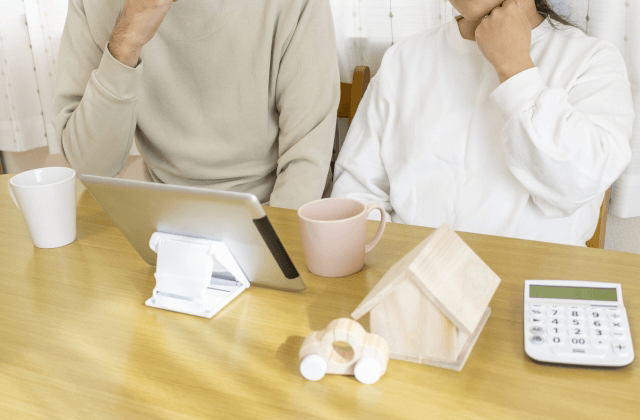
結婚生活がうまくいくための7つの原則
日本では結婚したカップルの35%、3組に1組が離婚を選ぶといわれています。離婚が珍しくない世の中ですが、一度人生を共にすると決めた相手との別れはできれば経験したくないものですよね。結婚生活を成功させる秘訣があれば、と思う人も少なくないでしょう。
今回はアメリカの心理学者で、ワシントン大学に作られた「ラブ(愛情)研究所」での調査結果から夫婦関係を再生させる秘訣も導き出したジョン・M・ゴットマン博士の著書をもとに、結婚生活に必要なことは何なのかをご紹介します。
相手に不満を伝えるときに「非難」「侮辱」の言葉を付け加えてしまうと相手の怒りを引き起こしてしまいますし、「自己弁護」することは問題の責任を相手に押しつけることになってしまいます。そしてこうした要因の末に、問題から目を背ける「逃避」の要因が起きてしまうと、夫婦間の溝は決定的なものになり心は離れていく一方になってしまうのです。
この連鎖が離婚を招くことは想像に難くありません。こうした傾向が見られる場合には、改善を試みる必要があるのです。では、何にポイントを置けば良いのでしょうか?
2:相手への思いやりと感謝の心を育てる
3:相手から逃げず真正面から向き合う
4:相手の意見を尊重する
5:二人で解決できる問題に取り組む
6:二人で行き詰まりを乗り越える
7:二人で分かち合える人生の意義を見つける
博士は夫婦間の関係を良好に保つには、上記の7つの原則を実践すべきだとしています。なお、「愛情地図」の質を高め合うとは相手に対する知識を深めることと言い換えることができます。
1~4の原則は、夫婦に限らず人と関係を持つときに気をつけるべきポイントにもなります。夫婦は生活を共にしているとはいえ、違った環境で育った赤の他人です。考え方や常識が違うのは当たり前なので、相手を理解しようとすることが大切です。その際に相手へのリスペクトの気持ちを忘れず、対等な立場で話をすることを忘れてはいけません。
5~7の原則は、二人のいざこざや乗り越えるべき問題が起きたときに、どう解決していくかを述べています。何かの問題について話すときには感情的にはならず、建設的な話し合いを心がけることが大切です。譲歩は必要ですが、しこりを残さないように妥協はせずに納得できるまで話し合いをしましょう。
時にはどうしても解決できない問題にぶつかることがあります。そんなときは「それは解決しなければいけない問題なのか?」と考えてみましょう。他人である以上、全ての考えを合致させるのは難しいもの。場合によっては解決しない問題として放置してしまっても良いという結論に達しても良いのです。
今回はアメリカの心理学者で、ワシントン大学に作られた「ラブ(愛情)研究所」での調査結果から夫婦関係を再生させる秘訣も導き出したジョン・M・ゴットマン博士の著書をもとに、結婚生活に必要なことは何なのかをご紹介します。
別れるカップルが出すサイン
博士は、離婚の危険があるカップルには「非難」「侮辱」「自己弁護」「逃避」の4つの危険要因が潜んでいるといいます。会話の中でこれらの要因が引き起こされると夫婦関係の溝を深めてしまう害悪になってしまうのです。相手に不満を伝えるときに「非難」「侮辱」の言葉を付け加えてしまうと相手の怒りを引き起こしてしまいますし、「自己弁護」することは問題の責任を相手に押しつけることになってしまいます。そしてこうした要因の末に、問題から目を背ける「逃避」の要因が起きてしまうと、夫婦間の溝は決定的なものになり心は離れていく一方になってしまうのです。
この連鎖が離婚を招くことは想像に難くありません。こうした傾向が見られる場合には、改善を試みる必要があるのです。では、何にポイントを置けば良いのでしょうか?
結婚生活を成功させる7つの原則とは
1:二人で「愛情地図」の質を高め合う2:相手への思いやりと感謝の心を育てる
3:相手から逃げず真正面から向き合う
4:相手の意見を尊重する
5:二人で解決できる問題に取り組む
6:二人で行き詰まりを乗り越える
7:二人で分かち合える人生の意義を見つける
博士は夫婦間の関係を良好に保つには、上記の7つの原則を実践すべきだとしています。なお、「愛情地図」の質を高め合うとは相手に対する知識を深めることと言い換えることができます。
1~4の原則は、夫婦に限らず人と関係を持つときに気をつけるべきポイントにもなります。夫婦は生活を共にしているとはいえ、違った環境で育った赤の他人です。考え方や常識が違うのは当たり前なので、相手を理解しようとすることが大切です。その際に相手へのリスペクトの気持ちを忘れず、対等な立場で話をすることを忘れてはいけません。
5~7の原則は、二人のいざこざや乗り越えるべき問題が起きたときに、どう解決していくかを述べています。何かの問題について話すときには感情的にはならず、建設的な話し合いを心がけることが大切です。譲歩は必要ですが、しこりを残さないように妥協はせずに納得できるまで話し合いをしましょう。
時にはどうしても解決できない問題にぶつかることがあります。そんなときは「それは解決しなければいけない問題なのか?」と考えてみましょう。他人である以上、全ての考えを合致させるのは難しいもの。場合によっては解決しない問題として放置してしまっても良いという結論に達しても良いのです。
結婚生活はよりよくできる
ゴットマン博士はこの本を通して「結婚生活は努力次第で良いものにできる」ということを教えてくれます。博士が提唱する原則は難しいものではないので、結婚生活に悩んでいる人はぜひ実践してみてください。人気の講義ランキングTOP20










