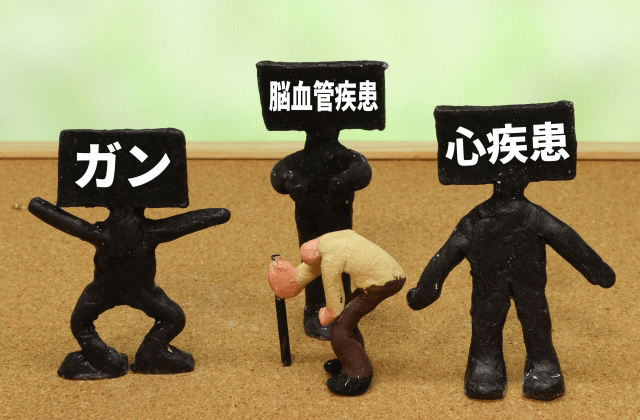
50代に多い「病気」とは?
年齢を重ねることで、体力が低下し、病気やケガのリスクは高まります。加齢の健康課題としてあるのが筋肉量の低下です。筋肉量は基礎代謝に大きく影響し、基礎代謝量は10代後半をピークに低下していき、40代を境に50代で急激に下がる傾向があります。今回は、人生の岐路ともいえる50代に多い病気について調べてみました。
この資料で50代の気になる病気としてあげられているのが、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症(高コレステロール血症等)」「腰痛症」「うつ病やその他こころの病気」でした。
そのほとんどが生活習慣病ともいえ、日頃の不摂生が原因と考えられます。また、加齢による筋力低下による腰痛や、更年期によるホルモンバランスの影響とも考えられているうつ病などが特徴的です。
死因の第1位である「がん」については40代後半から発症リスクが急激に上昇します。部位でみていくと大腸がんが最も多く、胃がん、肺がんと続きます。
また、男性特有のがんである前立腺がんは50歳ごろから急激に発症リスクが高まることも知っておいたほうがよいでしょう。
死因の第3位は「心疾患」。代表的な病名としては、「狭心症」、「心筋梗塞」です。肥満や高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙といった生活習慣に関連づけられ、血管や筋肉が老化することによって機能が低下していくため、50歳という加齢そのものが原因と考えられます。
死因の第4位「脳血管疾患」も、高血圧や動脈硬化によって血管が詰まったり破れたりと、第3位の「心疾患」と関連づけられ、50代から急増する病気になります。
その他、50代に多い病気には、「緑内障」「白内障」といった眼の病気、女性に多くみられるのは、「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」や「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」「更年期障害」があります。
なお、50代になると、ダイエットをしていないのに急に痩せるといった症状が出る場合があります。「がん」や「糖尿病」、「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」、「胃・十二指腸潰瘍」などの原因が考えられるので、内科や消化器内科、婦人科などで、症状に応じてはやめの受診をオススメします。
50代で気になる病気
平成28年度国民生活基礎調査・健康・通院者数から各年代の頻度の高い最も気になる傷病をリスト化した厚生労働省の資料があります。この資料で50代の気になる病気としてあげられているのが、「高血圧症」「糖尿病」「脂質異常症(高コレステロール血症等)」「腰痛症」「うつ病やその他こころの病気」でした。
そのほとんどが生活習慣病ともいえ、日頃の不摂生が原因と考えられます。また、加齢による筋力低下による腰痛や、更年期によるホルモンバランスの影響とも考えられているうつ病などが特徴的です。
50代の死因となる病気
50代の死因となる病気を厚生労働省の資料でみると、第1位「悪性新生物=癌、腫瘍」、第3位「心疾患」、第4位「脳血管疾患」と並びます。第2位の自殺も心の病として、「ミッドライフクライシス」としても象徴的です。死因の第1位である「がん」については40代後半から発症リスクが急激に上昇します。部位でみていくと大腸がんが最も多く、胃がん、肺がんと続きます。
また、男性特有のがんである前立腺がんは50歳ごろから急激に発症リスクが高まることも知っておいたほうがよいでしょう。
死因の第3位は「心疾患」。代表的な病名としては、「狭心症」、「心筋梗塞」です。肥満や高血圧、脂質異常、高血糖、喫煙といった生活習慣に関連づけられ、血管や筋肉が老化することによって機能が低下していくため、50歳という加齢そのものが原因と考えられます。
死因の第4位「脳血管疾患」も、高血圧や動脈硬化によって血管が詰まったり破れたりと、第3位の「心疾患」と関連づけられ、50代から急増する病気になります。
その他、50代に多い病気には、「緑内障」「白内障」といった眼の病気、女性に多くみられるのは、「骨粗鬆症(こつそしょうしょう)」や「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」「更年期障害」があります。
なお、50代になると、ダイエットをしていないのに急に痩せるといった症状が出る場合があります。「がん」や「糖尿病」、「甲状腺機能亢進症(バセドウ病)」、「胃・十二指腸潰瘍」などの原因が考えられるので、内科や消化器内科、婦人科などで、症状に応じてはやめの受診をオススメします。
<参考サイト> ・厚生労働省:年代別・世代別の課題(その2)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000528279.pdf
・厚生労働省:第8表 死因順位1)(第5位まで)別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth8.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000528279.pdf
・厚生労働省:第8表 死因順位1)(第5位まで)別にみた年齢階級・性別死亡数・死亡率(人口10万対)・構成割合
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii09/deth8.html
人気の講義ランキングTOP20
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
長谷川眞理子
明日はわが身?水道管破損と道路陥没~水から考える未来
テンミニッツ・アカデミー編集部







