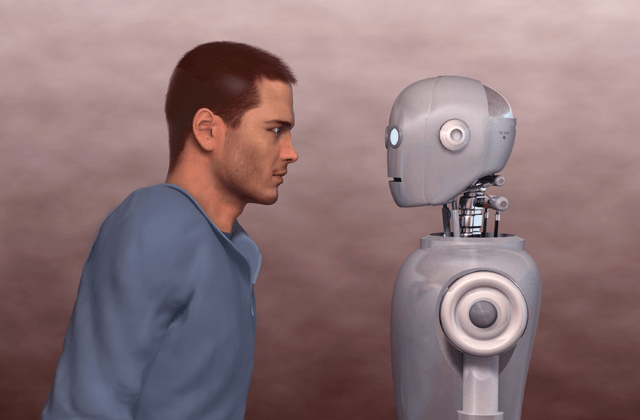
ロボットにも奪われない「将来も安泰な仕事」って!?
景気が良くなると、商品やサービスがよく売れるようになるので人手不足になり、雇用が改善し、失業率が下がる。逆に景気が悪くなると、ものが売れなくなるので、人手が余り、雇用が悪化し、失業率が上がる。
私たちが、いい仕事にありつけるかどうかは、このように経済の状態が大きく関わっている。要するに、景気が良ければ、仕事も見つかりやすいし、給料も上がりやすい。逆に景気が悪ければ、仕事はなかなか見つからないし、給料も上がりにくくなる。
技術的失業というのは、人間のしていた仕事を、機械が代わりに行うことで生まれる失業のことだ。
機械が人間の仕事を奪うという現象は、実は200年以上前にもあった。19世紀前半頃、産業革命真っ最中のイギリスでの出来事だ。
それまで職人の手で織られていた織物が、水力や蒸気機関の力で動く機械によって大量生産されるようになっていったのだ。機械の力で大量に安く出来るようになった結果、従来の職人たちは仕事を失い、やがて機械を打ちこわしてまわる暴動(ラッダイト運動)まで発生するようになった。
農業や資源の採掘のような一次産業、織物のような原料を商品に加工する二次産業が機械化し生まれた大量の余剰労働力は、事務仕事や企画、接客やサービスの提供といった三次産業へと流れていった。
その結果、オフィスワークや飲食やレジャー、情報産業など様々なサービスが開発され、豊かな消費社会が生まれた。つい100年や200年前は、一次産業や二次産業に従事する労働者がほとんどだったのだ。
つまり人間がやってきた仕事を機械が代わって行うことで、人間の労働力は一次産業から二次産業へ、二次産業から、三次産業へと大きくシフトしていった。
さて、現代は、コンピュータ技術とロボットの精密化によって、三次産業の分野にまで機械が進出してきている。
データ入力、会計、法務、レジ打ち、株の取引き、音楽の演奏、記事の執筆、接客、運転、音楽プロデュース、デザイン、料理、マッサージ...etc.
こういった仕事が次々と機械にとって代わられつつある。三次産業の次は、人間はどこへ向かえばいいのだろうか?
しかし、この人たちは全体から見れば極めて少数のエリート。一部の人しかそういった能力は持ち合わせていないし、また一部の人間しか、そもそも必要ではないのだ。
一方、同じ企画、会計、法務、プログラマーでも、上記のような人々から指示をもらって仕事をしていた人たちは、機械に仕事を奪われていくだろう。
だから、指示を待つというよりも、自らプロジェクトを作っていくような動きをする人材がこれからは求められるということだ。
また、手仕事でこだわりの製品やサービスを作る人も残っていくだろう。手間暇をかけたハンドメイドのぬくもりや、ひとつひとつ丁寧に育てた肉や野菜、まだまだ機械には追いつけない細やかで配慮の行き届いたサービスなど、少数しか供給できないが、高付加価値な仕事はこれからも残っていくだろう。
その他にも、経済的な競争から降りてしまって、自給自足のコミュニティを作るという、ハイテクに逆行する動きもあり得る。幸せに暮らすためには、世の中の流れに常に追いついていなければならないというわけではない。
私たちが、いい仕事にありつけるかどうかは、このように経済の状態が大きく関わっている。要するに、景気が良ければ、仕事も見つかりやすいし、給料も上がりやすい。逆に景気が悪ければ、仕事はなかなか見つからないし、給料も上がりにくくなる。
景気ではなく、技術が雇用悪化の原因に?
しかし、今後は景気の良し悪しに関わらず、どんどん人が切られていくという説がある。それは、「技術的失業」と呼ばれる。技術的失業というのは、人間のしていた仕事を、機械が代わりに行うことで生まれる失業のことだ。
機械が人間の仕事を奪うという現象は、実は200年以上前にもあった。19世紀前半頃、産業革命真っ最中のイギリスでの出来事だ。
それまで職人の手で織られていた織物が、水力や蒸気機関の力で動く機械によって大量生産されるようになっていったのだ。機械の力で大量に安く出来るようになった結果、従来の職人たちは仕事を失い、やがて機械を打ちこわしてまわる暴動(ラッダイト運動)まで発生するようになった。
技術的失業が豊かな社会を作っていった
しかし、暴動も長くは続かなかった。技術的失業のショックは、今までになかった新たな雇用が生まれることで、ゆるやかに吸収されていったのだ。農業や資源の採掘のような一次産業、織物のような原料を商品に加工する二次産業が機械化し生まれた大量の余剰労働力は、事務仕事や企画、接客やサービスの提供といった三次産業へと流れていった。
その結果、オフィスワークや飲食やレジャー、情報産業など様々なサービスが開発され、豊かな消費社会が生まれた。つい100年や200年前は、一次産業や二次産業に従事する労働者がほとんどだったのだ。
つまり人間がやってきた仕事を機械が代わって行うことで、人間の労働力は一次産業から二次産業へ、二次産業から、三次産業へと大きくシフトしていった。
さて、現代は、コンピュータ技術とロボットの精密化によって、三次産業の分野にまで機械が進出してきている。
データ入力、会計、法務、レジ打ち、株の取引き、音楽の演奏、記事の執筆、接客、運転、音楽プロデュース、デザイン、料理、マッサージ...etc.
こういった仕事が次々と機械にとって代わられつつある。三次産業の次は、人間はどこへ向かえばいいのだろうか?
これからも残る仕事と働き方
今後、まだまだ安泰なのは、まずは機械に指示を与える側の人間だろう。商品やサービスの企画やマーケティングをしたり、会計や法務でも特に中心的な部分を担ったり、複雑な機械やコンピュータの設計をする立場の人々だ。高度な知識とともに、創造的な能力も問われる。しかし、この人たちは全体から見れば極めて少数のエリート。一部の人しかそういった能力は持ち合わせていないし、また一部の人間しか、そもそも必要ではないのだ。
一方、同じ企画、会計、法務、プログラマーでも、上記のような人々から指示をもらって仕事をしていた人たちは、機械に仕事を奪われていくだろう。
だから、指示を待つというよりも、自らプロジェクトを作っていくような動きをする人材がこれからは求められるということだ。
また、手仕事でこだわりの製品やサービスを作る人も残っていくだろう。手間暇をかけたハンドメイドのぬくもりや、ひとつひとつ丁寧に育てた肉や野菜、まだまだ機械には追いつけない細やかで配慮の行き届いたサービスなど、少数しか供給できないが、高付加価値な仕事はこれからも残っていくだろう。
その他にも、経済的な競争から降りてしまって、自給自足のコミュニティを作るという、ハイテクに逆行する動きもあり得る。幸せに暮らすためには、世の中の流れに常に追いついていなければならないというわけではない。
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部







