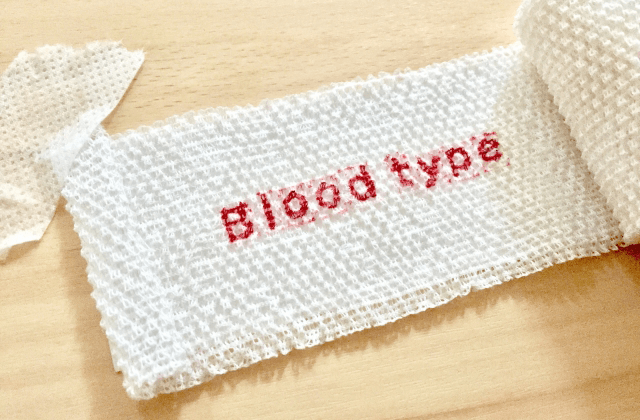
なぜ血液型にC型がないのか?
血液型といえばまずは「A」「B」「O」「AB」で表すABO式血液型が思い浮かびます。しかしよく考えてみると、なぜ「A」「B」と順番になっているのに次が「O型」なのでしょうか。ここにはなにか特別な理由が隠れているのかもしれません。ここでは血液型の歴史を少し振り返って調べてみましょう。
ABO式血液型に関する論文「正常なヒトの血液の凝集反応について」が発表されたのは、1901年11月14日のこと。発表したのはウィーン大学(当時オーストリア・ハンガリー帝国)の病理学研究室で主に解剖を手伝う助手として雇われていたカール・ラントシュタイナー(1868-1943)です。このとき彼はまだ32歳で、医学の学位は持っていたものの博士ではなかったとのことです。
彼は人の血液を混ぜると「凝集反応」が起きて血液が固まることに注目し、同僚たちの血液をもとに実験を行います。そうして血液が凝集する場合と凝集しない場合それぞれの組み合わせを発見し、血液をアルファベット順に「A型」「B型」「C型」の3種類に分けました。つまりこのときには「C型」があったわけです。次いで1902年には、同僚の研究者たちによってのちに「AB型」となる第4の血液型が発表されます。
1910年になって第4の血液型は「AB型」という名前になります。このとき「C型」は「O型」へと名称が変更されます。このときなぜ「O型」になったのかという点ですが、実はこれには諸説あります。「A型」と「B型」の成分を混ぜると凝集してしまいますが、「C型」では凝集がおきません(A、Bどちらの抗原も持っていない)。このことから「C型」は「0型(ゼロ型)」ともよばれたようです。
一つ目の説は、この「ゼロ型」が変化して「O(オー)」と呼ばれるようになったというものです。文書として印刷される際、0(ゼロ)がO(オー)と印刷されるミスが起き、その後「O(オー)型」が標準になったというもの。つまり見間違え説です。もう一つの有力な説は、ドイツ語で「~ない」を意味する「ohne」の頭文字を取ったというものがあります。ともあれ、こののち1927年には国際連盟の専門委員会にて血液型は正式に「A」「B」「O」「AB」を用いることが決定します。
実は血液型は完全にこの4種類だけというわけではありません、他にもよく知られているのはRh因子による区別があります。ラントシュタイナーは1930年にノーベル医学・生理学賞を受賞したのち1940年に弟子のウィーナーとともにRh抗原の有無によっても血液が分類されることを発見します。このRh抗原による分類上での「Rh陰性」という表現は、いくつかのRh抗原のうちD抗原と呼ばれるものがない状態を意味します。
一般的にRh陽性(+)が多く、Rh陰性(-)の出現頻度は、白人の場合で15%程度、日本人に至っては0.5%とたいへん低くなっています。特に日本では珍しい血液型と言えます。ほかにもまれな血液型としては、日本では20種類以上が登録されています。たとえばp(スモールピー)、-D-(バーディーバー)、Ko(ケーゼロ)といったものがあるようです。日本赤十字社によるとこれらまれな血液型に該当する献血者の血液は、10年の間マイナス80度以下で冷凍保存されるそうです。
はじめは「A型」「B型」「C型」だった
ABO式血液型に関する論文「正常なヒトの血液の凝集反応について」が発表されたのは、1901年11月14日のこと。発表したのはウィーン大学(当時オーストリア・ハンガリー帝国)の病理学研究室で主に解剖を手伝う助手として雇われていたカール・ラントシュタイナー(1868-1943)です。このとき彼はまだ32歳で、医学の学位は持っていたものの博士ではなかったとのことです。
彼は人の血液を混ぜると「凝集反応」が起きて血液が固まることに注目し、同僚たちの血液をもとに実験を行います。そうして血液が凝集する場合と凝集しない場合それぞれの組み合わせを発見し、血液をアルファベット順に「A型」「B型」「C型」の3種類に分けました。つまりこのときには「C型」があったわけです。次いで1902年には、同僚の研究者たちによってのちに「AB型」となる第4の血液型が発表されます。
「O型」はゼロから? それともドイツ語の「ohne」から?
1910年になって第4の血液型は「AB型」という名前になります。このとき「C型」は「O型」へと名称が変更されます。このときなぜ「O型」になったのかという点ですが、実はこれには諸説あります。「A型」と「B型」の成分を混ぜると凝集してしまいますが、「C型」では凝集がおきません(A、Bどちらの抗原も持っていない)。このことから「C型」は「0型(ゼロ型)」ともよばれたようです。
一つ目の説は、この「ゼロ型」が変化して「O(オー)」と呼ばれるようになったというものです。文書として印刷される際、0(ゼロ)がO(オー)と印刷されるミスが起き、その後「O(オー)型」が標準になったというもの。つまり見間違え説です。もう一つの有力な説は、ドイツ語で「~ない」を意味する「ohne」の頭文字を取ったというものがあります。ともあれ、こののち1927年には国際連盟の専門委員会にて血液型は正式に「A」「B」「O」「AB」を用いることが決定します。
Rh-、p(スモールピー)、-D-(バーディーバー)、Ko(ケーゼロ)
実は血液型は完全にこの4種類だけというわけではありません、他にもよく知られているのはRh因子による区別があります。ラントシュタイナーは1930年にノーベル医学・生理学賞を受賞したのち1940年に弟子のウィーナーとともにRh抗原の有無によっても血液が分類されることを発見します。このRh抗原による分類上での「Rh陰性」という表現は、いくつかのRh抗原のうちD抗原と呼ばれるものがない状態を意味します。
一般的にRh陽性(+)が多く、Rh陰性(-)の出現頻度は、白人の場合で15%程度、日本人に至っては0.5%とたいへん低くなっています。特に日本では珍しい血液型と言えます。ほかにもまれな血液型としては、日本では20種類以上が登録されています。たとえばp(スモールピー)、-D-(バーディーバー)、Ko(ケーゼロ)といったものがあるようです。日本赤十字社によるとこれらまれな血液型に該当する献血者の血液は、10年の間マイナス80度以下で冷凍保存されるそうです。
<参考>
山本文一郎、『血液型が分かる科学』、岩波ジュニア新書、2015年
血液型の分類にもともと「C型」があったことをご存じですか?|ブルーバックス編集部
https://gendai.media/articles/-/76819
血液型について│日本赤十字社
https://www.bs.jrc.or.jp/kk/hyogo/donation/m2_02_01_00_bloodtype.html
山本文一郎、『血液型が分かる科学』、岩波ジュニア新書、2015年
血液型の分類にもともと「C型」があったことをご存じですか?|ブルーバックス編集部
https://gendai.media/articles/-/76819
血液型について│日本赤十字社
https://www.bs.jrc.or.jp/kk/hyogo/donation/m2_02_01_00_bloodtype.html
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







