テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
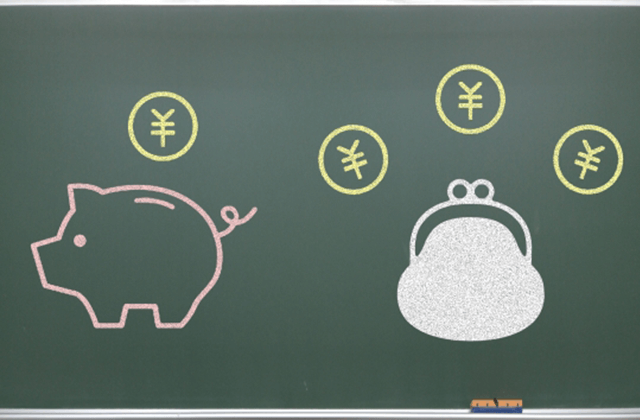
最低限身につけておきたい「金融リテラシー」
お金は人生を豊かにする一方で、関わり方を間違えば苦しみの元ともなります。お金と無縁で生きていくことはできません。だからこそお金との付き合い方が大事です。このとき必要なものが「金融リテラシー」です。これはお金に関する知識や判断能力のことを意味しています。ここでは「金融リテラシー」とはどういうものなのかという点について、もう少し詳しく考えてみましょう。
つまり欲望をコントロールして、必要なときに必要なものにお金を注げるようにすることが大事です。考えてみれば、子供の頃から私たちはこの問題にぶつかってきています。お年玉やお小遣いをどう使うべきか、考えたはずです。ただし、子供の頃は自分の欲しいものだけにお金を注げたかもしれませんが、大人になればそうはいきません。車や家をローンで購入したり、将来のために貯蓄や投資をしたり、何かあった時のために保険代を支払ったり。つまり、未来に向けたお金の運用が必要になります。こういった判断をするには、ある程度大きい金額と長いスパンをイメージしながら、さまざまな情報を集めて検討する必要があります。
【家計管理】
「家計管理」とは、毎月の収支を黒字に保つ習慣を身につけておくことです。これは毎月の出費をどう抑えるかということが基本となります。つまり「お金をどう使うか」ということに関するものです。黒字を保つには、特に固定費の見直しに効果があるようです。これには家賃や水道光熱費、通信料、車の維持費、各種サブスクリプション契約などが考えられます。ここを見直す際には、いきなり何かを取りやめたり大きく変えたりすると、生活に大きな影響がでて苦しくなることもあります。まずはこれらにかかっている費用を明確にしてから、じっくり考えて削れるところに手をつけることが大事です。
【生活設計】
「生活設計」は、おおよそ出費が必要となる時期に向けて資金を準備しておくことです。人が生きていく上でのライフイベントは大きく「就職」「結婚」「出産」「教育」「住宅」「介護」「老後」といったものが考えられます。このときにはある程度のお金が必要となるので、この時期をイメージしながら、資金を準備する必要があります。特に政府広報オンラインでは「教育費」「住宅の購入費」「老後の生活費」の3つを人生の三大費用として強調しています。ただし「生活設計」は「家計管理」において、ある程度の黒字が確保できていることが前提となります。
【金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル】
こういった備えをする際に「貯蓄」したり、余裕資金を「投資」に回したり、「保険」に加入したりして生活を防衛しておく必要が生まれます。「貯蓄」は収支管理を黒字に保つことができれば可能です。ただし「貯蓄」するだけでは資産は目減りする可能性があることから、一定程度「投資」に回すことが現代では推奨されています。また「保険」にもさまざまな種類がありますが、自身である程度の知識をもって選ばなければ、支払いが苦しくなることもあります。
また、ローンやリボ払いを契約する際には必ず利子を払わなければなりません。契約によっては多額の利子となるものもあります。また自身がいつまでも健康を維持して働き続けられる訳ではありません。無理のない返済計画を立てる必要があります。こういった問題にしっかり対処するためには、「利息・利子」や「投資のリスク」、「保険の仕組み」といったことを知り、何を重視して何を選び取るか決める必要があります。
金融庁のウェブサイトには、高校の出張講座に使われる資料が公開されています。自治体ではセミナーが開かれていることもあるようです。また金融リテラシーに関する知識をまとめた書籍や雑誌も多く出回っています。さらにインターネット上では、証券会社や銀行などの金融機関が無料で配信している動画もあります。まずは興味をもった情報に触れてみましょう。ただしSNSなどでは偽情報も出回っており、投資詐欺のリスクもあります。また一個人が自分の仕事をしながら、金融に関連するあらゆることに意識を向けて生きていくことは難しい場合もあります。こういった場合、必要なときに専門家に相談することも大事です。
「金融リテラシー」はお金と欲望をコントロールする力
政府広報オンラインによると、金融リテラシーとは「経済的に自立し、より良い生活を送るために必要なお金に関する知識や判断力のこと」とされています。人は「何かを手に入れたい」「どこかに行きたい」「詳しく知りたい」「安全が欲しい」などといった、さまざまな願望や希望を含んだ「欲望」を抱いて生きています。これらが自分をより前進させ、より豊かな環境や心身の安全・安定を手にするための力になります。一方でこれがうまくいかないと不満が残る不自由を感じます。これらの欲望はある程度のお金がないと叶えることはできません。また欲望の全てを叶えることは一般的に不可能です。つまり欲望をコントロールして、必要なときに必要なものにお金を注げるようにすることが大事です。考えてみれば、子供の頃から私たちはこの問題にぶつかってきています。お年玉やお小遣いをどう使うべきか、考えたはずです。ただし、子供の頃は自分の欲しいものだけにお金を注げたかもしれませんが、大人になればそうはいきません。車や家をローンで購入したり、将来のために貯蓄や投資をしたり、何かあった時のために保険代を支払ったり。つまり、未来に向けたお金の運用が必要になります。こういった判断をするには、ある程度大きい金額と長いスパンをイメージしながら、さまざまな情報を集めて検討する必要があります。
「金融リテラシー」3つのポイント
「金融リテラシー」の中身に関して政府広報オンラインでは、大きく次の3つの分野に分けて考えられています。一つ目は「家計管理」、二つ目は「生活設計」、三つ目は「金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル」です。それぞれ詳しくみてみましょう。【家計管理】
「家計管理」とは、毎月の収支を黒字に保つ習慣を身につけておくことです。これは毎月の出費をどう抑えるかということが基本となります。つまり「お金をどう使うか」ということに関するものです。黒字を保つには、特に固定費の見直しに効果があるようです。これには家賃や水道光熱費、通信料、車の維持費、各種サブスクリプション契約などが考えられます。ここを見直す際には、いきなり何かを取りやめたり大きく変えたりすると、生活に大きな影響がでて苦しくなることもあります。まずはこれらにかかっている費用を明確にしてから、じっくり考えて削れるところに手をつけることが大事です。
【生活設計】
「生活設計」は、おおよそ出費が必要となる時期に向けて資金を準備しておくことです。人が生きていく上でのライフイベントは大きく「就職」「結婚」「出産」「教育」「住宅」「介護」「老後」といったものが考えられます。このときにはある程度のお金が必要となるので、この時期をイメージしながら、資金を準備する必要があります。特に政府広報オンラインでは「教育費」「住宅の購入費」「老後の生活費」の3つを人生の三大費用として強調しています。ただし「生活設計」は「家計管理」において、ある程度の黒字が確保できていることが前提となります。
【金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル】
こういった備えをする際に「貯蓄」したり、余裕資金を「投資」に回したり、「保険」に加入したりして生活を防衛しておく必要が生まれます。「貯蓄」は収支管理を黒字に保つことができれば可能です。ただし「貯蓄」するだけでは資産は目減りする可能性があることから、一定程度「投資」に回すことが現代では推奨されています。また「保険」にもさまざまな種類がありますが、自身である程度の知識をもって選ばなければ、支払いが苦しくなることもあります。
また、ローンやリボ払いを契約する際には必ず利子を払わなければなりません。契約によっては多額の利子となるものもあります。また自身がいつまでも健康を維持して働き続けられる訳ではありません。無理のない返済計画を立てる必要があります。こういった問題にしっかり対処するためには、「利息・利子」や「投資のリスク」、「保険の仕組み」といったことを知り、何を重視して何を選び取るか決める必要があります。
高リテラシー層が気をつけていること
金融広報中央委員会が2022年に行った調査「金融リテラシー調査2022」によると、高リテラシー層(調査での正誤問題の正答率が 80%を超える層)は、他の層と比較すると「金融・経済情報を見る頻度が高い」、「家計管理をしっかり行っている」、「金融商品の内容を理解したうえで商品を選択している」「損失回避傾向および横並び意識が弱い」といった4つの特徴があるとされています。ここまでに挙げた「家計管理」や「金融と経済の基礎知識と、金融商品を選ぶスキル」に関してかなり意識を持っていることがわかります。金融庁のウェブサイトには、高校の出張講座に使われる資料が公開されています。自治体ではセミナーが開かれていることもあるようです。また金融リテラシーに関する知識をまとめた書籍や雑誌も多く出回っています。さらにインターネット上では、証券会社や銀行などの金融機関が無料で配信している動画もあります。まずは興味をもった情報に触れてみましょう。ただしSNSなどでは偽情報も出回っており、投資詐欺のリスクもあります。また一個人が自分の仕事をしながら、金融に関連するあらゆることに意識を向けて生きていくことは難しい場合もあります。こういった場合、必要なときに専門家に相談することも大事です。
<参考>
「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201404/1.html
「金融リテラシー」とは?お金の知識を身に付ける必要性や高めるメリットを解説!│伊予銀行
https://www.iyobank.co.jp/sp/iyomemo/entry/20221027.html
「金融リテラシー調査2022年」の結果|知るぽると(金融広報中央委員会)
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2022/pdf/22literacyr.pdf
高校生向け授業動画・教員向け解説動画|金融庁
https://www.fsa.go.jp/ordinary/douga.html
「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201404/1.html
「金融リテラシー」とは?お金の知識を身に付ける必要性や高めるメリットを解説!│伊予銀行
https://www.iyobank.co.jp/sp/iyomemo/entry/20221027.html
「金融リテラシー調査2022年」の結果|知るぽると(金融広報中央委員会)
https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/literacy_chosa/2022/pdf/22literacyr.pdf
高校生向け授業動画・教員向け解説動画|金融庁
https://www.fsa.go.jp/ordinary/douga.html
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










