テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
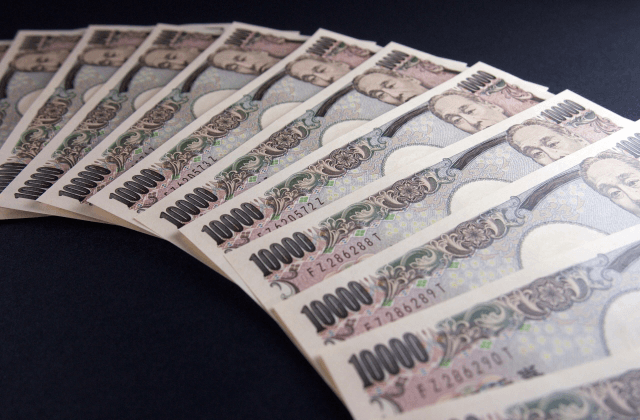
これから資産運用を始める人のための3つの原則~NISA、投資信託、分散投資
現代は超低金利の時代。銀行にお金を置いておくだけでは、タンス預金とたいして大して変わりはない。なにかしらの投資を行い、眠っているお金にも活躍してもらおうと考えるのは間違いではないだろう。
投資とひとくくりにいっても、さまざまな形がある。まず思いつくのは株式ではないだろうか。しかし、これは素人が手を出してはならない。なぜなら、プロ集団が大量の情報をもとに秒単位で売り買いしているからだ。個人ひとりがここで利益を上げるには、毎日ひたすら画面にくぎ付けになるしかない。何秒か遅れれば、一気に資金を失う危険性さえもある。
NISA口座はネットの証券会社でつくることをおススメする。ネットでは相談窓口がない分、手数料が安く、さらに証券会社は銀行よりも幅広い商品を揃えている。
NISA制度をうまく使えば、お得に投資を始めることができる。さらに投資信託を買えば、個人で株を買うリスクを軽減することができる。このことから一般的な投資初心者に対しては、なによりもこの方法をおススメしたい。では、どのような投資信託を買うのか。一つ言えることは、とにかく分散投資である。
リスク許容度20%で、国内債券型30%・海外債券型20%・国内株式型30%・海外株式型20%というものだ。リスク許容度に関しては、本人がその資金のどの程度を失っても構わないと考えるかということ。投資信託の種類は、リスクの低い順に、国内債券型・海外債券型・バランス型・国内株式型・海外株式型となる。このポートフォリオから自分がどの程度リスクを背負えるかということによって、比率を調整していくといい(もちろんリスクが低ければリターンも低い、その逆もしかりである)。
また、それぞれの中でもおススメはインデックス投資。これは一定の範囲の指標に連動して金額が自動的に動く仕組みである。人の手が介入していない分、運用コストを抑えることができる。
投資信託での資産運用は、運用期間を長期化すればするほどリスクは安定し、リターンが大きくなることが知られている。もちろん状況によって一気に全体の価格が下がることもあり得る。それでも過去のデータを見れば、数年後には必ず値戻りしている。投資信託を買う上で大事なことは、多少の変動に不安にならず、状況を見ながら分散投資を行っていくことだろう。
投資とひとくくりにいっても、さまざまな形がある。まず思いつくのは株式ではないだろうか。しかし、これは素人が手を出してはならない。なぜなら、プロ集団が大量の情報をもとに秒単位で売り買いしているからだ。個人ひとりがここで利益を上げるには、毎日ひたすら画面にくぎ付けになるしかない。何秒か遅れれば、一気に資金を失う危険性さえもある。
投資信託
ここで役に立つのが投資信託である。専門家に手数料を払って投資をお任せするものだ。投資信託にもさまざまな種類がある。例えば国内株式型、国内債券型、外国株式型、また外国不動産などなど、他にもバイオテクノロジー関連株など細かく分野が区切られた商品もある。商品を購入すると、資金をもとにプロが投資を代行してくれる。だがプロ投資家が損失を補填してくれるというものではないことは理解しておこう。投資には元本保証はない。NISA
NISA口座で投資をすれば、毎年、投資金額100万円分までの株式投資や投資信託にかかる値上がり益や配当金(分配金)が非課税となる(現行では2027年12月で終了予定。なお2016年から非課税枠は120万円へと増額)。つまり、毎年100万円までの非課税投資枠が得られる制度だ。ただし、最長5年間、つまり最大500万円までの投資に限定される。それ以上の投資は課税対象となる点には注意が必要だ。NISA口座はネットの証券会社でつくることをおススメする。ネットでは相談窓口がない分、手数料が安く、さらに証券会社は銀行よりも幅広い商品を揃えている。
NISA制度をうまく使えば、お得に投資を始めることができる。さらに投資信託を買えば、個人で株を買うリスクを軽減することができる。このことから一般的な投資初心者に対しては、なによりもこの方法をおススメしたい。では、どのような投資信託を買うのか。一つ言えることは、とにかく分散投資である。
分散投資(アセットアロケーション)
リスクを分散させるのは投資の大原則である。比較的リスクが高めの商品を含めつつ、安定的な商品を多めに買うことによってローリスクで利益を上げることが可能になる。どの程度のリスクを取るか。年齢や収入の違い、資産運用の目的などによって、分散方法は変わってくる。ここでは標準的なポートフォリオ(買い方)を紹介する。リスク許容度20%で、国内債券型30%・海外債券型20%・国内株式型30%・海外株式型20%というものだ。リスク許容度に関しては、本人がその資金のどの程度を失っても構わないと考えるかということ。投資信託の種類は、リスクの低い順に、国内債券型・海外債券型・バランス型・国内株式型・海外株式型となる。このポートフォリオから自分がどの程度リスクを背負えるかということによって、比率を調整していくといい(もちろんリスクが低ければリターンも低い、その逆もしかりである)。
また、それぞれの中でもおススメはインデックス投資。これは一定の範囲の指標に連動して金額が自動的に動く仕組みである。人の手が介入していない分、運用コストを抑えることができる。
投資信託での資産運用は、運用期間を長期化すればするほどリスクは安定し、リターンが大きくなることが知られている。もちろん状況によって一気に全体の価格が下がることもあり得る。それでも過去のデータを見れば、数年後には必ず値戻りしている。投資信託を買う上で大事なことは、多少の変動に不安にならず、状況を見ながら分散投資を行っていくことだろう。
<参考文献>
・目黒陽子『NISAで始める資産運用』小学館新書 2013年
・目黒陽子『NISAで始める資産運用』小学館新書 2013年
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










