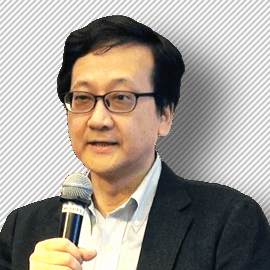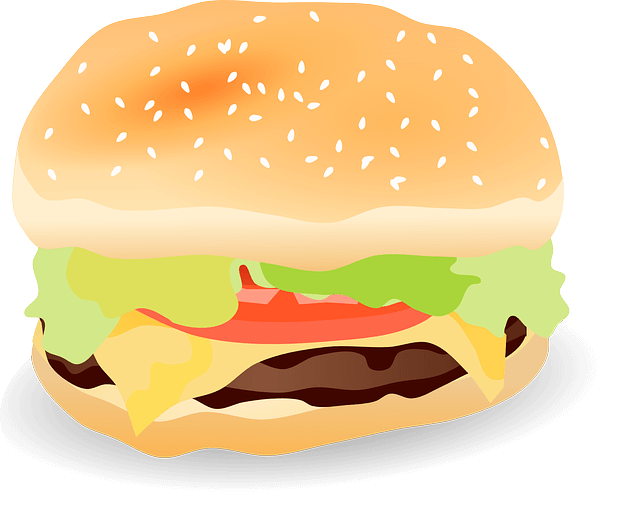●ブランドの議論で使える定義とは何か
ブランドの定義という問題を考えてみましょう。アメリカのマーケティング協会のウェブページによれば、ブランドとは、他とは異なる商品の名前やシンボルです。つまり、他とは区別された名前やシンボルがブランドだというのです。一見、納得する定義ですが、ブランドについて議論しようとする際、これが使える定義なのかどうかが問題です。
商品の名前がブランドだということは当たり前でしょう。しかし、わが社のブランドを強くするためにはどうするかという議論において、この定義はあまり使えません。ブランドをより良くするためには、より良い名前を選ぼう、より格好の良いシンボルを選ぼうという話にしかならないからです。この定義のままだと、それ以上議論が進まなくなってしまいます。
確かに昔のマーケティングの教科書を読むと、ブランドとは名前やシンボルなのだから、良い名前やシンボルを選ぶべきだと書かれています。しかしこの定義では、ブランドを強くしたいと思っても、名前やシンボル以上の議論は出てきません。例えば、人々の間でもっと豊かな連想を生み出させるような名前を選ぶとか、知名度を高めるといった、踏み込んだ議論ができないのです。
また、ブランドとは顧客への約束だという定義もよくなされます。だからこそ、お客さんに対して、しっかりいろんなことを約束しなければならないと、本の中には書かれていたりします。こうした定義自体が悪いわけではないのですが、つまるところ、定義について考えていくとよく分からなくなっていくのです。
ブランドは約束だという定義が問題なのは、ブランドというものについての、いわばアウトプットを表現したものだということです。ブランドの結果は約束だということを示しているわけです。もちろん、何かを定義する場合には、インプットを定義に入れることもあります。
いずれにせよ、例えば昔「芸術は爆発だ」と言った人がいましたが、こうした何らかの原因や結果だけを捉えて、それを定義とするのはあまり好ましくありません。というのも、そのものが何かという性質を、こうした定義ではうまく捉えられないからです。
ブランドの語源は焼きごてだという理解の仕方も、それ以上議論が先に進みません。ブランドというのは、物の所有や区分を表す言葉なのだということに尽きてしまいます。
...