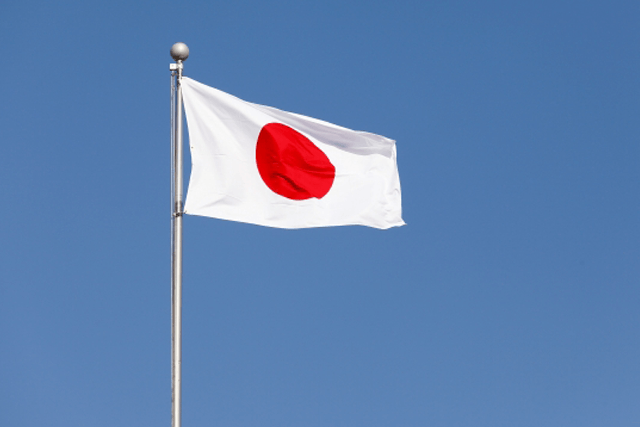●日本での元号の始まりは「大化」
こんにちは。東京大学史料編纂所教授の山本博文です。今日は「元号とはなにか」というお話をしたいと思います。
元号の始まりは、もともと中国の前漢の時代に元号がつくられます。武帝という前漢の皇帝が「建元」を使ったのが最初です。
日本での元号の始まりは「大化」で、西暦645年に制定されます。つまり長い歴史を持つ中国の元号が日本に取り入れられたということになります。
原理的にいえば、元号は「皇帝が、領地や人民だけではなく、時間をも支配する」という観念の現れと見ることができます。
では、なぜ日本に元号は導入されたのでしょうか。西暦645年には中大兄皇子が権勢をふるった蘇我入鹿を殺害して、蘇我氏の本宗家を滅ぼした「乙巳(いっし)の変」がありました。これが契機になって、新しい政治が始まります。その政治を「大化の改新」というわけですが、天皇家中心の世の中になったことを示す、一つの象徴として「大化」という元号が選ばれたと考えられます。
●事があれば使われていた初期の元号
最も初期の元号は、どのように扱われてきたでしょう。大化6(650)年に穴戸国(あなとのくに、山口県西部)の国造である草壁連醜経(しこぶ)という人が、白雉(しろききぎす、白いキジ)を献上します。これは非常にめでたいことだ=「祥瑞」だということで、「白雉(はくち)」という元号に改元します。つまり、大化ー白雉と続くわけです。
白雉5(654)年に孝徳天皇が崩御して、斉明天皇が即位する時に元号は制定されません。つまり白雉以降、改元がなされず、元号の使用は32年間にわたって途絶えるわけです。
その間、斉明天皇が崩御し、唐・新羅の連合軍との戦いである「白村江の戦い」があって、日本は敗北。唐・新羅が攻めてくる心配もあり、国中に城を築いたり、都も大津府にうつす世情となります。やがて天智天皇が即位しますが、死後に「壬申の乱」が起こり、弟である天武天皇が即位します。
天武天皇15(680)年に、今度は赤いキジの献上があって、これは非常にめでたいということで「朱鳥」という元号に改元します。つまり、しばらく使われていなかった元号が、このような祥瑞があったということで、再び国を統一した天武天皇の元で制定されることになるわけです。
天武天皇が崩御して、皇后だった持統天皇が即位します...