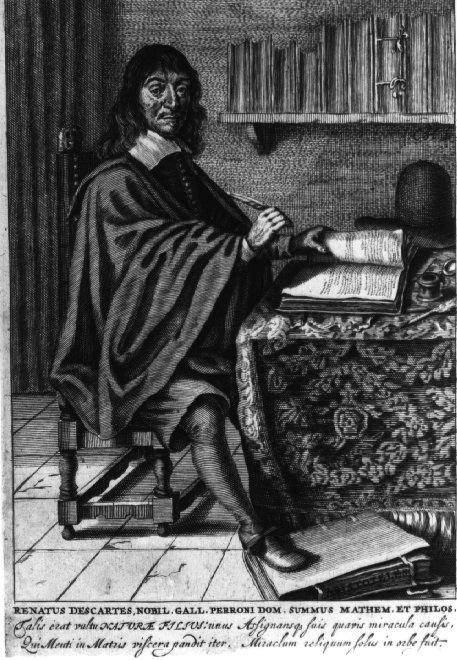●「我思う、ゆえに我在り」はデカルトの専売特許ではない
高校で実際に使われている倫理の教科書を何冊かおもちしました。東京書籍の『倫理』、第一学習社の『倫理』、山川出版社の『現代の倫理』、清水書院の『新倫理』、同じく清水書院の『現代倫理』です。他にも、多くの高校で倫理の授業に使われている教科書がありますが、こうした教科書全てに、デカルトと言えば、こう書いてあるわけです。
「我思う、ゆえに我在り」
これは「彼の専売特許でしょう」と言わんばかりに、倫理の教科書でデカルトについて紹介をしているのです。
これは或る意味、間違いではありません。もちろんデカルトと言えば、「我思う、ゆえに我在り」です。「私は考えているから、私は存在するのだ」ということを明確に宣言した哲学者として記憶に残っていますし、そのことに間違いはないのですが、専売特許というのは少し不正確な理解です。もちろん教科書がそう言っているわけではなく、私がこれらの教科書を読みながらそういう印象を抱いたわけです。いずれにしても、もし「我思う、ゆえに我在り」をデカルトの専売特許と捉えている方がいたとしたら、是非今回のレクチャーを聴いて、デカルトについて理解を深めていただきたいと思います。
なぜならば、同じようなことを実は、4世紀から5世紀にかけて活躍した初期キリスト教会のラテン教父が言っているからです。ラテン教父とは、ラテン語で著作活動を行っていた教父です。教父にはギリシャ教父とラテン教父がいて、ギリシャ教父はギリシャ語で主に著作活動をしていた人です。ここで取り上げたいラテン教父は、4世紀から5世紀にかけて活躍した初期キリスト教会のアウグスティヌスという人で、彼がデカルトと同じようなことを言っているのです。
実際デカルトも、同時代の哲学者も、そのことに気付いていました。「デカルトさん、あなた、そんなことを仰っているけれど、それは本当に自分のオリジナルだと思っているの? アウグスティヌスがすでにもう言っていますよ」と言われて、デカルトも渋々それを認めているというのが実際のところです。
●デカルトの懐疑は「方法的懐疑」と呼ばれる
では一体、この「我思う、ゆえに我在り」に相当する表現はどこに出てくるかというと、デカルトが最初に公刊した『方法序説』...