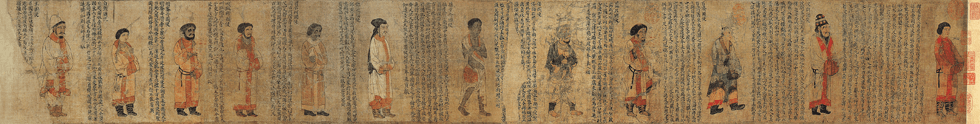●城塞都市という形が生んだ「朝貢」というビジネス形態
では、3回目の『中国の「なぜ」』についてお話ししたいと思います。中国では、我々がよく知っているように「朝貢外交」など、「朝貢」という言葉があります。一体なぜ、中国では「朝貢外交」という言葉があるのか。朝貢を求めるのかということをお話ししたいと思います。
この「朝貢」という意味がわかると、さらに中国という国の権力構造や中国という国は一体何であるのかがわかると思います。
「朝貢」というのは読んで字の如く、「朝」は「朝廷」の「朝」です。これに「貢」(みつぐ)ということになります。では、朝廷というものが王様、国家権力の場所であるという意味は何かと言うと、必ず、王権、王様の権力というものは朝に広場で訓示をするからです。だから「朝の庭」=「朝廷」と言われており、「朝」という字が王権を表す言葉として定着しました。その王権に対する貢物だから「朝貢」と言います。
中国というのは、どちらかと言うと商業の国です。中国はどこに行っても城塞都市です。もともと国というのは囲みですから。つまり城塞があり、囲われたところのなかで権力が集中し、王様あるいは各地域の諸候は必ず城塞のなかに囲われている。日本のように、お城があって周辺に城下町があるのは珍しい。ヨーロッパもそうですが、中心を必ず城塞、城壁で囲むんですね。その外にいる人たちがそのなかに入ることが許されるのは商売です。なかに入ってきて、人参でも肉でも、外でつくってきたものを売りに来る。地域の王様の許可を得て城塞のなかに物を売りに来る。言ってみれば、宮廷や王朝は、もともとは市場のことなのです。そうすると、そこに入ってくるわけだから、入ってくるときに当然、所場代というか、商売をするわけだからいくらか払うわけです。そのいくらか払ったお金というのが税になっていくわけです。
つまり、最初から中国では、巨大な王権ができる前から、各地域で城壁を囲んで、そこに所場代を払って取引に来て、商いをするわけですから、言ってみれば、中国における王様というのは、「ビジネスの総元締め」と考ればいいのです。
●「仲間・味方」と認めつつ、「中心はあくまでも中国」の姿勢
そうしますと、それがどんどん大きくなっていくと、北京でもそうですが、最初は周辺から珍しい物を持って取引に来るけれども、それがだんだ...