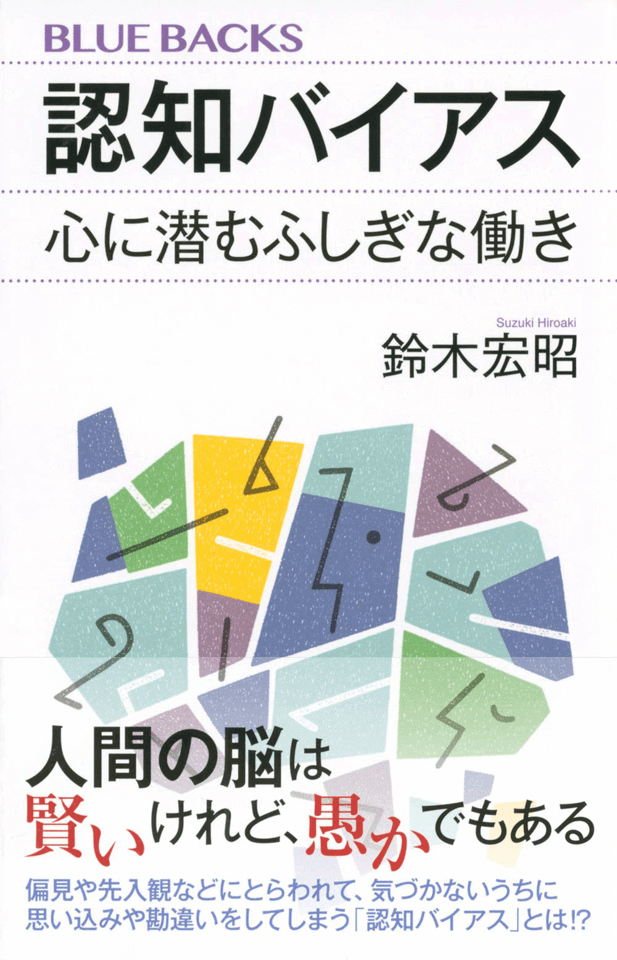●知覚から行動までの「認知」の仕組み
皆さん、こんにちは。これから「認知バイアス入門」というお話をする、鈴木宏昭です。どうぞよろしくお願いします。
私は青山学院大学に長年勤めており、専門は認知科学で、認知心理学などもやっています。心の働き、仕組み、成り立ちなどを研究するのが認知科学です。私は2020年に『認知バイアス 心に潜むふしぎな働き』というタイトルの本を講談社のブルーバックスから出しました。これがきっかけでいろいろな認知バイアスの話をいろいろなところでするようになって、テンミニッツTVでもお話しするという次第です。
まず認知バイアスということを考えるとき、「認知」と「バイアス」を1つずつお話ししていきたいと思います。スライドに図式が出ておりますけれども、まず左側に「世界(状況)」があります。世界というのはいろいろな「情報」を発信しています。
例えば、雷が鳴り、パッと光ってゴロゴロという音がしたとします。こういう状況になると、その視覚的な情報とか、聴覚的な情報は世界から発せられるわけです。そうすると、私たちはそれに対して、「注意」を向けて「知覚」するという心の仕組みを働かせます。
その後、その状況の全てが私たちの処理に関わるわけではありません。スライドに「記憶」と書いていますけれども、詳しくいうと、日常語的な記憶とは少し違いまして、専門的には「ワーキングメモリ」という、私たちの頭の中の作業場のような場所に、その注意を向けた一部の情報が入っています。
スライドに「概念」と書いていますが、私たちはいろいろな知識を持っています。雷だったら雷についてのいろいろなことを知っているわけです。入った情報に対して、そういう知識と照合したり、あるいはそれを使って情報を補ったりして、「あ、雷が鳴った」と気づくというわけです。
そうすると、今度は「思考」という心のメカニズムが働くようになります。そこで例えば、「雨が降っているかも」というようなことに気づくわけです。そこから、雷の例だと「創造」ということはあまりないのですが、場合によってはそこから新しいものを創り出すようなことも起きたりすることもあります。
雷で雨が降るかもしれないというようなことがあると、今度はそれ...