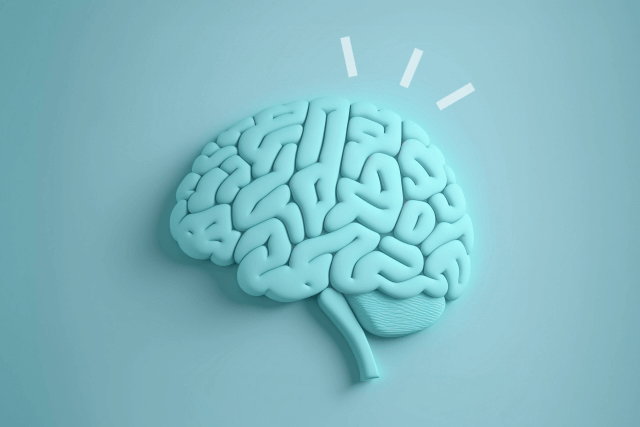●電磁気学の発展によって大きく進展した脳研究
次に、もう一つの柱である、電気的な測定法について説明します。
生物が電気を発生するという現象、いわゆる「生体電気現象」というのは、実は発見が古く、1700年代に発見されていました。これは、カエルの足の筋肉が電気を受けるとピクピクと動くということから、実は生体というのは電気を使って信号や情報をやり取りしているのではないかということが分かってきまして、これが後に「電気生理学」と呼ばれる学問に発展していきます。これを見つけたのはイタリアのガルバニという人ですが、この研究に影響を受けた、同じくイタリアのボルタという人が電池を発明するに至ります。ボルタというのが今、電気の単位となっているボルトの元となったわけですが、この電池の発明を皮切りに、「電磁気学」という学問が発展して、われわれが今使っている家電だとかコンピューターとか、それからインターネットに続いていくわけです。
生体が電気を発生するということが最初にあって、そこから電磁気学が生まれたということが面白いと思いました。
このように、電磁気学の知見が高まって測定技術が発展すると、さらに新しい生体の電気現象が測定できるようになってきまして、これが非常に高まったのが20世紀です。20世紀は「電気生理学黄金時代」とも呼ばれていまして、筋肉だけではなくて、実は脳を作っている脳細胞、ニューロンが電気活動をしているということも次々と明らかになってきました。
この技術を皮切りに、脳の電気活動を測る技術が次々と発展してきまして、特に「細胞外記録法」は革命的な進展をもたらしました。これは、脳に電極を埋め込むことで、生きている動物の電気活動を測ることができるという方法です。これを使って、動物が迷路を解いていくときに、どのように脳活動をしているかということも分かってきました。
【参考動画】
https://youtu.be/lfNVv0A8QvI
これはその研究の一部ですが、迷路を解こうとしているラットが今、自分がどこにいるかということに応じて、別の細胞を活性化しているということを表している研究です。この研究から、脳の中には(...