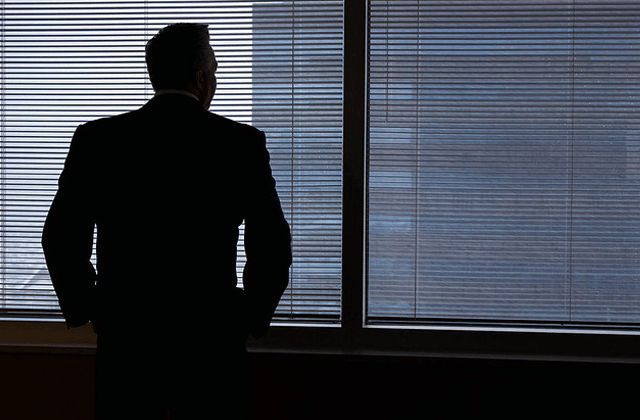
終身雇用に年功序列…日本型雇用はどう変わる?
経済界から終身雇用に関する発言が相次いでいます。「制度疲労を起こしている。終身雇用を前提にすることが限界になっている」、さらに「雇用維持のために事業を残すべきではない」と経団連の中西宏明会長(日立製作所会長)は述べ、経営者に対して新しいビジネスに注力するよう訴えています。また、トヨタ自動車の豊田章男社長も「雇用を続ける企業などへのインセンティブがもう少し出てこないと、なかなか終身雇用を守っていくのは難しい局面に入ってきた」と述べています。
終身雇用・年功序列はこれまでも少しずつ変化してきましたが、いま大きな転換点を迎えているのかもしれません。ここでは、雇用のあり方は今後どのように変化するのか、考えてみましょう。
もちろん、日本の企業も、国際的に戦うにはこういったグローバルに活躍する人材を採用しない手はありません。つまり、現代の企業が求めるのは、その分野におけるスペシャリストです。また、情報社会では旧来の技術先進国だけが技術や資金を独占するのではなく、場所を選ばず新たな事業を起こしたり、資金を集めたりすることが可能です。つまり、プレイヤーはどこからでも参戦できます。このスピード感で考えると、企業の内側に人材を抱え込んでいても、加速化する競争に対抗できないかもしれません。
また、これまで日本企業は全体を見通してバランスを取るジェネラリストを育成してきました。もちろん、企業において一定のジェネラリストは必要かもしれません。しかし、こういった人材を多く育てることは、現代では企業の利益とは合致しにくいと考えていいでしょう。つまり、大所帯で一斉に同じ目的に向けて動くシステムが機能しなくなってきているということではないでしょうか。それよりも、細かくさまざまな分野にアンテナを張り、すばやくアプローチすることによって技術を蓄えたり、商機を掴んだりする力のほうが今は必要なのかもしれません。
終身雇用では「会社がメインで個人はその従属的存在」でした。しかし、今後は「個人が中心となって会社は個人の生活の一場面」となるかもしれません。もちろんこの時、個人が所属する会社は一つとは限らないでしょう。これまでの終身雇用であれば、社員は必然的に「会社のために」働いてきたわけですが、終身雇用に基づかないジョブ型雇用よりの働き方では、「個人の能力を会社に活かす」という発想になるはずです。こうなるともちろん、社員を束ねてマネジメントする専門家が必要となります。
また、日本型雇用の特徴の一つである退職給付制度(一時金・年金)のある企業は、現状では80.5%です(平成30年調査)。詳しく企業規模別に見ると「1,000人以上」が92.3%、「300~999人」が91.8%、「100~299人」が84.9%、「30~99人」が77.6%となっており、大企業ほど手厚くなっています。また退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業の割合は9.3%、退職年金制度に関しては5.1%となっています。
終身雇用はまだ多くの支持があり、退職金の現状をみるところ、それほど大きな変革も起きていないようです。しかし、経営側としてはこのあたりにメスを入れる必要があるのでしょう。労働側の意識と企業経営の乖離をどのように解決していくのか、これからの課題といえるかもしれません。
終身雇用・年功序列はこれまでも少しずつ変化してきましたが、いま大きな転換点を迎えているのかもしれません。ここでは、雇用のあり方は今後どのように変化するのか、考えてみましょう。
終身雇用が限界である理由のひとつはグローバル化
終身雇用とは、日本独自のガラパゴス化した制度と言えるかもしれません。海外の企業は、国境を越えて有能な人材を高い報酬で迎え入れます。ここでの有能な人材とは、これが自分の強みだ、という専門性や武器を持っている人材です。もちろん、日本の企業も、国際的に戦うにはこういったグローバルに活躍する人材を採用しない手はありません。つまり、現代の企業が求めるのは、その分野におけるスペシャリストです。また、情報社会では旧来の技術先進国だけが技術や資金を独占するのではなく、場所を選ばず新たな事業を起こしたり、資金を集めたりすることが可能です。つまり、プレイヤーはどこからでも参戦できます。このスピード感で考えると、企業の内側に人材を抱え込んでいても、加速化する競争に対抗できないかもしれません。
また、これまで日本企業は全体を見通してバランスを取るジェネラリストを育成してきました。もちろん、企業において一定のジェネラリストは必要かもしれません。しかし、こういった人材を多く育てることは、現代では企業の利益とは合致しにくいと考えていいでしょう。つまり、大所帯で一斉に同じ目的に向けて動くシステムが機能しなくなってきているということではないでしょうか。それよりも、細かくさまざまな分野にアンテナを張り、すばやくアプローチすることによって技術を蓄えたり、商機を掴んだりする力のほうが今は必要なのかもしれません。
「終身雇用」から「ジョブ型雇用」へ
こうして、雇用はジョブ型という形に変化しつつあります。ジョブ型雇用とは専門スキルを生かして働く限定正社員もしくは有期契約労働者のことです。こういった労働形態の場合、契約内容以上の労働を行なう義務はないので、労働者にとっても雇用側にとっても合理的だと考えられます。こうなってくると、職場の価値やあり方、会社との関わり方も大きく変化する可能性があります。終身雇用では「会社がメインで個人はその従属的存在」でした。しかし、今後は「個人が中心となって会社は個人の生活の一場面」となるかもしれません。もちろんこの時、個人が所属する会社は一つとは限らないでしょう。これまでの終身雇用であれば、社員は必然的に「会社のために」働いてきたわけですが、終身雇用に基づかないジョブ型雇用よりの働き方では、「個人の能力を会社に活かす」という発想になるはずです。こうなるともちろん、社員を束ねてマネジメントする専門家が必要となります。
「終身雇用」は多くの人が望んでいる
こう考えると、たしかに「終身雇用」は限界なのかもしれません。しかし、だれもが競争社会の中で貪欲に生きたいと願っているわけではありません。たとえば、独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った「第7回勤労生活に関する調査」(2015年)によれば、「終身雇用」「年功賃金」を支持する人の割合は、87.9%となっています。この数値は調査を開始した1999年以降、過去最高であり、また全年齢層で87%から88%台と支持されています。また、日本型雇用の特徴の一つである退職給付制度(一時金・年金)のある企業は、現状では80.5%です(平成30年調査)。詳しく企業規模別に見ると「1,000人以上」が92.3%、「300~999人」が91.8%、「100~299人」が84.9%、「30~99人」が77.6%となっており、大企業ほど手厚くなっています。また退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業の割合は9.3%、退職年金制度に関しては5.1%となっています。
終身雇用はまだ多くの支持があり、退職金の現状をみるところ、それほど大きな変革も起きていないようです。しかし、経営側としてはこのあたりにメスを入れる必要があるのでしょう。労働側の意識と企業経営の乖離をどのように解決していくのか、これからの課題といえるかもしれません。
<参考サイト>
・「第7回勤労生活に関する調査」結果|独立行政法人 労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/press/documents/20160923.pdf
・平成 30 年就労条件総合調査の概況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/dl/gaikyou.pdf
・「第7回勤労生活に関する調査」結果|独立行政法人 労働政策研究・研修機構
https://www.jil.go.jp/press/documents/20160923.pdf
・平成 30 年就労条件総合調査の概況|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/dl/gaikyou.pdf
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







