テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
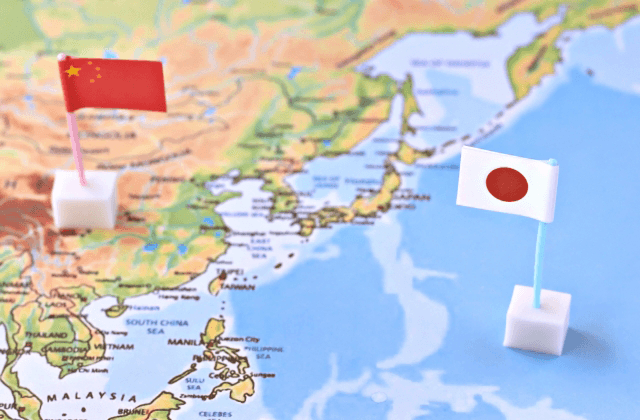
中国人が困った「日本のマナー」とは?
旅行や国際的なイベントのために来日する人も多いようです。また労働市場では、より高いスキルや国際的な業務経験を持つ人材を求めて、積極的に海外の人材を採用する場面も増えています。なかでも中国からの来日者数はかなり多いようです。こういった場面で話に挙がってくるのがマナーの違い。今回は、日本人にとってのマナーが中国の人たちにどのように受け取られているのか、少し見てみましょう。
具体的に、戸惑いのポイントはどういうところなのでしょうか。一つには日本での「お礼文化」に関してのものがあるようです。オズマピーアールの記事では同社で働く二人の中国人へのインタビューが掲載されています。これによると「中国人はおごってもらっても基本的にお礼は言わない」とのこと。日本では建前的なやり取りとして、お礼は必要と考える人が多いと思いますが、実際に日本でのこの習慣を中国でやってしまった時「せっかく食事をして距離が縮まったと思ったのにと怒られたことがある」そうです。中国での人間関係では「距離の近さ」が重要ということのようです。たしかに、日本人でもこの感覚の方が、気持ちが楽という人もいるかもしれません。ここはなかなか面白い感覚の違いです。
このあたりもかなり大きなギャップとなりそうです。インタビューによると、「面子を潰された」ということは、そのまま会社を辞める理由になるとのこと。それだけ中国人は自分があってこそ、という意識が強いと言えるでしょう。これに対して日本では、自分の主張はあっても、これを通そうと思ったら、自分の主張をどれだけ抑えながらうまく立ち振る舞うかということが大事になります。うまく立ち振る舞うことのうちには根回しが大事になってきたりするので、面倒ではあります。
同じものを見て、同じような経験をしてきた人間であれば、自ずと相手の思考や心情を察知できます。つまり、「空気を読む」ことも可能でしょう。このような強い同質性がこれまでの日本の特徴でした。しかしこの先の少子化社会では、旧来の日本の文化的背景を持って生まれ育つ人間の数は減少します。日本がいつまでもこの同質性を維持することに腐心していれば、外側からの理解を得ることはより難しくなります。それよりも、どうすればより他者に明確に自分の意思や意図を伝えられるか、という発想でその方法を磨くほうが、この先の社会では有効な能力になるのではないでしょうか。外国人のマナーを知ることは、その人たちが何を大事にしているのかを知ることです。これは他者とつながるための第一歩かも知れません。
お礼に対する違和感
国内や海外での総合的なPRを手掛ける株式会社オズマピーアールは在日中国人女性プラットフォーム「一般社団法人美ママ協会」の会員を対象に日本のマナーや習慣に関する調査を行っています。これによると、日本に住む中国人の6割が「初来日時に日本のマナーや習慣に戸惑った」と回答しているそうです。また、「初来日時に日本でのマナーや習慣について人に尋ねたことがあるか」という質問に対して、「あてはまる」「ややあてはまる」と回答した人は合わせて75.7%。同社の分析では、訪日中国人のマナーについて注目が集まる一方で、訪日する側の中国人自身も、日本でのマナーや習慣を気にしているとのこと。具体的に、戸惑いのポイントはどういうところなのでしょうか。一つには日本での「お礼文化」に関してのものがあるようです。オズマピーアールの記事では同社で働く二人の中国人へのインタビューが掲載されています。これによると「中国人はおごってもらっても基本的にお礼は言わない」とのこと。日本では建前的なやり取りとして、お礼は必要と考える人が多いと思いますが、実際に日本でのこの習慣を中国でやってしまった時「せっかく食事をして距離が縮まったと思ったのにと怒られたことがある」そうです。中国での人間関係では「距離の近さ」が重要ということのようです。たしかに、日本人でもこの感覚の方が、気持ちが楽という人もいるかもしれません。ここはなかなか面白い感覚の違いです。
人前で怒られることの違和感
名刺を渡す際などに自己紹介することがあると思います。日本では、まず組織があってそこに所属している一人です、という名乗り方をするでしょう。これに対して中国でのビジネスマンは、まず人が先に立つということのようです。中国では自分が会社に力を貸している、という考え方があるようです。また、中国人は面子を大事にするので、ミスをした社員をみんなの前で上司が叱ることはないとのこと。中国では同僚の目を避け、個室に呼び出して注意するそうです。このあたりもかなり大きなギャップとなりそうです。インタビューによると、「面子を潰された」ということは、そのまま会社を辞める理由になるとのこと。それだけ中国人は自分があってこそ、という意識が強いと言えるでしょう。これに対して日本では、自分の主張はあっても、これを通そうと思ったら、自分の主張をどれだけ抑えながらうまく立ち振る舞うかということが大事になります。うまく立ち振る舞うことのうちには根回しが大事になってきたりするので、面倒ではあります。
「空気を読む」は必要か
マナーとは、相手を不快にさせないための作法、と言ってもいいでしょう。ですが、こういった作法はその個人の所属している文化によって変化します。だからこそこういったマナーはズレがあって当然と言えます。日本人はよく「空気を読む」と言います。これは、さまざまな情報をまとめて状況を察し、配慮して言葉や振る舞いを選べ、ということかと思われます。日本でのマナーは、この「空気を読む」ことと強く関係しています。同じものを見て、同じような経験をしてきた人間であれば、自ずと相手の思考や心情を察知できます。つまり、「空気を読む」ことも可能でしょう。このような強い同質性がこれまでの日本の特徴でした。しかしこの先の少子化社会では、旧来の日本の文化的背景を持って生まれ育つ人間の数は減少します。日本がいつまでもこの同質性を維持することに腐心していれば、外側からの理解を得ることはより難しくなります。それよりも、どうすればより他者に明確に自分の意思や意図を伝えられるか、という発想でその方法を磨くほうが、この先の社会では有効な能力になるのではないでしょうか。外国人のマナーを知ることは、その人たちが何を大事にしているのかを知ることです。これは他者とつながるための第一歩かも知れません。
<参考サイト>
・【中国人が困る日本のマナーや習慣に関する調査】|OZMAPR
https://ozma.co.jp/globalcommunication/news-20190722/
・外国人が日本で働くために必要なスキルと手続ガイド|To Creator
https://www.dsp.co.jp/tocreator/all/career-all/foreign-workers/
・【中国人が困る日本のマナーや習慣に関する調査】|OZMAPR
https://ozma.co.jp/globalcommunication/news-20190722/
・外国人が日本で働くために必要なスキルと手続ガイド|To Creator
https://www.dsp.co.jp/tocreator/all/career-all/foreign-workers/
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










