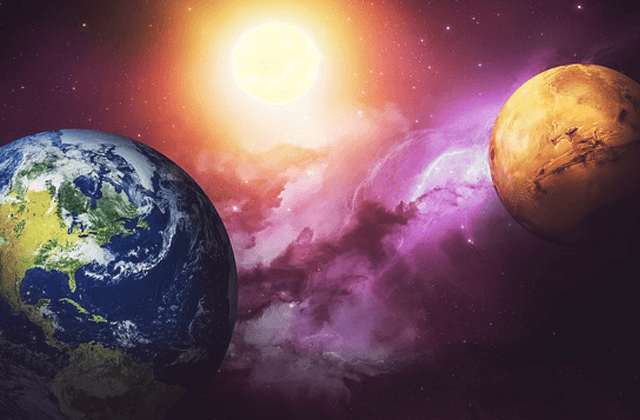
宇宙旅行が夢でない今だから知りたい宇宙の姿
民間主導の宇宙旅行もいよいよ秒読みとなってきた現在ですが、その費用はお一人さま25万米ドル(約2,700万円強)。資格は18歳以上で健康であれば年齢の上限はない、と宇宙旅行を企画するクラブツーリズムの広報は呼びかけています。
もしも宇宙旅行に参加できるとなったら、気になるのは何といっても安全性だと思いますが、その安全性を知るためには、宇宙船を動かすしくみがそもそもどうなっているかを知る必要があります。教養としての宇宙講義を集めたテンミニッツTV『宇宙の謎と宇宙探査の最新技術に迫る』特集から、かいつまんでご紹介いたします。
宇宙旅行に申し込む前に最初に頭に入れたいのは、地球の周りを飛ぶ人工衛星の仕組み。なぜ人工衛星が落ちないかというと、「宇宙にある物体は障害物さえなければ飛び続ける」のが、万物の真実だからです。さらに、その物体が外に飛び出そうとする遠心力と地球に向き合う引力がちょうど釣り合うと、ずっと地球のそばで回り続けます。このときの速さは秒速7.9キロメートル、新幹線の約100倍にもなります。
宇宙へ旅をしたいと思えば、秒速7.9キロメートルの壁を破る必要があります。そのときにロケットエンジンが大きな役割を果たします。二番目に頭に入れたいのは、ロケットエンジンが「飛んでいる物体の経路を変える」ことです。安定した状態だと地球を周回する軌道を描きますが、さらに加速することで、その軌道を楕円に変えることができるのです。
ただし、ここで問題なのは周囲に何もない宇宙空間において「加速=押す」行為が非常に難しいことです。そこで「ロケット推進」という方法が使われます。これは、自身の質量の一部を噴射し、その反作用で加速させることを言います。これが三つ目の、決定的に重要なことです。
現在企画されている宇宙旅行のような短期間の場合はこれでいいのですが、時間のかかる宇宙探査では、「はやぶさ」で有名になったイオンエンジン(電気推進)が有効です。燃料としてキセノンを用い、プラズマ生成→イオン加速→電子による中和の3段階を経て陽イオンを放出、極めて少ない燃料で長時間動作できる仕組みです。排気速度は通常の約10倍、いわば「省エネ型」ロケットエンジンと呼んでいいでしょう。
仮に火星で一定の探査を行おうとすると、まず秒速約7.9キロメートルで高度20キロメートルの人工衛星軌道に達します。それから速度変化を与えるのですが、このとき毎秒プラス2.9キロメートルの速度にすると火星のところまで届きます。
火星の方向に近づいた探査機は太陽の重力に引っ張られるため、地球の速度としては21.5キロメートル/秒の速度を持っています。ところが、火星は太陽の周りを毎秒24キロメートルで回っていますから、探査機が火星に着いたときには、探査機が火星を先行してこの場所に入り、それよりも速度が速い火星が探査機に追いついてくるような状態になります。
火星の周りを回る軌道に入るためにはタイミングを見計らって減速しなければなりません。有人の探査であれば、帰り道を考えないといけませんから、さらに火星の周回軌道から地球の周回軌道へ、そして着陸という二度の速度変化が必要になります。
2006年8月、プラハで開かれた国際天文学連合総会で、惑星の定義が議論され、あらたに採択された結果から、「冥王星は惑星ではない」ことが決まりました。
当時は、このことから「冥王星が惑星から降格された」、中には「冥王星はなくなった」というとんでもない話まで飛び出したといいます。実はそんなことでは全くなく、観測技術の進歩によって新しく見えてきた、「太陽系外縁天体」という新しい種族の中の一族である「冥王星型天体」の盟主として新たな地位を与えられたのだ、と岡村定矩氏(東京大学名誉教授)は言います。
これを受けて、新しい太陽系のイメージはどうなったでしょうか。これまでは太陽を中心として、ほぼ同心円状に水星、金星、地球、火星、木星と惑星があり、火星と木星の軌道の間に非常にたくさんの小さな天体、小惑星。さらにその外に、土星、天王星、海王星、冥王星となっていました。
今では、海王星の外に1000個以上もの小天体が新たに見つかっています。これが「太陽系外縁天体」であり、その中には冥王星と同じぐらいの大きさのものもあります。これらは「冥王星型天体」として、エリス、マケマケ、ハウメアと名付けられました。
太陽系を離れて遠くへ行くと、10000天文単位(太陽~地球間の距離の1万倍)、すなわち1光年あたりまで遠ざかってようやく名前の付いた星が見えてきます。地球に一番近い恒星は「アルファ・ケンタウリ」ですが、太陽系の属する天の川銀河には1000億もの恒星が含まれるとされています。
ただし、ほとんどのブラックホールは恒星とひもづくことなく単独で浮遊しているため、眼には見えません。このような「見えない」ブラックホールを「野良ブラックホール」と名付け、その検出方法を研究しているのが岡朋治氏(慶應義塾大学理工学部物理学科教授)です。
岡氏の研究グループは「超新星残骸W44」と呼ばれる、太陽系から1万光年程度離れた天体に付随するガス雲を研究して、意外な結果を得ました。超新星残骸の膨張速度をはるかに上回る速度のガスが、非常に狭い領域に局在していたことで、考えられる可能性は二つあります。一つはそこで正体不明の爆発が起きたこと、二つ目は小さな重いものが高速で突っ切った可能性です。
岡氏は後者を推し、ブラックホールだと結論づけました。偶然に出会った事例から、ブラックホール自体は見えなくても、周りのガスの運動を観測することで間接的に検出する方法が示されたわけです。
2019年のノーベル物理学賞は系外惑星発見に宇宙論確立と、宇宙尽くしでした。近い将来、日本の研究者もきっと選ばれる日が来るのではないでしょうか。ぜひテンミニッツTVをご覧になって、宇宙への興味の扉を開いてみてください。
もしも宇宙旅行に参加できるとなったら、気になるのは何といっても安全性だと思いますが、その安全性を知るためには、宇宙船を動かすしくみがそもそもどうなっているかを知る必要があります。教養としての宇宙講義を集めたテンミニッツTV『宇宙の謎と宇宙探査の最新技術に迫る』特集から、かいつまんでご紹介いたします。
宇宙旅行に参加する前に頭に入れたい三つのこと
まずは宇宙推進工学を専門分野とする小泉宏之氏(東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授)の「宇宙探査の現在と可能性」と題するレクチャーをのぞいてみましょう。宇宙旅行に申し込む前に最初に頭に入れたいのは、地球の周りを飛ぶ人工衛星の仕組み。なぜ人工衛星が落ちないかというと、「宇宙にある物体は障害物さえなければ飛び続ける」のが、万物の真実だからです。さらに、その物体が外に飛び出そうとする遠心力と地球に向き合う引力がちょうど釣り合うと、ずっと地球のそばで回り続けます。このときの速さは秒速7.9キロメートル、新幹線の約100倍にもなります。
宇宙へ旅をしたいと思えば、秒速7.9キロメートルの壁を破る必要があります。そのときにロケットエンジンが大きな役割を果たします。二番目に頭に入れたいのは、ロケットエンジンが「飛んでいる物体の経路を変える」ことです。安定した状態だと地球を周回する軌道を描きますが、さらに加速することで、その軌道を楕円に変えることができるのです。
ただし、ここで問題なのは周囲に何もない宇宙空間において「加速=押す」行為が非常に難しいことです。そこで「ロケット推進」という方法が使われます。これは、自身の質量の一部を噴射し、その反作用で加速させることを言います。これが三つ目の、決定的に重要なことです。
火星への探査で大切にしたいのは?
今では、ロケット推進の力で移動する装置そのものをロケットと呼ぶことが多いため、「エンジンがロケット?」と混乱してしまう人もいるかもしれません。ロケットのエネルギー源には、化学ロケット、電気ロケット、原子力ロケットがあります。実用化されているロケットのほとんどは化学ロケットで、酸化剤と燃料を固めて固体燃料としています(内燃式)。現在企画されている宇宙旅行のような短期間の場合はこれでいいのですが、時間のかかる宇宙探査では、「はやぶさ」で有名になったイオンエンジン(電気推進)が有効です。燃料としてキセノンを用い、プラズマ生成→イオン加速→電子による中和の3段階を経て陽イオンを放出、極めて少ない燃料で長時間動作できる仕組みです。排気速度は通常の約10倍、いわば「省エネ型」ロケットエンジンと呼んでいいでしょう。
仮に火星で一定の探査を行おうとすると、まず秒速約7.9キロメートルで高度20キロメートルの人工衛星軌道に達します。それから速度変化を与えるのですが、このとき毎秒プラス2.9キロメートルの速度にすると火星のところまで届きます。
火星の方向に近づいた探査機は太陽の重力に引っ張られるため、地球の速度としては21.5キロメートル/秒の速度を持っています。ところが、火星は太陽の周りを毎秒24キロメートルで回っていますから、探査機が火星に着いたときには、探査機が火星を先行してこの場所に入り、それよりも速度が速い火星が探査機に追いついてくるような状態になります。
火星の周りを回る軌道に入るためにはタイミングを見計らって減速しなければなりません。有人の探査であれば、帰り道を考えないといけませんから、さらに火星の周回軌道から地球の周回軌道へ、そして着陸という二度の速度変化が必要になります。
冥王星が惑星から外れて、何が変わった?
宇宙旅行や火星探査も夢ではなくなった今、大事なのは私たちの住む太陽系とその外に広がる星の世界をシミュレーションすることかもしれません。2006年8月、プラハで開かれた国際天文学連合総会で、惑星の定義が議論され、あらたに採択された結果から、「冥王星は惑星ではない」ことが決まりました。
当時は、このことから「冥王星が惑星から降格された」、中には「冥王星はなくなった」というとんでもない話まで飛び出したといいます。実はそんなことでは全くなく、観測技術の進歩によって新しく見えてきた、「太陽系外縁天体」という新しい種族の中の一族である「冥王星型天体」の盟主として新たな地位を与えられたのだ、と岡村定矩氏(東京大学名誉教授)は言います。
これを受けて、新しい太陽系のイメージはどうなったでしょうか。これまでは太陽を中心として、ほぼ同心円状に水星、金星、地球、火星、木星と惑星があり、火星と木星の軌道の間に非常にたくさんの小さな天体、小惑星。さらにその外に、土星、天王星、海王星、冥王星となっていました。
今では、海王星の外に1000個以上もの小天体が新たに見つかっています。これが「太陽系外縁天体」であり、その中には冥王星と同じぐらいの大きさのものもあります。これらは「冥王星型天体」として、エリス、マケマケ、ハウメアと名付けられました。
太陽系を離れて遠くへ行くと、10000天文単位(太陽~地球間の距離の1万倍)、すなわち1光年あたりまで遠ざかってようやく名前の付いた星が見えてきます。地球に一番近い恒星は「アルファ・ケンタウリ」ですが、太陽系の属する天の川銀河には1000億もの恒星が含まれるとされています。
太陽系と星の世界をシミュレーションする
天の川銀河にあるのは恒星だけではありません。X線天文学の発展により、それまでは理論上の仮説だった「ブラックホール」の存在も確認されるようになりました。現在認識されているのは60個ほどですが、理論的には1億から10億という膨大な数のブラックホールが存在する可能性があります。ただし、ほとんどのブラックホールは恒星とひもづくことなく単独で浮遊しているため、眼には見えません。このような「見えない」ブラックホールを「野良ブラックホール」と名付け、その検出方法を研究しているのが岡朋治氏(慶應義塾大学理工学部物理学科教授)です。
岡氏の研究グループは「超新星残骸W44」と呼ばれる、太陽系から1万光年程度離れた天体に付随するガス雲を研究して、意外な結果を得ました。超新星残骸の膨張速度をはるかに上回る速度のガスが、非常に狭い領域に局在していたことで、考えられる可能性は二つあります。一つはそこで正体不明の爆発が起きたこと、二つ目は小さな重いものが高速で突っ切った可能性です。
岡氏は後者を推し、ブラックホールだと結論づけました。偶然に出会った事例から、ブラックホール自体は見えなくても、周りのガスの運動を観測することで間接的に検出する方法が示されたわけです。
2019年のノーベル物理学賞は系外惑星発見に宇宙論確立と、宇宙尽くしでした。近い将来、日本の研究者もきっと選ばれる日が来るのではないでしょうか。ぜひテンミニッツTVをご覧になって、宇宙への興味の扉を開いてみてください。
<参考サイト>
宇宙の謎と宇宙探査の最新技術に迫る│10MTV
https://10mtv.jp/pc/feature/detail.php?id=87
宇宙の謎と宇宙探査の最新技術に迫る│10MTV
https://10mtv.jp/pc/feature/detail.php?id=87
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







