テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
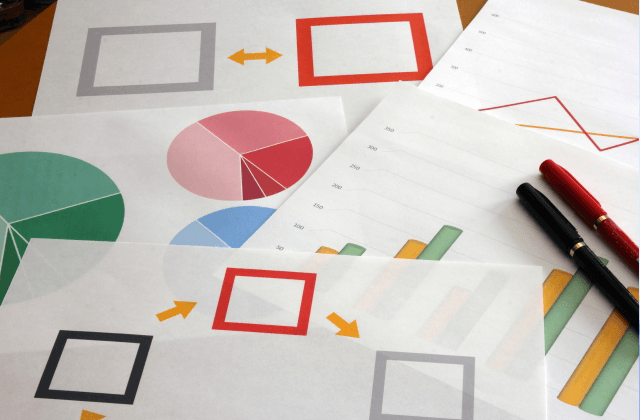
「わかりにくい資料」の特徴とは?
仕事に限らず何かをしようとするときには、説明・報告など情報共有しなければならない場面は多々あります。特に会議資料など、情報共有する場合もされる場合も、わかりやすさとわかりにくさといった視点から、その内容について考えさせられたことが少なからずあるのではないでしょうか?今回は、そんな、情報共有のための資料がテーマです。
では、わかりにくさとはドコにあるのでしょうか?
・投影スライドなのに、情報が詰め込みすぎ。しかもフォントが小さすぎて読めない。(公務員/男性28歳)
・専門的な用語や画数の多い漢字が多過ぎ。しかもムダなイラストやビジュアルを多用し、しかもスライド数が多い。煙に巻こうとしているのかマウントをとろうとしているのか、ポイントが大づかみできない過剰な構成。(教育/男性35歳)
・アニメーションなど、むだな演出が多過ぎで、内容が空疎。しかも、間違ったワーディングや誤字誤植も。(ゲーム/男性40歳)
・レイアウトは一見キレイでまとまっているんだけど、内容がないという...パワポなど、用意されたテンプレートに任せっきりで、自分で考えていない。(メーカー/女性32歳)
知人に取材したところ、こんなコメントをいただきました。
・誤った情報、誤字脱字が多い
・レイアウトがフラットでポイントがつかみにくい
・情報を詰め込みすぎて要領を得ていない
・専門用語や難しい言葉が多い
・ビジュアル素材やアニメーション演出などが過剰
問題は、内容と状況にみあった表現にあるようです。内容は個々の事案に属することですが、誰にどんな情報を届けようとしているのか、その明確さと簡潔さがポイントになります。わかりにくい資料とは、頭の中のイメージをそのまま表出した、独りよがりな資料ということができるのではないでしょうか。
表現については、視覚認知の研究成果を知っておくとよいでしょう。東洋経済ONLINEでも紹介されている、視覚認知のゲシュタルトの法則(Gestalt Principles of Visual Perception)です。
・近接:物理的に近くにあるものを同じグループに属するものとみなす
・類似:似た色、形状、サイズ、向きを持つものを同じグループとみなす
・囲み:一緒に囲まれているものを同じグループとみなす
・閉合:一部が欠けていても、頭の中にある全体の構造にあてはめて認識する
・連続性:明確に連続性がなくても、最も自然な形でそれを見出す
・接続:線などで物理的につなげられているものを同じグループの一部とみなす
図解やグラフなど資料の根幹をデザイン・レイアウトするときの指針となります。
また、スライド資料作成の場合は、以下のポイントをおさえるようにしましょう。
・スライド1頁にテーマを一つ →下位情報は、4~7に絞り込む
・情報に優先順位をつける →色や字体、大きさで強調
・難しい言葉/専門用語を要チェック、受け手の理解に合わせる
・色使いは3色ルール →紙色・地色+文字色+ポイント色の3色で構成
・字体はイメージに合わせてシンプルに2書体以下に
・会場の一番後ろの席からの視認性/可読性を確認
伝えたい内容と表現が独りよがりにならないように、情報を伝える対象者の理解を助けるための組み立てを意識するようにしましょう。
わかりにくい資料とは?
情報共有といえば、業務報告やプレゼンテーションなどで扱われる投影スライドや紙資料があります。わかりにくい報告やプレゼンテーションは、話し方もありますが、スライドや紙資料の作り方が大きく影響します。では、わかりにくさとはドコにあるのでしょうか?
・投影スライドなのに、情報が詰め込みすぎ。しかもフォントが小さすぎて読めない。(公務員/男性28歳)
・専門的な用語や画数の多い漢字が多過ぎ。しかもムダなイラストやビジュアルを多用し、しかもスライド数が多い。煙に巻こうとしているのかマウントをとろうとしているのか、ポイントが大づかみできない過剰な構成。(教育/男性35歳)
・アニメーションなど、むだな演出が多過ぎで、内容が空疎。しかも、間違ったワーディングや誤字誤植も。(ゲーム/男性40歳)
・レイアウトは一見キレイでまとまっているんだけど、内容がないという...パワポなど、用意されたテンプレートに任せっきりで、自分で考えていない。(メーカー/女性32歳)
知人に取材したところ、こんなコメントをいただきました。
わかりにくい資料の特徴は?
少し整理して、わかりにくい資料の特徴を探ってみると、・誤った情報、誤字脱字が多い
・レイアウトがフラットでポイントがつかみにくい
・情報を詰め込みすぎて要領を得ていない
・専門用語や難しい言葉が多い
・ビジュアル素材やアニメーション演出などが過剰
問題は、内容と状況にみあった表現にあるようです。内容は個々の事案に属することですが、誰にどんな情報を届けようとしているのか、その明確さと簡潔さがポイントになります。わかりにくい資料とは、頭の中のイメージをそのまま表出した、独りよがりな資料ということができるのではないでしょうか。
わかりやすい資料づくり
わかりやすい資料にするためには、共感性を高める工夫が必要です。表現については、視覚認知の研究成果を知っておくとよいでしょう。東洋経済ONLINEでも紹介されている、視覚認知のゲシュタルトの法則(Gestalt Principles of Visual Perception)です。
・近接:物理的に近くにあるものを同じグループに属するものとみなす
・類似:似た色、形状、サイズ、向きを持つものを同じグループとみなす
・囲み:一緒に囲まれているものを同じグループとみなす
・閉合:一部が欠けていても、頭の中にある全体の構造にあてはめて認識する
・連続性:明確に連続性がなくても、最も自然な形でそれを見出す
・接続:線などで物理的につなげられているものを同じグループの一部とみなす
図解やグラフなど資料の根幹をデザイン・レイアウトするときの指針となります。
また、スライド資料作成の場合は、以下のポイントをおさえるようにしましょう。
・スライド1頁にテーマを一つ →下位情報は、4~7に絞り込む
・情報に優先順位をつける →色や字体、大きさで強調
・難しい言葉/専門用語を要チェック、受け手の理解に合わせる
・色使いは3色ルール →紙色・地色+文字色+ポイント色の3色で構成
・字体はイメージに合わせてシンプルに2書体以下に
・会場の一番後ろの席からの視認性/可読性を確認
伝えたい内容と表現が独りよがりにならないように、情報を伝える対象者の理解を助けるための組み立てを意識するようにしましょう。
<参考サイト>
・東洋経済ONLINE:致命的に資料がわかりにくい人の6つの盲点
https://toyokeizai.net/articles/-/161569
・東洋経済ONLINE:パッとしない資料を作ってしまう人々の共通点
https://toyokeizai.net/articles/-/309204
・東洋経済ONLINE:致命的に資料がわかりにくい人の6つの盲点
https://toyokeizai.net/articles/-/161569
・東洋経済ONLINE:パッとしない資料を作ってしまう人々の共通点
https://toyokeizai.net/articles/-/309204
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










