テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
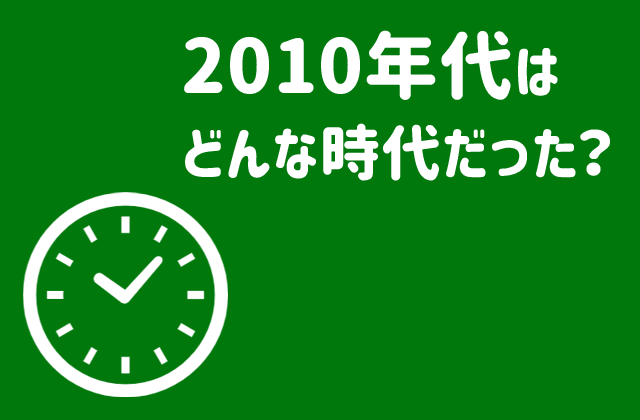
2010年代はどういう時代だったか振り返る
2010年代の日本とは、いったいどういう時代だったのでしょうか。今回は、記録や記憶に残る出来事や流行となった人物やフレーズなどを手がかりに、2010年代を振り返ってみたいと思います。
さらに尖閣諸島で中国漁船衝突事件が発生するなど、政治や経済での問題が浮き彫りとなった厳しい年でもありました。「新語・流行語大賞」では「~なう」のほかに「AKB48」「イクメン」「女子会」など、2020年代では一般用語化した言葉の多くも誕生したようです。
2011年の大事件といえば、なんといっても3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)です。広範囲にわたる津波や福島第一原子力発電所事故による被害も甚大で、帰宅難民や風評被害などの社会問題も発生しました。ただし、人々の連帯や助け合いなどの力も再確認された場面もあり、世相を反映する「今年の漢字」には「絆」が選ばれました。また、FIFA女子ワールドカップドイツ大会が開催され、「なでしこジャパン」が優勝し、社会現象ともなりました。地デジが開始されたのもこの年です。
東京スカイツリーが竣工された2012年。同年開催されたロンドンオリンピックでは、日本人選手の過去最多となる38個のメダルを獲得。ロンドンパラリンピックでも16個のメダルを獲得しました。また、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥氏が、日本人として25年ぶり史上2人目となるノーベル生理学・医学賞を受賞。「iPS細胞」がより広く人口に膾炙するようになりました。政治では野党第一党の自由民主党が、単独で絶対安定多数を確保する大勝を果たし、3年3カ月ぶりに政権を奪還。安倍晋三が内閣総理大臣に再就任し、第2次安倍内閣が発足しました。
林先生の「今でしょ!」、滝クリの「お・も・て・な・し」、あまちゃんの「じぇじぇじぇ」、半沢直樹の「倍返し」など、世相を彩る多様な流行が生まれた2013年。この年は政府が「アベノミクス」を政策として掲げて経済対策に乗り出す一方、特定秘密保護法案の成立が大きな政治課題となり、さらにはブラック企業やヘイトスピーチなど、社会問題も明るみになってきた年でもありました。また、富士山が世界文化遺産に登録されました。
消費税が5%から8%に増税された2014年。いわゆる「STAP細胞問題」の騒動が起こり、フジテレビ系昼の長寿番組『森田一義アワー 笑っていいとも!』が放送終了。「新語・流行語大賞」には「ダメよ~ダメダメ」と「集団的自衛権」が大賞に選ばれ、「カープ女子」や「こじらせ女子」といった「〇〇女子」や「理系女子(リケジョ)」や「土木系女子(ドボジョ)」といった言葉が流行り始めました。一方、アニメではニンテンドー3DSから派生した「妖怪ウォッチ」が大ヒット。同様にアニメ映画「アナと雪の女王」が大ヒットを記録し、主題歌の邦題「ありのままで」が流行語となるなど、社会現象化しました。超高層ビル「あべのハルカス」が開業したのもこの年です。
2016年は「マイナンバー制度」の運用開始に始まり、アイドルグループ・SMAPの解散で終わった一年となりました。他方、熊本では大地震が発生し、神奈川県相模原市では犠牲者19人と戦後最多の犠牲者数の殺人事件となる相模原障害者施設殺傷事件が発生するなど、人々を震撼させました。また、バラク・オバマ氏が現職アメリカ合衆国大統領として史上初、かつて同国により原子爆弾が投下された広島市を訪問する一方で、「トランプ現象」によって日本だけでなく世界中が巻き込まれることとなりました。そして、ピコ太郎氏の「PPAP」や「ポケモンGO」が社会現象となり、「ゲス不倫」がインパクトを残した一年でした。
森友学園問題・加計学園問題・日報隠蔽問題といった、数多の政治問題に焦点が当たった2017年。「新語・流行語大賞」にも、「忖度」「フェイクニュース」「Jアラート」といった、政治や経済にまつわる言葉がトップテン入りとなりました。また、座間9遺体事件が発覚したのも同年です。しかしながら、東洋大学の桐生祥秀氏が男子100メートル日本人初の9秒台である9.98秒を記録し、弱冠15歳の将棋棋士・藤井聡太氏が公式戦29連勝の新記録を樹立し、同じく将棋棋士の羽生善治氏が史上初の「永世七冠」を達成するなど、喜ばしい記録の達成に立ち会えた年でもありました。
2018年は、大阪府北部地震や北海道胆振東部地震や西日本を中心とした広範囲な被害を出した記録的な集中豪雨が発生、「災害級の暑さ」ともいわれるほどの猛暑ともなるなど、多くの人が自然災害をあらためて意識する年となりました(ただし、「スーパーボランティア」が「新語・流行語大賞」のトップテンに入りに)。他方、平昌オリンピックで活躍し銅メダルを獲得したカーリング女子の「そだねー」が話題となり、歌手の安室奈美恵氏が芸能界を引退し、「#MeToo運動」が世界的に盛り上がり、日本でも多くの当事者や賛同者が声を上げて動き始めたのもこの年です。
平成から令和への改元が行われた2019年。日本で開催されたラグビーワールドカップ2019では、初となる決勝トーナメントへの進出を果たし、日本中を「ONE TEAM」へと盛り上げてくれたラグビー日本代表チームが大きな話題となりました。その一方で、刃物を持った男が児童ら20人を襲った川崎市登戸通り魔事件、36人の死者を出した京都アニメーション放火殺人事件が発生し、人々を叫喚させました。また、働き方改革関連法の順次施行、消費税の10%に増税と食料品や新聞など一部の商品を8%に据え置く軽減税率の導入など、社会や経済システムの変換が行われた年にもなりました。
いかがでしたでしょうか。夢中になった出来事、すでになつかしいフレーズ、今では大切になっている思い出などありましたでしょうか。こうして流行のトピックスとともに駆け足で振り返ってみると、2010年代とは、システムの変革が萌芽した年代であったように思えます。地球規模の自然環境、世界単位でのネットワーク環境、そしてそれらの状況に応じた人々の意識にすら、変革の萌芽が宿された時代であったように見えてきます。
2010年代前半を振り返る
記録的な猛暑に見舞われた2010年。夏の猛暑日の連続で全国的に熱中症にかかる人が続出し、「今年の漢字」にも「暑」が選ばれました。またこの年は、中国にGDPを抜かれて日本は世界第3位に転落し、さらに尖閣諸島で中国漁船衝突事件が発生するなど、政治や経済での問題が浮き彫りとなった厳しい年でもありました。「新語・流行語大賞」では「~なう」のほかに「AKB48」「イクメン」「女子会」など、2020年代では一般用語化した言葉の多くも誕生したようです。
2011年の大事件といえば、なんといっても3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)です。広範囲にわたる津波や福島第一原子力発電所事故による被害も甚大で、帰宅難民や風評被害などの社会問題も発生しました。ただし、人々の連帯や助け合いなどの力も再確認された場面もあり、世相を反映する「今年の漢字」には「絆」が選ばれました。また、FIFA女子ワールドカップドイツ大会が開催され、「なでしこジャパン」が優勝し、社会現象ともなりました。地デジが開始されたのもこの年です。
東京スカイツリーが竣工された2012年。同年開催されたロンドンオリンピックでは、日本人選手の過去最多となる38個のメダルを獲得。ロンドンパラリンピックでも16個のメダルを獲得しました。また、京都大学iPS細胞研究所所長の山中伸弥氏が、日本人として25年ぶり史上2人目となるノーベル生理学・医学賞を受賞。「iPS細胞」がより広く人口に膾炙するようになりました。政治では野党第一党の自由民主党が、単独で絶対安定多数を確保する大勝を果たし、3年3カ月ぶりに政権を奪還。安倍晋三が内閣総理大臣に再就任し、第2次安倍内閣が発足しました。
林先生の「今でしょ!」、滝クリの「お・も・て・な・し」、あまちゃんの「じぇじぇじぇ」、半沢直樹の「倍返し」など、世相を彩る多様な流行が生まれた2013年。この年は政府が「アベノミクス」を政策として掲げて経済対策に乗り出す一方、特定秘密保護法案の成立が大きな政治課題となり、さらにはブラック企業やヘイトスピーチなど、社会問題も明るみになってきた年でもありました。また、富士山が世界文化遺産に登録されました。
消費税が5%から8%に増税された2014年。いわゆる「STAP細胞問題」の騒動が起こり、フジテレビ系昼の長寿番組『森田一義アワー 笑っていいとも!』が放送終了。「新語・流行語大賞」には「ダメよ~ダメダメ」と「集団的自衛権」が大賞に選ばれ、「カープ女子」や「こじらせ女子」といった「〇〇女子」や「理系女子(リケジョ)」や「土木系女子(ドボジョ)」といった言葉が流行り始めました。一方、アニメではニンテンドー3DSから派生した「妖怪ウォッチ」が大ヒット。同様にアニメ映画「アナと雪の女王」が大ヒットを記録し、主題歌の邦題「ありのままで」が流行語となるなど、社会現象化しました。超高層ビル「あべのハルカス」が開業したのもこの年です。
2010年代後半を振り返る
2015年は、ラグビーワールドカップ2015が開催されました。日本が南アフリカに歴史的勝利を収め、ラグビー日本代表の五郎丸歩氏が話題となりました。経済政策では安倍内閣が「一億総活躍社会」を掲げて呼びかける一方で、政治では安全保障関連法案が成立に関心が高まり、「アベ政治を許さない」とした社会的な動きが起こり、関東・東北で豪雨などの自然災害が発生するなど、多くの人々が「安」に揺らぎを感じる年ともなりました。なお、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」がユネスコ世界遺産(文化遺産)に登録されました。2016年は「マイナンバー制度」の運用開始に始まり、アイドルグループ・SMAPの解散で終わった一年となりました。他方、熊本では大地震が発生し、神奈川県相模原市では犠牲者19人と戦後最多の犠牲者数の殺人事件となる相模原障害者施設殺傷事件が発生するなど、人々を震撼させました。また、バラク・オバマ氏が現職アメリカ合衆国大統領として史上初、かつて同国により原子爆弾が投下された広島市を訪問する一方で、「トランプ現象」によって日本だけでなく世界中が巻き込まれることとなりました。そして、ピコ太郎氏の「PPAP」や「ポケモンGO」が社会現象となり、「ゲス不倫」がインパクトを残した一年でした。
森友学園問題・加計学園問題・日報隠蔽問題といった、数多の政治問題に焦点が当たった2017年。「新語・流行語大賞」にも、「忖度」「フェイクニュース」「Jアラート」といった、政治や経済にまつわる言葉がトップテン入りとなりました。また、座間9遺体事件が発覚したのも同年です。しかしながら、東洋大学の桐生祥秀氏が男子100メートル日本人初の9秒台である9.98秒を記録し、弱冠15歳の将棋棋士・藤井聡太氏が公式戦29連勝の新記録を樹立し、同じく将棋棋士の羽生善治氏が史上初の「永世七冠」を達成するなど、喜ばしい記録の達成に立ち会えた年でもありました。
2018年は、大阪府北部地震や北海道胆振東部地震や西日本を中心とした広範囲な被害を出した記録的な集中豪雨が発生、「災害級の暑さ」ともいわれるほどの猛暑ともなるなど、多くの人が自然災害をあらためて意識する年となりました(ただし、「スーパーボランティア」が「新語・流行語大賞」のトップテンに入りに)。他方、平昌オリンピックで活躍し銅メダルを獲得したカーリング女子の「そだねー」が話題となり、歌手の安室奈美恵氏が芸能界を引退し、「#MeToo運動」が世界的に盛り上がり、日本でも多くの当事者や賛同者が声を上げて動き始めたのもこの年です。
平成から令和への改元が行われた2019年。日本で開催されたラグビーワールドカップ2019では、初となる決勝トーナメントへの進出を果たし、日本中を「ONE TEAM」へと盛り上げてくれたラグビー日本代表チームが大きな話題となりました。その一方で、刃物を持った男が児童ら20人を襲った川崎市登戸通り魔事件、36人の死者を出した京都アニメーション放火殺人事件が発生し、人々を叫喚させました。また、働き方改革関連法の順次施行、消費税の10%に増税と食料品や新聞など一部の商品を8%に据え置く軽減税率の導入など、社会や経済システムの変換が行われた年にもなりました。
いかがでしたでしょうか。夢中になった出来事、すでになつかしいフレーズ、今では大切になっている思い出などありましたでしょうか。こうして流行のトピックスとともに駆け足で振り返ってみると、2010年代とは、システムの変革が萌芽した年代であったように思えます。地球規模の自然環境、世界単位でのネットワーク環境、そしてそれらの状況に応じた人々の意識にすら、変革の萌芽が宿された時代であったように見えてきます。
<参考文献・参考サイト>
・2010年代の日本 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC
・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞
https://www.jiyu.co.jp/singo/
・「新語・流行語大賞全記録」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「今年の漢字」一覧 | 事業・活動情報 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
・2010年代の日本 - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/2010%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E3%81%AE%E6%97%A5%E6%9C%AC
・「現代用語の基礎知識」選 ユーキャン 新語・流行語大賞
https://www.jiyu.co.jp/singo/
・「新語・流行語大賞全記録」『現代用語の基礎知識 2019』(自由国民社)
・「今年の漢字」一覧 | 事業・活動情報 | 公益財団法人 日本漢字能力検定協会
https://www.kanken.or.jp/project/edification/years_kanji/history.html
人気の講義ランキングTOP20










