テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
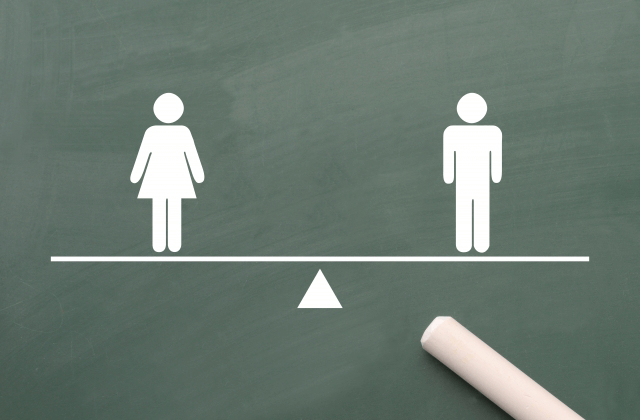
現代で配慮すべき「性別表現」ガイドライン
男女共同参画社会基本法が公布され早20年が経とうとしています。昭和の頃に比べれば一般的な男女観は変わってきており、女性の社会進出や男性の家事育児も普通のこととして浸透しつつあります。とはいえ、今日でもなお古い価値観に基づいたCMが炎上し、こんな時代錯誤な宣伝が未だに作られるのかと絶句させられることも少なくありません。
現代はまさに新旧の価値観が混ざり合う過渡期、公共機関や企業はそれに対応した新しい広報のガイドラインを提示しています。今回はそれらガイドラインにどのようなことが書かれているのかを紹介します。
各自治体のガイドラインでは、広報に使われるイラストや写真へも配慮を促しています。たとえば《夕飯前の家族の様子》を描いたイラスト画では、
<従来→新>
《ご飯を作っているお母さん》→《テーブルの上を片付けているお母さん》
《お手伝いをする女の子》→《お手伝いをする》
《パソコンで作業中のお父さん》→《ご飯を作っているお父さん》
《遊んでいる男の子》→《お手伝いをする》
というように、男女共に家事をするイメージが掲げられています。また、職場での会議や講演会の様子を描いたイラストなどにありがちな、《中心的な男性》《従属的な女性》という構図や、防犯ポスターなどでしばしば目にする《被害者=女性/加害者=男性》という役回りも、性別で固定せず均等にするよう推奨されています。
他にも「火の用心! 火事に気をつけよう!」と訴えるポスターに火事とも消防署とも関係ない女性の写真やイラストを載せるなど、アイキャッチャーとして女性を使う広告も見直しが呼びかけられているようです。
職業にまつわる名称で性別にとらわれることのないよう変わったものとして真っ先に思い浮かぶのは「看護婦」が「看護師」になったことでしょう。2001年に「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」という名称に変わったことにより、翌年から男女共に「看護師」に統一されました。他にも「スチュワーデス」が「客室乗務員(キャビン・アテンダント)」になったように、様々な職業名が改められてきています。
・「営業マン」→「営業社員」
・「サラリーマン/OL」→「会社員」
・「女子アナ」→「アナウンサー」
・「カメラマン」→「フォトグラファー/写真家」
・「女流作家」→「作家」
・「女社長」→「経営者」
一部例外として「女優」や「巫女」などはそのままで良いそうですが、職業を不必要に《マン=男性》に限定しない、性別を強調したり特別視したりしないことに基準があるようです。
とはいえ、大河ドラマ『女城主 井伊直虎』のタイトルが『城主 井伊直虎』になってしまうと、戦国時代という過酷な時代を城主として強く生き抜いた女性がいたというアピールが効かなくなってしまいます。ただの言葉狩りにならないよう、パブリックとエンターテイメントなど場面によっての使い分けが求められるところです。
……しかし、そうなると名前で呼べるほど親しくない人のパートナーについて質問するときは困ってしまいますね。「奥さん/旦那さんはお元気にされていますか?」というような質問をしたいときに「パートナーはお元気にされていますか?」だといまひとつ座りが悪い気がします。いずれ新しい言葉が出てくるかもしれません。
他にも結婚を表す言葉では、
・「嫁をもらう/やる/嫁ぐ」→「結婚する」
・「入籍」→「婚姻届を出す」
・「婿/嫁」→「娘の夫/息子の妻」
・「姑/舅」→「妻or夫の母/妻or夫の父」
など、何気なく口にしている名称にもメスが入れられていました。世代によっては馴染むのに時間がかかりそうですね。
このように、日常における言葉遣いのレベルからも男女平等意識の変革が行われるよう、ガイドラインでは制定されています。しかし、何よりも望まれているのは《名》だけでなく《実》がともなう男女平等社会の実現であることに相違ありません。男女のいずれの性別であることも、人生設計の妨げにならない時代の到来が待ち望まれます。
現代はまさに新旧の価値観が混ざり合う過渡期、公共機関や企業はそれに対応した新しい広報のガイドラインを提示しています。今回はそれらガイドラインにどのようなことが書かれているのかを紹介します。
性別による役割分担イメージを刷新
かつてCMで使われた「私作る人、僕食べる人」というフレーズをご存知の方も多いのではないでしょうか。婦人団体から性別役割分担の固定化につながると抗議を受けた結果、約2ヶ月で放送中止になりました。現代の広報では、従来の男女の役割分担的イメージへの配慮、刷新がひとつのキーになっているといっても過言ではありません。各自治体のガイドラインでは、広報に使われるイラストや写真へも配慮を促しています。たとえば《夕飯前の家族の様子》を描いたイラスト画では、
<従来→新>
《ご飯を作っているお母さん》→《テーブルの上を片付けているお母さん》
《お手伝いをする女の子》→《お手伝いをする》
《パソコンで作業中のお父さん》→《ご飯を作っているお父さん》
《遊んでいる男の子》→《お手伝いをする》
というように、男女共に家事をするイメージが掲げられています。また、職場での会議や講演会の様子を描いたイラストなどにありがちな、《中心的な男性》《従属的な女性》という構図や、防犯ポスターなどでしばしば目にする《被害者=女性/加害者=男性》という役回りも、性別で固定せず均等にするよう推奨されています。
他にも「火の用心! 火事に気をつけよう!」と訴えるポスターに火事とも消防署とも関係ない女性の写真やイラストを載せるなど、アイキャッチャーとして女性を使う広告も見直しが呼びかけられているようです。
言葉のガイドライン《職業編》
ガイドラインには私たちに身近な《言葉》や《名称》の改正も提示されています。職業にまつわる名称で性別にとらわれることのないよう変わったものとして真っ先に思い浮かぶのは「看護婦」が「看護師」になったことでしょう。2001年に「保健婦助産婦看護婦法」が「保健師助産師看護師法」という名称に変わったことにより、翌年から男女共に「看護師」に統一されました。他にも「スチュワーデス」が「客室乗務員(キャビン・アテンダント)」になったように、様々な職業名が改められてきています。
・「営業マン」→「営業社員」
・「サラリーマン/OL」→「会社員」
・「女子アナ」→「アナウンサー」
・「カメラマン」→「フォトグラファー/写真家」
・「女流作家」→「作家」
・「女社長」→「経営者」
一部例外として「女優」や「巫女」などはそのままで良いそうですが、職業を不必要に《マン=男性》に限定しない、性別を強調したり特別視したりしないことに基準があるようです。
とはいえ、大河ドラマ『女城主 井伊直虎』のタイトルが『城主 井伊直虎』になってしまうと、戦国時代という過酷な時代を城主として強く生き抜いた女性がいたというアピールが効かなくなってしまいます。ただの言葉狩りにならないよう、パブリックとエンターテイメントなど場面によっての使い分けが求められるところです。
言葉のガイドライン《日常編》
家父長制や家制度に基づいた表現の見直しも図られています。「奥さん」「家内」「旦那さん」「主人」「亭主」という言葉は男性を主としてとらえ、女性は家の中にいるものという旧来のイメージを抱かせるものとして、今では「妻/夫」「つれあい」「パートナー」などに改められています。……しかし、そうなると名前で呼べるほど親しくない人のパートナーについて質問するときは困ってしまいますね。「奥さん/旦那さんはお元気にされていますか?」というような質問をしたいときに「パートナーはお元気にされていますか?」だといまひとつ座りが悪い気がします。いずれ新しい言葉が出てくるかもしれません。
他にも結婚を表す言葉では、
・「嫁をもらう/やる/嫁ぐ」→「結婚する」
・「入籍」→「婚姻届を出す」
・「婿/嫁」→「娘の夫/息子の妻」
・「姑/舅」→「妻or夫の母/妻or夫の父」
など、何気なく口にしている名称にもメスが入れられていました。世代によっては馴染むのに時間がかかりそうですね。
このように、日常における言葉遣いのレベルからも男女平等意識の変革が行われるよう、ガイドラインでは制定されています。しかし、何よりも望まれているのは《名》だけでなく《実》がともなう男女平等社会の実現であることに相違ありません。男女のいずれの性別であることも、人生設計の妨げにならない時代の到来が待ち望まれます。
<参考サイト>
・『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』宇都宮市
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf
・『男女の表現についていっしょに考えてみませんか』宝塚市
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/s/_res/projects/default_project/_page_/001/000/450/guideline.pdf
・『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』宇都宮市
https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf
・『男女の表現についていっしょに考えてみませんか』宝塚市
http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/s/_res/projects/default_project/_page_/001/000/450/guideline.pdf
人気の講義ランキングTOP20










