テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
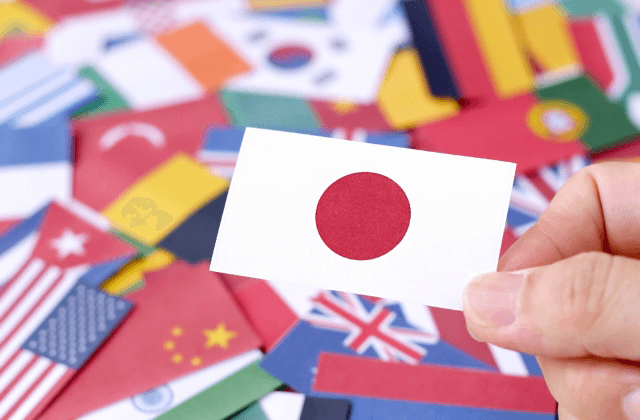
日本だけ?海外に無い日本の文化とは
海外を旅行して現地の文化に触れて帰国したあと、そうではなくて海外から来日された方と話しているときなど、「これって日本だけ?」と、海外に無い日本の文化を感じたことはありますか?
今回は、海外に無い日本の文化について、「挨拶」「仕草」そして「感覚」の側面から、考察してみたいと思います。
「いただきます」は、食事の前の挨拶言葉です。漢字で書くと「戴きます」となり、「戴」には「いただく」「おしいただく」「あがめる」「うける」といった、最上級の謙譲や感謝が込められています。「いただきます」感謝の対象は、食材そのものや育ててくれた人や存在、さらには眼前の食事を用意してくれた人など、広範囲におよびます。そのため、キリスト教文化圏などの食前の神への感謝の祈りとは、本質的に異なっています。
・おつかれさま
「おつかれさま」は、相手をねぎらう際に用いる挨拶言葉です。「ごくろうさま」は目上の人から目下の人に使うのに対し、「おつかれさま」は同僚や目上の人に対しても使うことができます。状況として「疲れている」人に掛ける言葉としてではなく、時間帯や状況に左右されにくい和を尊ぶ日本文化を象徴するような有能なクッション言葉として、特にビジネスシーンをはじめとした場面で多用されています。
・つまらないものですが
「つまらないものですが」は、物を差し上げる際に添える挨拶言葉です。謙遜・謙譲を尊ぶともいわれる日本文化の言語化の、代表的な言葉ともいえます。しかしながら、本当につまらない物を贈るわけではありません。たとえどんなに贈り物が素晴らしかったとしても、「あなたを思う私の気持ちや感謝の心」もしくは「あなたが私にしてくださった行為や思ってくださるお心」などに比べればつまらないというような、あくまでも上位概念的な比較級でしか表せない気持ちを言葉にしています。
手の人差し指と中指とを開いてV字形を作る「ピースサイン」または「Vサイン」と呼ばれるハンドサインは、日本では写真撮影の際に多用される定番ポーズですが、海外でも定番とういうわけではありません。欧米では、写真撮影時に「ピース」をしている大人は、「子どもっぽい」と感じられるそうです。
・“ちょっと失礼”を表す「手刀」
手指を伸ばしてそろえ刀のように見立てる「手刀」は、相撲などで今日的にも用いられていることもあり、日本では感謝の意や恐縮の委を表する礼儀的な仕草として浸透しています。そこから派生したのか、人前を横切る際などに日本では差し出した右手で手刀を切る動作で“ちょっと失礼”を表現しますが、欧米など海外ではこのような動作に該当する動作がないことあって、通じません。
・指や腕をクロスさせた「バツ」
指・手・腕などを×に交差させることが、「不可」「No」「ダメ」といった否定を表すジェスチャーと捉えられるのも、日本固有の習慣といわれています。その他にも、仕草やハンドサインには、個人の意思や願望だけでなく固有の文化に由来する場合が多々あります。文化として尊重することも大切ですが、同時に、異文化を尊重する思いやりの心も必要です。
環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏が、世界共通語にと提唱した「もったいない(MOTTAINAI)」は、日本の文化に深く根ざした感覚です。資源が少なく閉鎖的である反面、手先が器用で万物に心情すらも込めることができる日本的感覚において、あらゆる物質に感謝を込めて粗末にしないといった「もったいない」精神が育まれたのかもしれません。
・「木漏れ日」を愛でる
樹木の枝葉のすきまから射す日の光である「木漏れ日」は、翻訳できない日本語の一つといわれています。自然を征服する存在としてではなく、畏怖しながらも日々移り変わる変化を尊び愛で楽しんできた日本的感覚には、豊かな自然観の発露ともいえる言葉も多数存在します。
・「もののあわれ」
「あわれ」は、深く感動した時に思わず「ああ」と声を発する感覚に由来しているといわれています。そして、「あわれ」をさらに進めた「もののあわれ」は、対象客観を示す「もの」と感動主観を示す「あわれ」との一致するところに生じる、調和のとれた優美繊細な情趣の世界を理念化した日本的感覚の極地ともいえる感覚です。
「物より心」の旨を前述しましたが、とはいえ、物質的な物を「ものおもい」や「モノづくり」といった概念にまで昇華させているところに、海外に無い日本の文化の特徴があるように感じられます。
いかがでしたでしょうか。その他にも、生活や食事のマナー、年中行事やお祭り、生活様式など、海外に無い日本の文化は多々あります。グローバルと同時にローカルの意味や特徴から学ぶことは、学ぶ人の生活を豊かにしてくれるはずです。興味を持たれた方は、ぜひ学んでみてください。
今回は、海外に無い日本の文化について、「挨拶」「仕草」そして「感覚」の側面から、考察してみたいと思います。
日本的挨拶
・いただきます「いただきます」は、食事の前の挨拶言葉です。漢字で書くと「戴きます」となり、「戴」には「いただく」「おしいただく」「あがめる」「うける」といった、最上級の謙譲や感謝が込められています。「いただきます」感謝の対象は、食材そのものや育ててくれた人や存在、さらには眼前の食事を用意してくれた人など、広範囲におよびます。そのため、キリスト教文化圏などの食前の神への感謝の祈りとは、本質的に異なっています。
・おつかれさま
「おつかれさま」は、相手をねぎらう際に用いる挨拶言葉です。「ごくろうさま」は目上の人から目下の人に使うのに対し、「おつかれさま」は同僚や目上の人に対しても使うことができます。状況として「疲れている」人に掛ける言葉としてではなく、時間帯や状況に左右されにくい和を尊ぶ日本文化を象徴するような有能なクッション言葉として、特にビジネスシーンをはじめとした場面で多用されています。
・つまらないものですが
「つまらないものですが」は、物を差し上げる際に添える挨拶言葉です。謙遜・謙譲を尊ぶともいわれる日本文化の言語化の、代表的な言葉ともいえます。しかしながら、本当につまらない物を贈るわけではありません。たとえどんなに贈り物が素晴らしかったとしても、「あなたを思う私の気持ちや感謝の心」もしくは「あなたが私にしてくださった行為や思ってくださるお心」などに比べればつまらないというような、あくまでも上位概念的な比較級でしか表せない気持ちを言葉にしています。
日本的仕草
・写真撮影時の「ピース」手の人差し指と中指とを開いてV字形を作る「ピースサイン」または「Vサイン」と呼ばれるハンドサインは、日本では写真撮影の際に多用される定番ポーズですが、海外でも定番とういうわけではありません。欧米では、写真撮影時に「ピース」をしている大人は、「子どもっぽい」と感じられるそうです。
・“ちょっと失礼”を表す「手刀」
手指を伸ばしてそろえ刀のように見立てる「手刀」は、相撲などで今日的にも用いられていることもあり、日本では感謝の意や恐縮の委を表する礼儀的な仕草として浸透しています。そこから派生したのか、人前を横切る際などに日本では差し出した右手で手刀を切る動作で“ちょっと失礼”を表現しますが、欧米など海外ではこのような動作に該当する動作がないことあって、通じません。
・指や腕をクロスさせた「バツ」
指・手・腕などを×に交差させることが、「不可」「No」「ダメ」といった否定を表すジェスチャーと捉えられるのも、日本固有の習慣といわれています。その他にも、仕草やハンドサインには、個人の意思や願望だけでなく固有の文化に由来する場合が多々あります。文化として尊重することも大切ですが、同時に、異文化を尊重する思いやりの心も必要です。
日本的感覚
・「もったいない」精神環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マータイ氏が、世界共通語にと提唱した「もったいない(MOTTAINAI)」は、日本の文化に深く根ざした感覚です。資源が少なく閉鎖的である反面、手先が器用で万物に心情すらも込めることができる日本的感覚において、あらゆる物質に感謝を込めて粗末にしないといった「もったいない」精神が育まれたのかもしれません。
・「木漏れ日」を愛でる
樹木の枝葉のすきまから射す日の光である「木漏れ日」は、翻訳できない日本語の一つといわれています。自然を征服する存在としてではなく、畏怖しながらも日々移り変わる変化を尊び愛で楽しんできた日本的感覚には、豊かな自然観の発露ともいえる言葉も多数存在します。
・「もののあわれ」
「あわれ」は、深く感動した時に思わず「ああ」と声を発する感覚に由来しているといわれています。そして、「あわれ」をさらに進めた「もののあわれ」は、対象客観を示す「もの」と感動主観を示す「あわれ」との一致するところに生じる、調和のとれた優美繊細な情趣の世界を理念化した日本的感覚の極地ともいえる感覚です。
「物より心」の旨を前述しましたが、とはいえ、物質的な物を「ものおもい」や「モノづくり」といった概念にまで昇華させているところに、海外に無い日本の文化の特徴があるように感じられます。
いかがでしたでしょうか。その他にも、生活や食事のマナー、年中行事やお祭り、生活様式など、海外に無い日本の文化は多々あります。グローバルと同時にローカルの意味や特徴から学ぶことは、学ぶ人の生活を豊かにしてくれるはずです。興味を持たれた方は、ぜひ学んでみてください。
<参考文献>
・「戴」『字通』(白川静著、平凡社)
・『日本の常識は世界の非常識』(ミッシェル・エンゲルバート/マドレーヌ・グラデュ著、オーエス出版)
・「もったいない(MOTTAINAI)」『イミダス2018』(集英社)
・『翻訳できない世界のことば』(エラ・フランシス・サンダース、マドレーヌ・グラデュ著/イラスト、前田まゆみ訳、創元社)
・「もののあはれ」『日本大百科全書』(武田元治著、小学館)
・「戴」『字通』(白川静著、平凡社)
・『日本の常識は世界の非常識』(ミッシェル・エンゲルバート/マドレーヌ・グラデュ著、オーエス出版)
・「もったいない(MOTTAINAI)」『イミダス2018』(集英社)
・『翻訳できない世界のことば』(エラ・フランシス・サンダース、マドレーヌ・グラデュ著/イラスト、前田まゆみ訳、創元社)
・「もののあはれ」『日本大百科全書』(武田元治著、小学館)
人気の講義ランキングTOP20










