テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
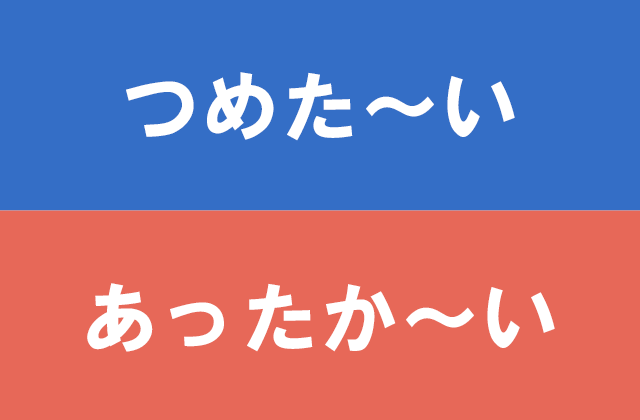
なぜ自販機の表記に「~」が入るのか?
暗い夜道で自販機を見つけるとほっとします。寒い時期には暖かい飲み物を、暑い時には冷たい飲み物をいつでも準備してくれているのは、ほんとにありがたいもの。こうした自販機の表示をよく見ると、「あたたか~い」「つめた~い」といったように「~」が入っている表示をよく目にします。「~」はなぜつけられるようになったのでしょうか。
この表記は飲料メーカーが決め、自販機メーカーが実際に作っているものだそうです。また、ガイドラインでは基本的には「あたたかい/つめたい」もしくは「あったか~い/つめた~い」の2種類が想定されているとのことです。また色に関しても、「温かい飲み物は「赤字に白抜き」、冷たい飲み物は「青地に白抜き」が基本となっている」とのこと。ただし、いずれも強制力はないそうです。
たしかに、「あたたかい/つめたい」でも情報としては十分ですが、「あったか~い」「つめた~い」といった表記の方が、なんだか人肌感があるというか、機械的ではなく和む感じがします。最近はほとんどの場合、「あったか~い」「つめた~い」となっており、「~」がないものはかなり古いものとのこと。ただ外国人観光客などにもわかりやすい表記を求めるとすれば、「HOT/COLD」といった表記も必要かもしれません。
これはアサヒ飲料が「冷えた飲み物を飲みたくない」という需要に応じようと始めたものです。2016年当初は300台でしたが、2019年には全国で1万3000台が稼働しているとのこと。主に、オフィスや病院、スポーツ施設などといった常温のニーズが見込まれるロケーションを中心に今後も展開するとのことです。健康管理に対する意識の高まりに応じた、あたらしい試みと言えるでしょう。
たしかに、冷たい飲み物ばかりを摂取するとお腹を壊すことがあります。冷たい飲み物は確かにのどごしはいいのですが、体に負担がかかることも確かです。また、エアコンが効いているオフィスや体が冷えやすい女性など常温で飲みたいと思うのも当然です。また、冷たい飲み物をカバンの中に入れて、水滴で中が濡れてしまうのが嫌」という意見もあるようです。こういった需要をとらえて、コンビニなどでも「常温」のドリンクを置くところも増えているようです。
多くの自販機が「あったか~い」「つめた~い」を採用
自販機の表記は「あったか~い」「つめた~い」以外にも、シンプルに「あったかい」「つめたい」と表記されているものもあるそうです。ちなみに筆者の近所の自販機は、ほぼ全て「あったか~い」「つめた~い」といった「~」入りの表記でした。この表記は飲料メーカーが決め、自販機メーカーが実際に作っているものだそうです。また、ガイドラインでは基本的には「あたたかい/つめたい」もしくは「あったか~い/つめた~い」の2種類が想定されているとのことです。また色に関しても、「温かい飲み物は「赤字に白抜き」、冷たい飲み物は「青地に白抜き」が基本となっている」とのこと。ただし、いずれも強制力はないそうです。
たしかに、「あたたかい/つめたい」でも情報としては十分ですが、「あったか~い」「つめた~い」といった表記の方が、なんだか人肌感があるというか、機械的ではなく和む感じがします。最近はほとんどの場合、「あったか~い」「つめた~い」となっており、「~」がないものはかなり古いものとのこと。ただ外国人観光客などにもわかりやすい表記を求めるとすれば、「HOT/COLD」といった表記も必要かもしれません。
最近は「常温」の自販機も増えている
ながらく自販機はこの「あったか~い」と「つめた~い」が季節に合わせて切り替わるものでしたが、最近はこのどちらでもないものも出てきているようです。それが「常温」。日本自動販売システム機会工業会によると、自販機で「あったか~い」と表示されているものの温度は約55度程度。また、「つめた~い」と表示されているものは約5度です。これらに対して「常温」は約20度。これはアサヒ飲料が「冷えた飲み物を飲みたくない」という需要に応じようと始めたものです。2016年当初は300台でしたが、2019年には全国で1万3000台が稼働しているとのこと。主に、オフィスや病院、スポーツ施設などといった常温のニーズが見込まれるロケーションを中心に今後も展開するとのことです。健康管理に対する意識の高まりに応じた、あたらしい試みと言えるでしょう。
たしかに、冷たい飲み物ばかりを摂取するとお腹を壊すことがあります。冷たい飲み物は確かにのどごしはいいのですが、体に負担がかかることも確かです。また、エアコンが効いているオフィスや体が冷えやすい女性など常温で飲みたいと思うのも当然です。また、冷たい飲み物をカバンの中に入れて、水滴で中が濡れてしまうのが嫌」という意見もあるようです。こういった需要をとらえて、コンビニなどでも「常温」のドリンクを置くところも増えているようです。
<参考サイト>
・「あったか~い」「つめた~い」じゃない!アサヒ飲料、常温自販機を年内300台へ│日刊工業新聞社(2016.5.18)
https://newswitch.jp/p/4700
・「あたたかい」でも「つめたい」でもない、「常温」の自販機が増えている理由 | オトナンサー
https://otonanswer.jp/post/35858/
・夏でもホットを飲む女性は6割以上! 冷たすぎない「常温自販機」も登場|レタスクラブ
https://www.lettuceclub.net/news/article/115519/
・なぜ自販機には「つめたい」と「つめた~い」が混在?「炎」や「氷」マークで表示の例も | ラジトピ ラジオ関西トピックス
https://jocr.jp/raditopi/2020/10/21/162334/
・よくあるご質問|日本自動販売システム機会工業会
https://www.jvma.or.jp/information/information_5.html
・「あったか~い」「つめた~い」じゃない!アサヒ飲料、常温自販機を年内300台へ│日刊工業新聞社(2016.5.18)
https://newswitch.jp/p/4700
・「あたたかい」でも「つめたい」でもない、「常温」の自販機が増えている理由 | オトナンサー
https://otonanswer.jp/post/35858/
・夏でもホットを飲む女性は6割以上! 冷たすぎない「常温自販機」も登場|レタスクラブ
https://www.lettuceclub.net/news/article/115519/
・なぜ自販機には「つめたい」と「つめた~い」が混在?「炎」や「氷」マークで表示の例も | ラジトピ ラジオ関西トピックス
https://jocr.jp/raditopi/2020/10/21/162334/
・よくあるご質問|日本自動販売システム機会工業会
https://www.jvma.or.jp/information/information_5.html
人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部
昭和陸軍の派閥抗争には三つの要因があった
中西輝政










