テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
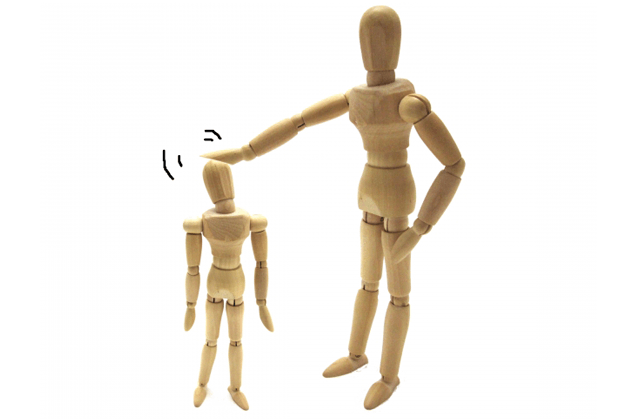
育ちが良い人が「しないこと」とは
育ちがいいなと感じる人、いますよね
会話をしているときなどにふと、相手に対して「この人、育ちがいいな」と感じること、ありますよね。「育ちがいい」という言葉の意味は、「育ち」=「成長、生育の背景や過程」が「いい」=「きちんとした環境できちんとした教育を受けたり、教養を得たりしている」ことを指します。確かに、育ちがいいと感じる人は、知的な雰囲気をまとっていますよね。しかしそれだけでなく、優しくて温かい人柄であるところも魅力です。育ちがいい人というと、裕福な家庭の出身と思われやすいですが、単にお金をかけた高度な教育を受けただけの人には、他人を見下して馬鹿にした態度を取る人もいます。そんな人は育ちがいいとはいえませんよね。つまり、育ちがいい人がお金持ちであることは絶対に必要な条件ではありません。それよりも、「人として大切なこと」=「気配りや道徳心」を持っている人といえるでしょう。
そんな人だからこそ、「しないこと」があるのはご存知でしょうか。それは育ちがいい人自身にしてみれば、しないようにわざわざ気をつけているわけではなく、気配りや道徳心から自然と避けていることなのです。
育ちがいい人がしないこととは?
それでは具体的に、育ちがいい人ならしないことを見てみましょう。他人を否定する:発言を頭ごなしに否定されたら、誰でも気分が悪いですよね。育ちがいい人は、はじめから他人を否定しません。「考えが違う」と感じたら、一度相手の言葉を受け止めてから自分の意見を言います。
乱暴な言葉遣いをする:下品な言葉そのものも、下品な言葉で他人の陰口や店員への文句を言う行動も、周囲の雰囲気を悪くしますよね。育ちがいい人はそんなことはせず、他人を気遣った品のある言葉で話します。
粗野な行動をする:育ちがいい人は、大きな音を立ててものを置いたり、公共の場で大騒ぎをしたりなど、他人がびっくりして眉をひそめるようなことはしません。どんな場所でも丁寧な所作で穏やかに行動します。
無駄遣いする:育ちがいい人は、衝動買いのようなお金の無駄遣いも、夜更かしや遅刻などの時間の無駄遣いもしません。その結果、余裕が生まれるので、節約に苦しんだり時間に追い立てられたりもしないのです。
見苦しい食べ方をする:お箸の使い方や食事の様子が汚い人といっしょにいると苦痛ですよね。育ちがいい人は食器をきれいに使って静かに食べます。また、姿勢を正して食べるので食事する姿がきれいに見えます。
当たり前のことかもしれませんが、全部きちんと実行できるかというと難しく感じることでもありますよね。
育ちがいい人の思考回路
育ちがいい人は、なぜこのような行動をしないのでしょうか。一番の理由は、「他人の立場になってものを考えるから」といえるでしょう。他人を否定しないのも、乱暴な言葉遣いをしないのも、他人が見たり聞いたりしたときに不快な思いをさせないよう気を配っているからです。そして、そのような教育を家庭で受けてきたからこそ、他人への思いやりは〝当たり前〟として身についているのです。無駄遣いをしないというのは、自分のためのように感じられますが、これも「他人の時間を無駄遣いしない」=「遅刻をしない」という考え方になり、最終的には他人を思いやる行動につながります。自分を律した生き方は、他人に好意を持たれる行動にも現れるのですね。
育ちがいい人がしないことを実践するのは難しいと感じてしまうなら、それは心の奥底に自己中心的なところがあるからです。周囲から「育ちがいい人だな」と思われて一目置かれるには、他人を思いやる気持ちを忘れないようにしましょう。
もちろん誰にでも、自分を優先して自分を甘やかさなければつらくなってしまうときはあるもの。無理はせず自分にできる気配りからはじめていけば、自然と周囲からの好感度も上がっていくはずですよ。
<参考サイト>
・OTONA SALONE 育ちのいい人が「しないこと」って?意外にシンプルな6つ
https://otonasalone.jp/272375/
・Oggi それって褒め言葉?「育ちがいい」の意味や、当てはまる人の特徴について解説
https://oggi.jp/6626223
・OTONA SALONE 育ちのいい人が「しないこと」って?意外にシンプルな6つ
https://otonasalone.jp/272375/
・Oggi それって褒め言葉?「育ちがいい」の意味や、当てはまる人の特徴について解説
https://oggi.jp/6626223
人気の講義ランキングTOP20
実は生物の「進化」とは「物事が良くなる」ことではない
長谷川眞理子










