テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
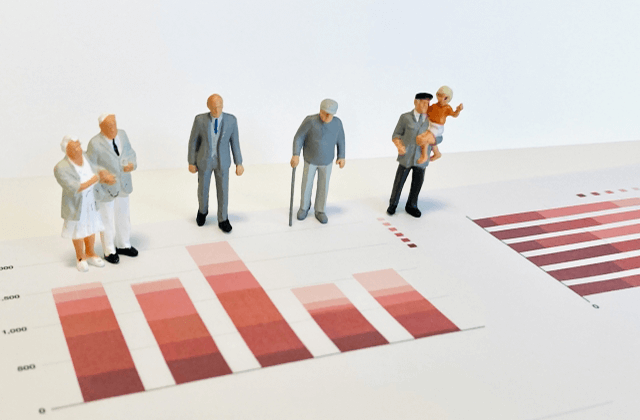
65歳以上が多い業種と平均年収は?
高齢化世界一と名高い日本ですが、総人口は1億2471万人、うち65歳以上が3627万人と29.1%を占めています。
世界的に比較すると、日本(29.1%)は世界200の国・地域中で最も高く、次いでイタリア(24.1%)、フィンランド(23.3%)、プエルトリコ(22.9%)などとなっています。
日本の高齢者人口を詳しくみると、女性が男性より479万人多く、女性2053万人(女性人口の32.0%)、男性1574万人(男性人口の26.0%)を数えます。70歳以上人口は2872万人(総人口の23.0%)で、前年に比べ39万人増。75歳以上人口は1937万人(同15.5%)で、前年に比べ72万人増。80歳以上人口は1235万人(同9.9%)で、前年に比べ41万人増です。
75歳以上人口が総人口の15%以上を占めるのは、初めてのこと。いわゆる「団塊の世代」(1947年~1949年生まれ)が2022年から75歳を迎え始めたことによると考えられています。ちなみに「2025年問題」とは、この世代の引退に伴う後継者不足による企業の危機を指しています。
政府は2025年に65歳定年を義務づけ、さらに70歳までを努力目標と掲げていますが、実際の就業率は60~64歳で71.5%、65~69歳で50.3%、70~74歳で32.6%に上ります。
こちらも国際比較をしてみると、日本の高齢者の就業率が、主要国の中でも高い水準であることが分かります。2011年と2021年の就業率を見ると、韓国(29.1→34.9%)。日本(19.2→25.1%)、アメリカ(16.7→18.0%)、カナダ(11.0→12.9%)と軒並み上がっているなかでも日本は目立ちます。
日本を追って高齢化の進んでいるヨーロッパ諸国ではイギリス(8.4→10.3%)、ドイツ(4.6→7.4%)、イタリア(3.2→5.1%)、フランス(2.0→3.4%)と就業率の向上はゆるやか。このあたりは社会保障とも国民性とも連動してくることなので、働く高齢者とのんびり高齢者、どちらが幸福か単純には比較できません。
では、暮らし向きに不安があるのかというと、経済的な暮らし向きについて心配がない65歳以上の人が68.5%を占めています。2019年に「老後資金2,000万円」が問題になりましたが、世帯主が60代の世帯平均貯蓄は2,384万円、70歳以上でも2,259万円と、平均額ではうまくクリアしているようです。
ただし、65歳以上で生活保護を受給する人も当然存在します。2019年に生活保護を受給した65歳以上は105万人。これは全受給者205万人の半数以上となっており、65歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.93%を数えます。
また、働き方の実際を見ると、非正規雇用で働く人の割合は、男性の場合55~59歳で10.5%だったのが、60~64歳では45.3%、65~69歳では67.8%となります。女性の場合も55~59歳で59.1%、60~64歳で74.7%、65~69歳では83.9%と、非正規比率が高まるのが大きな特徴です。
非正規の職員・従業員についた主な理由は、男女とも「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最多(男性30.7%、女性38.0%)を占めていますが、「正規の職員・従業員の仕事がないから」男性10.6%、女性6.0%の声も無視できません。
主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が130万人と最も多く、次いで「農業、林業」が104万人、「サービス業(他に分類されないもの)」が103万人、「医療,福祉」が101万人などとなっています。しかし、割合をみると「農業、林業」が53.3%と最も高く、次いで「不動産業、物品賃貸業」が26.8%、「サービス業(他に分類されないもの)」が22.8%、「生活関連サービス業、娯楽業」が19.4%です。
サラリーマンの収入は、一般に55~59歳をピークに下がると言われています。2021年の調査では平均月収が30.7万円のところ、55~59歳で36.55万円に上昇し、60~64歳になると29.28万円(55~59歳の約80%)、70歳以上では24.33万円(同約66.6%)にまでダウンします。
では、50代後半と比べて比較的賃金が下がらない業種もあるのでしょうか。ベスト3とワースト3を割り出してみたところ、比較的賃金が下がらないのは「医療・福祉」30.64万円(55~59歳の約93%)、「教育・学習支援」45.16万円(同約92%)、「宿泊・飲食」24.66万円(同約86%)などでした。逆に低下幅が大きいのは「電気・ガス・熱供給・水道業」29.06万円(同約58%)、「複合サービス」23.35万円(同約65%)、「情報通信」34.37万円(同約68%)などの業種でした。
60~64歳で年収のピークを迎える医師や大学教授とまではいかなくても、自分の属する業種が今後どうなるのか、注目したいところです。
世界的に比較すると、日本(29.1%)は世界200の国・地域中で最も高く、次いでイタリア(24.1%)、フィンランド(23.3%)、プエルトリコ(22.9%)などとなっています。
日本の高齢者人口を詳しくみると、女性が男性より479万人多く、女性2053万人(女性人口の32.0%)、男性1574万人(男性人口の26.0%)を数えます。70歳以上人口は2872万人(総人口の23.0%)で、前年に比べ39万人増。75歳以上人口は1937万人(同15.5%)で、前年に比べ72万人増。80歳以上人口は1235万人(同9.9%)で、前年に比べ41万人増です。
75歳以上人口が総人口の15%以上を占めるのは、初めてのこと。いわゆる「団塊の世代」(1947年~1949年生まれ)が2022年から75歳を迎え始めたことによると考えられています。ちなみに「2025年問題」とは、この世代の引退に伴う後継者不足による企業の危機を指しています。
働く高齢者の比率と幸福度は連動する?
令和3(2021)年時点で、日本の労働力人口は6907万人。うち65~69歳が410万人、70歳以上は516万人と、労働力人口に占める65歳以上割合は13.4%で上昇を続けています。ちなみにほぼ40年前の1980年には4.9%、10年前の2011年ですら8.9%と記録されています。政府は2025年に65歳定年を義務づけ、さらに70歳までを努力目標と掲げていますが、実際の就業率は60~64歳で71.5%、65~69歳で50.3%、70~74歳で32.6%に上ります。
こちらも国際比較をしてみると、日本の高齢者の就業率が、主要国の中でも高い水準であることが分かります。2011年と2021年の就業率を見ると、韓国(29.1→34.9%)。日本(19.2→25.1%)、アメリカ(16.7→18.0%)、カナダ(11.0→12.9%)と軒並み上がっているなかでも日本は目立ちます。
日本を追って高齢化の進んでいるヨーロッパ諸国ではイギリス(8.4→10.3%)、ドイツ(4.6→7.4%)、イタリア(3.2→5.1%)、フランス(2.0→3.4%)と就業率の向上はゆるやか。このあたりは社会保障とも国民性とも連動してくることなので、働く高齢者とのんびり高齢者、どちらが幸福か単純には比較できません。
「老後資金2,000万円」と悠々自適は別問題?
「何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいか」の質問に対して、収入を伴う仕事についている60歳以上の層からの主流回答は「働けるうちはいつまでも」(36.7%)となり、87%の人が少なくとも70歳くらいまで、もしくはそれ以上働きたいと望んでいることが分かりました。では、暮らし向きに不安があるのかというと、経済的な暮らし向きについて心配がない65歳以上の人が68.5%を占めています。2019年に「老後資金2,000万円」が問題になりましたが、世帯主が60代の世帯平均貯蓄は2,384万円、70歳以上でも2,259万円と、平均額ではうまくクリアしているようです。
ただし、65歳以上で生活保護を受給する人も当然存在します。2019年に生活保護を受給した65歳以上は105万人。これは全受給者205万人の半数以上となっており、65歳以上人口に占める生活保護受給者の割合は2.93%を数えます。
また、働き方の実際を見ると、非正規雇用で働く人の割合は、男性の場合55~59歳で10.5%だったのが、60~64歳では45.3%、65~69歳では67.8%となります。女性の場合も55~59歳で59.1%、60~64歳で74.7%、65~69歳では83.9%と、非正規比率が高まるのが大きな特徴です。
非正規の職員・従業員についた主な理由は、男女とも「自分の都合のよい時間に働きたいから」が最多(男性30.7%、女性38.0%)を占めていますが、「正規の職員・従業員の仕事がないから」男性10.6%、女性6.0%の声も無視できません。
50代後半がピークのサラリーマン、60代でも増収が望める業種は?
65歳からの働き方について、業種別の事情を見ていきましょう。この項は「賃金構造基本統計調査」がベースなので、月収で記している点、ご注意ください。主な産業別にみると、「卸売業、小売業」が130万人と最も多く、次いで「農業、林業」が104万人、「サービス業(他に分類されないもの)」が103万人、「医療,福祉」が101万人などとなっています。しかし、割合をみると「農業、林業」が53.3%と最も高く、次いで「不動産業、物品賃貸業」が26.8%、「サービス業(他に分類されないもの)」が22.8%、「生活関連サービス業、娯楽業」が19.4%です。
サラリーマンの収入は、一般に55~59歳をピークに下がると言われています。2021年の調査では平均月収が30.7万円のところ、55~59歳で36.55万円に上昇し、60~64歳になると29.28万円(55~59歳の約80%)、70歳以上では24.33万円(同約66.6%)にまでダウンします。
では、50代後半と比べて比較的賃金が下がらない業種もあるのでしょうか。ベスト3とワースト3を割り出してみたところ、比較的賃金が下がらないのは「医療・福祉」30.64万円(55~59歳の約93%)、「教育・学習支援」45.16万円(同約92%)、「宿泊・飲食」24.66万円(同約86%)などでした。逆に低下幅が大きいのは「電気・ガス・熱供給・水道業」29.06万円(同約58%)、「複合サービス」23.35万円(同約65%)、「情報通信」34.37万円(同約68%)などの業種でした。
60~64歳で年収のピークを迎える医師や大学教授とまではいかなくても、自分の属する業種が今後どうなるのか、注目したいところです。
<参考サイト> ・総務省:統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1320.html
・厚生労働省:賃金構造基本統計調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou_a.html
・令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html
https://www.stat.go.jp/data/topics/topi1320.html
・厚生労働省:賃金構造基本統計調査
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou_a.html
・令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2021/index.html
人気の講義ランキングTOP20










