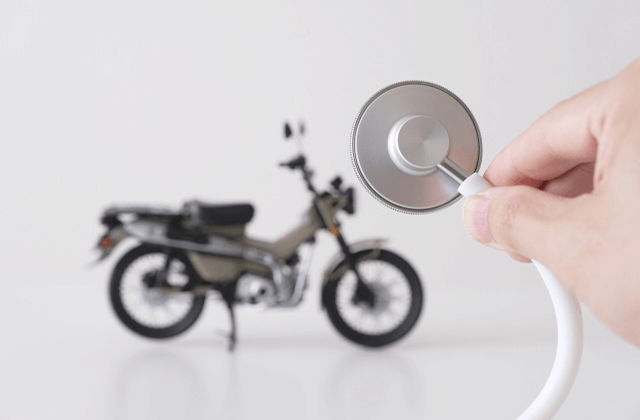
バイクの寿命を縮める4つのNG行為
バイクは長く乗れば乗るほど愛着がわき、手放したくないという声もよく聞かれます。できる限り長く乗りたいものですが、ではどういった点がバイクの寿命を縮めるのでしょうか。またバイクの寿命は一般的にはどれくらいが目安で、寿命を伸ばすにはどういった点に気を付ければよいのでしょうか。
また、あまり乗らずに放置することも問題となります。たとえばチェーンが錆びたり、タイヤが劣化したり、バッテリーが自然放電したりすることが考えられます。また、エンジン内に結露した水分がオイルと混ざり、オイルが劣化することもあるようです。これらは日ごろから適度に動かしていれば防げる問題です。また保管するときに野ざらしにしていれば、もちろんこういった問題はより大きくなります。
さらにもう一つポイントがあるとすれば、無理なメンテナンスをしている場合も考えられます。バイクは自分でいじる楽しみもある乗り物ですが、素人には難しい繊細な部分も多いです。専門的な知識や技術がないままにいじったことで、結果的に寿命を縮めることになる場合もあるようです。つまりバイクの寿命を縮める要素は、まずは「急のつく運転」です。これに加えて「メンテナンスの怠り」「適切でない保管方法」「適切でないメンテナンス」といった点が大きなポイントとして挙げることができそうです。
こういった事態を防ぐためには、法定点検を定期的に受けることです。法定点検には12か月点検と24か月点検がありますが、行わなかった場合の罰則は特にありません。250CCを超える中型、大型バイクであれば2年に1度車検を受ける義務があるので、特に問題が起きやすいのはこの義務がない250CC以下のバイクです。また中型大型のバイクであっても12か月で点検を受けることで、何か問題があった時に早めに対処することが可能になります。
ということで、バイクの寿命の伸ばすために必要なことは、まずは「急のつく運転をしない」こと。あとはこれに加えて「12か月の法定点検を受ける」、「長く放置せず定期的に乗る」、「可能な限り屋内駐車場で保管する」といったポイントかと思われます。ちなみにエンジンオイル交換の目安は3000キロから5000キロくらい、エンジンオイルフィルターの交換はエンジンオイル交換2回につき1回の頻度とのこと。エンジンオイルはエンジンを正常に保つには欠かせないものです。日ごろから意識的にチェックしましょう。
パーツが劣化するポイント
バイクに長く乗るためにNGとされる行為の一つが「急」のつく操作です。例えばエンジン始動後にアクセル全開で急加速する、急ブレーキするといった行為は確実にバイクの寿命を縮めます。こういった行為はバイクに大きな負担をかけ、消耗部品の寿命を縮めると同時に燃費の悪化につながります。こうして消耗品が劣化したまま走ると、ほかのパーツに負担がかかりさらに寿命を縮める原因となります。また、あまり乗らずに放置することも問題となります。たとえばチェーンが錆びたり、タイヤが劣化したり、バッテリーが自然放電したりすることが考えられます。また、エンジン内に結露した水分がオイルと混ざり、オイルが劣化することもあるようです。これらは日ごろから適度に動かしていれば防げる問題です。また保管するときに野ざらしにしていれば、もちろんこういった問題はより大きくなります。
さらにもう一つポイントがあるとすれば、無理なメンテナンスをしている場合も考えられます。バイクは自分でいじる楽しみもある乗り物ですが、素人には難しい繊細な部分も多いです。専門的な知識や技術がないままにいじったことで、結果的に寿命を縮めることになる場合もあるようです。つまりバイクの寿命を縮める要素は、まずは「急のつく運転」です。これに加えて「メンテナンスの怠り」「適切でない保管方法」「適切でないメンテナンス」といった点が大きなポイントとして挙げることができそうです。
バイクの寿命は一般的に10万キロが目安
一般的にはバイクの寿命も車同様10万キロとされる場合が多いようです。ちなみに原付はエンジンへの負担が大きく、2万から3万キロが目安とされるようです。一般的なバイクでは10万キロを超えると特にエンジンにやや問題が出てくることが多いようです。たとえば、エンジンがかかりにくくなる、燃費が悪くなる、異音がするといった状態が起こりやすくなったら要注意。またエンジン以外でもレギュレーターやクラッチといった部分でも修理や交換の必要が出てくることも多いようです。こういった事態を防ぐためには、法定点検を定期的に受けることです。法定点検には12か月点検と24か月点検がありますが、行わなかった場合の罰則は特にありません。250CCを超える中型、大型バイクであれば2年に1度車検を受ける義務があるので、特に問題が起きやすいのはこの義務がない250CC以下のバイクです。また中型大型のバイクであっても12か月で点検を受けることで、何か問題があった時に早めに対処することが可能になります。
ということで、バイクの寿命の伸ばすために必要なことは、まずは「急のつく運転をしない」こと。あとはこれに加えて「12か月の法定点検を受ける」、「長く放置せず定期的に乗る」、「可能な限り屋内駐車場で保管する」といったポイントかと思われます。ちなみにエンジンオイル交換の目安は3000キロから5000キロくらい、エンジンオイルフィルターの交換はエンジンオイル交換2回につき1回の頻度とのこと。エンジンオイルはエンジンを正常に保つには欠かせないものです。日ごろから意識的にチェックしましょう。
<参考サイト>
バイクの寿命を延ばすには点検・メンテナンスを徹底して故障を減らすのが鉄則!|バイクパーキング アイドゥ
https://www.yes-i-do.co.jp/column08.html
バイクはメンテナンス次第で10万キロ走れる!メンテナンス方法を解説|グーバイク
https://www.goobike.com/magazine/maintenance/maintenance/537/
クルマの場合は10万キロと言われているけど…バイクの走行距離の目安ってどれくらい?|バイクのニュース
https://bike-news.jp/post/276646
バイクの車検費用について徹底解説|バイクパーキング アイドゥ
https://www.yes-i-do.co.jp/column20.html
バイクの寿命を延ばすには点検・メンテナンスを徹底して故障を減らすのが鉄則!|バイクパーキング アイドゥ
https://www.yes-i-do.co.jp/column08.html
バイクはメンテナンス次第で10万キロ走れる!メンテナンス方法を解説|グーバイク
https://www.goobike.com/magazine/maintenance/maintenance/537/
クルマの場合は10万キロと言われているけど…バイクの走行距離の目安ってどれくらい?|バイクのニュース
https://bike-news.jp/post/276646
バイクの車検費用について徹底解説|バイクパーキング アイドゥ
https://www.yes-i-do.co.jp/column20.html
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部







