テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
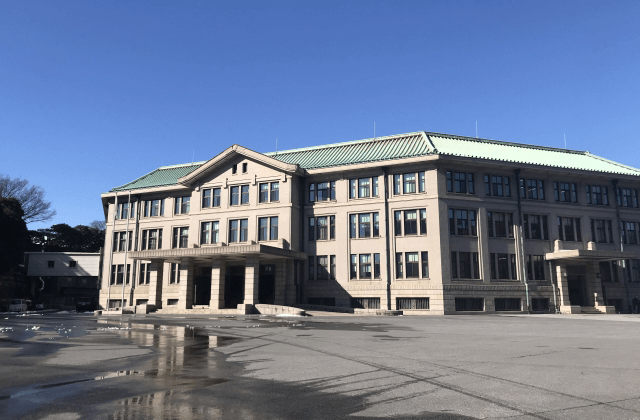
「宮内庁御用達」制度は今どうなっているの?
伝統工芸の逸品や老舗の銘品や銘菓などの話題が出た際に、「宮内庁御用達」や「皇室御用達」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
「御用達」とは、主に江戸時代に宮中・幕府・諸大名へ用品を納めることを認可された「御用商人」が由来とされています。要するに、「宮内庁御用達」制度とは、宮内庁への出入りを許可する商工業者を決める制度を意味します。
「宮内省御用達」となるためには、(1)2年以上同じ営業に従事していること、(2)博覧会などの場で優れた商品であると認められたこと、(3)(1)(2)の経歴が事実であることを公的機関の文書によって証明すること――の3条件が求められました。そのうえで、宮内省への出入り認める名誉を与えられた業者には、「宮内省御用達」の称標が与えられました。
しかし、時代とともに御用達を店の宣伝に利用する業者が増えたため、昭和10(1935)年に制度を改めることとなります。新たな条件として、(4)5年以上宮内省に出入りした業者であること、(5)与えられる称標の有効期限を5年とすること、などが見直されました。さらに、広告などでむやみに称標を使用しないよう厳しい注意が添えられたといわれています。
そして、第二次世界大戦を経て宮内省は、昭和24(1949)年から宮内庁となります。ここで始めて、「宮内省御用達」制度は「宮内庁御用達」制度に変わりました。さらに、昭和29年に「宮内庁御用達」制度そのものが廃止となり、現在に至ります。
実は、「宮内庁御用達」制度が廃止となった具体的な理由は公表されていません。ただし、宮内庁の後ろに控える皇室の権威にあやかりたい業者からの売り込みが激しくなったからではないか、などといわれています。
そのため、日本広告審査機構は、現在では「宮内庁御用達」という文言の使用について、「歴史的事実として表示するような場合を除き使うことはできません」としています。
明治・大正・昭和において「宮内庁御用達」制度に採用された老舗の多くは、現在も伝統を受け継いだ逸品や銘品を作り続けています。そして、あえて「宮内庁御用達」を名乗らなくともその名に恥じない品質とブランド力を維持し、令和の今も消費者に愛され信頼されています。
「御用達」とは、主に江戸時代に宮中・幕府・諸大名へ用品を納めることを認可された「御用商人」が由来とされています。要するに、「宮内庁御用達」制度とは、宮内庁への出入りを許可する商工業者を決める制度を意味します。
「宮内庁御用達」制度の歴史
「宮内庁御用達」制度は、宮内庁の前身となる明治2(1869)年に誕生した宮内省による、「宮内省御用達」制度として、明治24(1891)年に始まりました。宮内省、つまりは皇室が優れた商工業者にお墨付きを与えることにより、日本の伝統文化や技術の水準を維持することや、生活の様式化により需要の高まった商品の技術を向上することなど、産業奨励政策の一環として始められたといわれています。「宮内省御用達」となるためには、(1)2年以上同じ営業に従事していること、(2)博覧会などの場で優れた商品であると認められたこと、(3)(1)(2)の経歴が事実であることを公的機関の文書によって証明すること――の3条件が求められました。そのうえで、宮内省への出入り認める名誉を与えられた業者には、「宮内省御用達」の称標が与えられました。
しかし、時代とともに御用達を店の宣伝に利用する業者が増えたため、昭和10(1935)年に制度を改めることとなります。新たな条件として、(4)5年以上宮内省に出入りした業者であること、(5)与えられる称標の有効期限を5年とすること、などが見直されました。さらに、広告などでむやみに称標を使用しないよう厳しい注意が添えられたといわれています。
そして、第二次世界大戦を経て宮内省は、昭和24(1949)年から宮内庁となります。ここで始めて、「宮内省御用達」制度は「宮内庁御用達」制度に変わりました。さらに、昭和29年に「宮内庁御用達」制度そのものが廃止となり、現在に至ります。
「宮内庁御用達」制度後の逸品や銘品
以上のように、現在、「宮内庁御用達」制度はすでにない過去の制度となっています。実は、「宮内庁御用達」制度が廃止となった具体的な理由は公表されていません。ただし、宮内庁の後ろに控える皇室の権威にあやかりたい業者からの売り込みが激しくなったからではないか、などといわれています。
そのため、日本広告審査機構は、現在では「宮内庁御用達」という文言の使用について、「歴史的事実として表示するような場合を除き使うことはできません」としています。
明治・大正・昭和において「宮内庁御用達」制度に採用された老舗の多くは、現在も伝統を受け継いだ逸品や銘品を作り続けています。そして、あえて「宮内庁御用達」を名乗らなくともその名に恥じない品質とブランド力を維持し、令和の今も消費者に愛され信頼されています。
<参考文献・参考サイト>
・『皇室御用達ものがたり』(日本文化再発見研究室、祥伝社)
・『皇室ゆかりの逸品《厳選47》』(鮫島敦監修、辰巳出版)
・商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないの? | 小売業
https://www.jaro.or.jp/shiryou/topic/kourigyou/062.html
・「御用達」の意味は?語源は?実は正式な制度ではなかった!?
https://dime.jp/genre/963642/
・『皇室御用達ものがたり』(日本文化再発見研究室、祥伝社)
・『皇室ゆかりの逸品《厳選47》』(鮫島敦監修、辰巳出版)
・商品などに「宮内庁御用達」と表示しても問題ないの? | 小売業
https://www.jaro.or.jp/shiryou/topic/kourigyou/062.html
・「御用達」の意味は?語源は?実は正式な制度ではなかった!?
https://dime.jp/genre/963642/
人気の講義ランキングTOP20
適者生存ではない…進化論とスペンサーの社会進化論は別物
長谷川眞理子










