テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
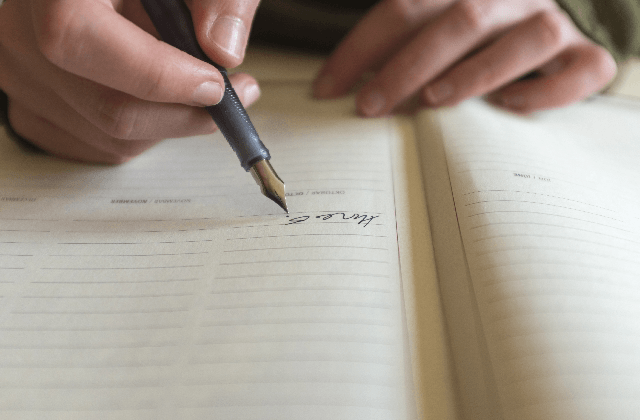
「頭がいい人は字が汚い」ってホント?
予備校講師としてテレビにもよく出演する林修先生は「東大合格者トップ層は字が汚く、2番手グループは字がきれい」だと言います。このことからすると、「頭がいいほど字が汚くなる」ということになるかもしれません。実際はどうなのでしょうか。
日本の国語教育では、漢字の学習としてバランスや「トメ・ハネ・ハライ」などを意識する授業にかなりの時間を割くようです。また、習い事で「書道教室」に通っていたという人も少なくないのではないでしょうか。つまり、日本では、「字をきれいに書く」ということは大切な教養として息づいていると言えるでしょう。
たしかにメモやノートを取るのはある程度、時間はかかります。なので、記録のための字を書く時間はなるべく減らしたいと考えていてもおかしくはないでしょう。つまり、効率よく物事を進めるには、字をきれいに書くということにこだわってはいられない、ということです。
また、スタッフの一人が、大学時代に履修した西洋美術史の先生のことを教えてくれました。その先生は東大を出た後にフランスの有名大学に留学して研究を積んだ、いわゆる「頭のいい」方でした。
スタッフによれば、その先生の授業は外国語が混じったり抽象的な言葉を使うことが多いため、一応板書して伝えようとはしてくれるのですが、その文字がいつもうねうねしていて、漢字なのか、カタカナなのか、はたまたアルファベットなのか、区別することが難しいくらいに難解な文字だったそうです。
これは、まさに頭のスピードに文字が追い付かない例です。先の林先生が言う、頭がいい人というのは、字を書くのは誰かに見せるためではなく、自分のためと割り切っているのかもしれません。ただ、「伝達」という文字の役割においては、少なくともある程度判読できる文字でなければつらいですよね。
ですが、ふとしたときに目にしたきれいな、あるいは丁寧な文字はやはり魅力的で、その人の背景に品の良さや真面目さといったものを感じるのではないでしょうか。こういう細やかさを感じることができる私たち日本人の感性は、大事にしていきたいですね。
教養としての美文字教育
最近ではPCの普及で、手書きの文字を見る機会も減ってきました。そんな中、ふと知人の手書き文字を見て、「この人、こんなにきれいな字を書くのか」と見直したり、逆に普段は礼儀正しい人の雑な文字を見て「意外だなぁ」などと思ったりした経験はありませんか。もしかしたら私たちは、無意識に「字はその人を表す」という感覚をもっているのかもしれません。日本の国語教育では、漢字の学習としてバランスや「トメ・ハネ・ハライ」などを意識する授業にかなりの時間を割くようです。また、習い事で「書道教室」に通っていたという人も少なくないのではないでしょうか。つまり、日本では、「字をきれいに書く」ということは大切な教養として息づいていると言えるでしょう。
頭の回転が早い人は字が汚い!?
ですが、海外ではやや事情が違うようです。ある記事によると、字の汚さと頭の良さについて、アメリカでは、日本人の留学生が美しい筆記体で提出したところ、受け取った先生はその字の美しさに驚いたあと、「エネルギーは内容にもっと使うべき」とばかりに、その場で再提出を通告したそうです。ちなみに、アメリカの学生たちはどれも殴り書きに近かったけれども、書くスピードはとにかく速かったということです。たしかにメモやノートを取るのはある程度、時間はかかります。なので、記録のための字を書く時間はなるべく減らしたいと考えていてもおかしくはないでしょう。つまり、効率よく物事を進めるには、字をきれいに書くということにこだわってはいられない、ということです。
また、スタッフの一人が、大学時代に履修した西洋美術史の先生のことを教えてくれました。その先生は東大を出た後にフランスの有名大学に留学して研究を積んだ、いわゆる「頭のいい」方でした。
スタッフによれば、その先生の授業は外国語が混じったり抽象的な言葉を使うことが多いため、一応板書して伝えようとはしてくれるのですが、その文字がいつもうねうねしていて、漢字なのか、カタカナなのか、はたまたアルファベットなのか、区別することが難しいくらいに難解な文字だったそうです。
これは、まさに頭のスピードに文字が追い付かない例です。先の林先生が言う、頭がいい人というのは、字を書くのは誰かに見せるためではなく、自分のためと割り切っているのかもしれません。ただ、「伝達」という文字の役割においては、少なくともある程度判読できる文字でなければつらいですよね。
日本人なら丁寧さも大事にしたい
たしかに、字に対して見た目や丁寧さを意識することと、学習スピードを上げることは両立しづらいでしょう。そう考えると、「頭がいいほど字が汚くなる」、つまり、頭がいい人ほど字がきれいとか汚いとか気にしなくなる(気にしない)、ということになるのかもしれません。ですが、ふとしたときに目にしたきれいな、あるいは丁寧な文字はやはり魅力的で、その人の背景に品の良さや真面目さといったものを感じるのではないでしょうか。こういう細やかさを感じることができる私たち日本人の感性は、大事にしていきたいですね。
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










