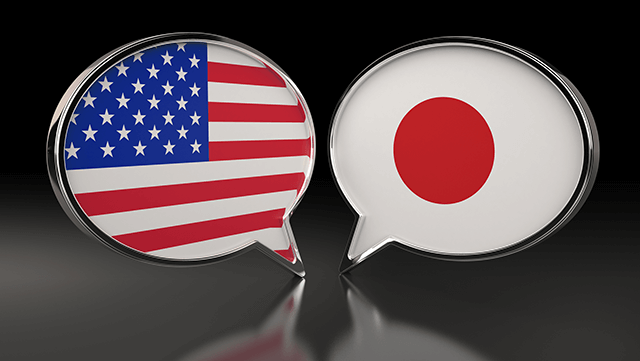●アメリカ国内の分断状況はかつてない深刻さ
―― 吉田先生、「米国の対中政策~戦略の現状の課題」の講義、まことにありがとうございました。ぜひ、こちらにつきまして質疑応答をお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。
吉田 よろしくお願いします。
―― 吉田さん、どうもありがとうございました。毎回毎回充実度が上がってくるので、いつも楽しく聞かせていただいております。
COVID-19を境に米中対立がさらに激化してきている状況が、今日の吉田さんの説明で分かりました。第一次世界大戦の死者を上回るようなコロナの問題があり、香港の問題があって、トランプ対バイデンというアメリカ大統領選があり、米国内を分裂してしまうようなデモクラシーへの闘いがあった。ワシントンの安全地帯に住んでおられる吉田さんのお家でも騒動に巻き込まれたということでしたね。
今回のお話で私どもが非常に危惧しているのは、トランプとバイデンというよりも、その後方にいる人たちの分断がかなり決定的になっていることです。アメリカの「対中戦略」と同時に、アメリカ国内の分断がここまで強くなった時期はなかなか見たことがない感じがします。そのあたり、いかがでしょうか。
吉田 私は、1991年から93年に最初にアメリカに来ました。「イージスシステム」のための留学でしたが、ニュージャージーの田舎に住みました。当時アメリカで問題になっていたのは、いわゆる教育の問題や経済不況、さらに都市部では白人が郊外に出ていき、マイノリティの人たちが流入するという一種のドーナツ化現象もありました。
そのような社会的問題はあったにせよ、例えばその頃戦われていた湾岸戦争などについては、まさに国を挙げる体制で、これほどまとまるものかというところを見せてくれました。問題が深刻な割にはいつも楽観的だった気がします。一言でいうと、「明日は今日よりもいいのではないか」という姿勢です。
●ディベート慣れした大統領候補のテレビ討論会
吉田 次に2005年には在米日本大使館の防衛駐在官のトップとしてアメリカに来て、やはり3年間いました。テロとの闘いの真っ最中でした。この時は共和党と民主党が相容れないような部分が出てきたにせよ、それでも超党派の合意があったように感じます。
ちょうどこの頃からソーシャルネットワークといったものが出現します。そ...