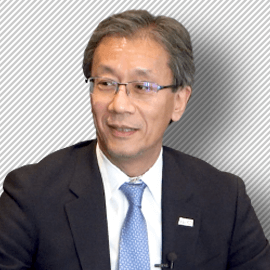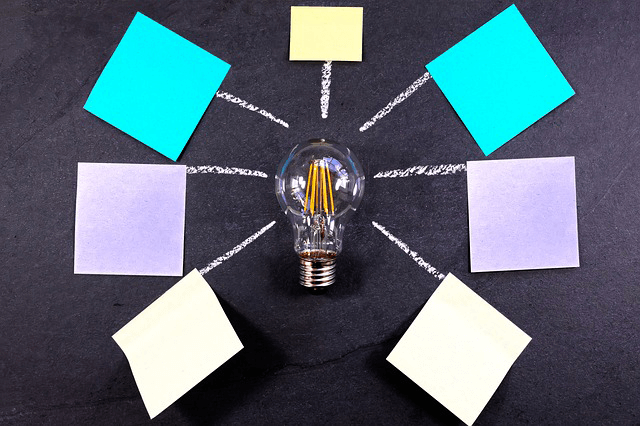●「これをやりたい」ということを予算より先に考える
―― 今まで日本の国立大学は、文科省の予算に縛られているため上限が決まっていて、どちらかというとどんどん減らされる方向で進んできました。藤井先生のような考え方でいくと、逆に、学生とともに(社会)実装することによって、お金も一緒に集まるような組立図が可能になりますね。
藤井 そうですね。やはりもう発想を変えなければいけないと思っています。今までは、まさにおっしゃる通り、配分された予算をどう配るかということで、上限も決まっていました。これからはむしろ、「これをやったらいいのではないか」ということを考えて、まず「やる」ということを決めていく。やるのだけど、そのためにはどうお金を手当しようか、という順番にするわけです。
私はこれまでに寄付や基金の担当もしてきましたが、これもやはり「これがやりたいんだ」ということがなければ、寄付をお願いするにしても、何のための寄付なのか分からないわけです。「やるべきこと」が先になければ、支援も受けられない。そこも、まさに「対話と共感」になると思います。
つまり、「こういうことがしたいので、ぜひ支援してください」。あるいは今のお話で言えば、「学生にぜひこれをやってもらいたい。この学生たちをサポートしてもらえませんか」という順番でものを考えるということだと思うわけです。
寄付でサポートできる場合もあるでしょうし、違う財源でカバーする場合もあるでしょうけれども、やはり発想の順番を変えないといけない。「なけなしのお金で、やれることだけをやろう」といった発想では、やはり活動全体が縮こまってしまうので、そこのマインドは変えないといけないと考えております。
●「好きなこと」が世界につながり、社会をよくしていく
―― 日本版「REIT」の取り組みが三井不動産の岩沙(弘道)さんの先導で行われてきました。彼も26年間にわたり不動産業のトップを走っているので、日本の会社では珍しい方です。マンハッタンやロンドンがどうしてきれいになったのかを研究していて、REITの仕組みにたどり着かれました。2600億でスタートしたものが、今では34兆ぐらいになっています。東京が大改革できたのは、REITと規制制限の撤廃が大きかった。これがなければ、こんなに短期間で東京はきれいにならなかったと思います。しかも、34兆の資金が湧...