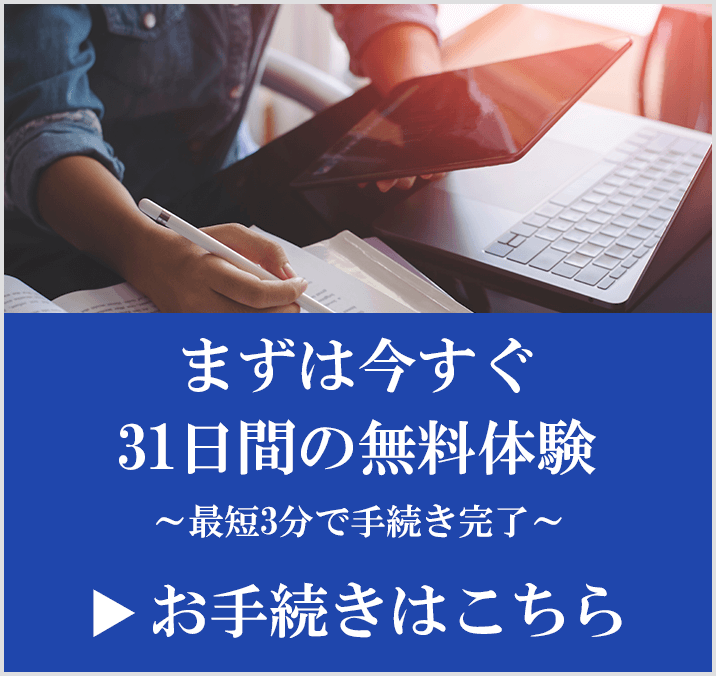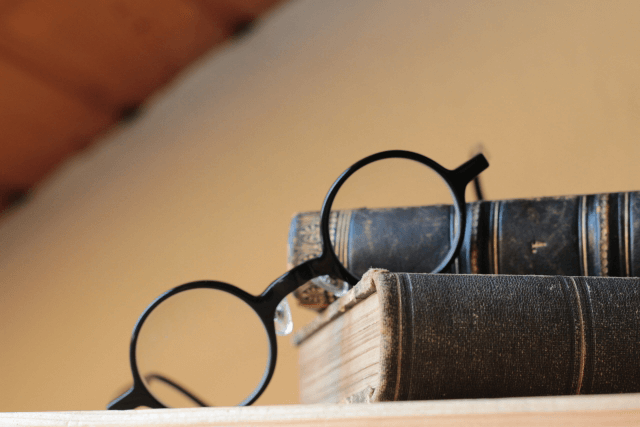●小林秀雄を理解するには近代日本小史から
皆さん、こんにちは。文芸批評家の浜崎洋介です。今回は、吉本隆明あるいは小林秀雄についての講義の第2回目です。いよいよ小林秀雄について少し見ていきたいと思っているわけです。
ただ、先にこれも結論から言っておきますが、小林秀雄は「近代批評の祖」とか、「近代文芸批評の父」とか、そのようにいわれることが多いのですが、重要なのは、彼が昭和初期に登場してきていることなのです。
実は前回の講義の中で二葉亭四迷の話を少ししましたが、彼は明治20年代に出てくるのです。それで言文一致をつくって、日本の近代小説の父になっていくわけです。ただ、小林秀雄は「近代批評の祖」といわれながら、なぜか昭和なのです。これは実は意味があると私は思っています。というのは、昭和にならないと出てこない問題があったからだといえるかと思います。
ということは、小林秀雄の言っていること、あるいはやっていることを理解するためには、ちょっと日本近代史をさらっておく必要があるし、たぶんそちらのほうが小林秀雄の言っていることが分かりやすいと思います。それでちょっと今回は、「近代日本小史」と名づけて少し議論をしていきたいなと思っています。
まず見ておきたいのは、明治維新からということになります。これは本当に簡単にまとめるしかないのですが、薩摩と長州による尊王倒幕思想があったということはもう皆さんご存じだと思います。最初は尊王攘夷だったのです。攘夷ということは外国を打ち払うということなのですが、これが薩摩と長州が逆に負けることによって、尊王攘夷ではなく、攘夷はできないから、倒幕をして、その限りにおいて私たちの政府をつくり上げ、日本を西洋近代化してより強くするということに舵を切るのです。
つまり彼らは、日本の独立を守るために、西洋近代化をしなければならないのだということを語り出します。しかし、これは非常にアイロニカルです。つまり日本の独立ということは、日本ということが主語なのですが、そのためになんと西洋化するということですから、非常に矛盾に満ちた、そのような作業をせざるを得なかったのです。
これを「和魂洋才」と当時言ったわけです。これは幕末の思想家である佐久間象山という人が言ったわけですが、そういう矛盾を強...