●歴史学は果たして凡人の領域なのか
皆さん、こんにちは。歴史について、皆さんも私たちも、実は内心ひそかに考えていることがあります。歴史学者は、格別の才能や天分がなくても務まる平凡な職業ではないか、歴史学は凡人の領域ではないかということです。歴史学者や歴史学はそのように人に思い込ませるところがあります。しかし、果たしてそうでしょうか。
その原因の一端は、歴史学が法学や経済学のように、社会科学としての原理と応用の関係に認知された共通の基準や知識を必要とせず、実地の結果や成果によって社会の審判を受けることも少ないからでしょう。
私は、政治学や社会学の友人から、「自分は歴史をやっている」と言われたことがあります。つまり、自分たちは政治学や社会学の専門家である一方、歴史学の徒でもあるという理解があるのです。自分たちの方法は歴史学的だと思っているのだろうと思います。歴史学はそれほど気楽な学問だと思われているのかと驚きました。
●多くの人は歴史を虚勢の道具としてしか使わない
私たち歴史家は、自戒を込めて、自分たちの学問を考えるべきだと思います。私が学生時代に感銘を受けた半世紀ほど前の東洋史・アジア史の研究者に、増井経夫さんがいます。増井さんは、『アジアの歴史と歴史家』という書物の中でこのようなことを言っています。すなわち、「学界が社会の装飾になり終ると、花鳥風月を心とする人も実践に情熱を傾ける人も、所詮は才も学も識も虚勢の道具としてしか使わなくなった」という警世の言であります。
つまり、才能と学問があり、見識を持っている人も、歴史を虚勢の道具としてしか使わないということです。結果的に今、日本の歴史の針路、日本の未来について、文明論的な洞察と過去とのバランスが取れた対話を歴史学者に期待する市民は、どれほどいるでしょうか。
最近顕著な現象があります。私たちが歴史的実証、あるいは歴史的な作業と呼ぶ非常に地味な学問的手法、つまり地道に史料を読む努力をしなければならないのが本来の歴史学です。しかし、このような作業を経ていない歴史学以外の学者、はたまた創作を事にする作家や、社会についてあれこれ語る評論家たちも、左右を問わず、自分は歴史を勉強している、歴史に対して自分は真摯に向かい合っていると語り、戦争責任や植民地支配といった問題に関わる論争のあたかも主役...











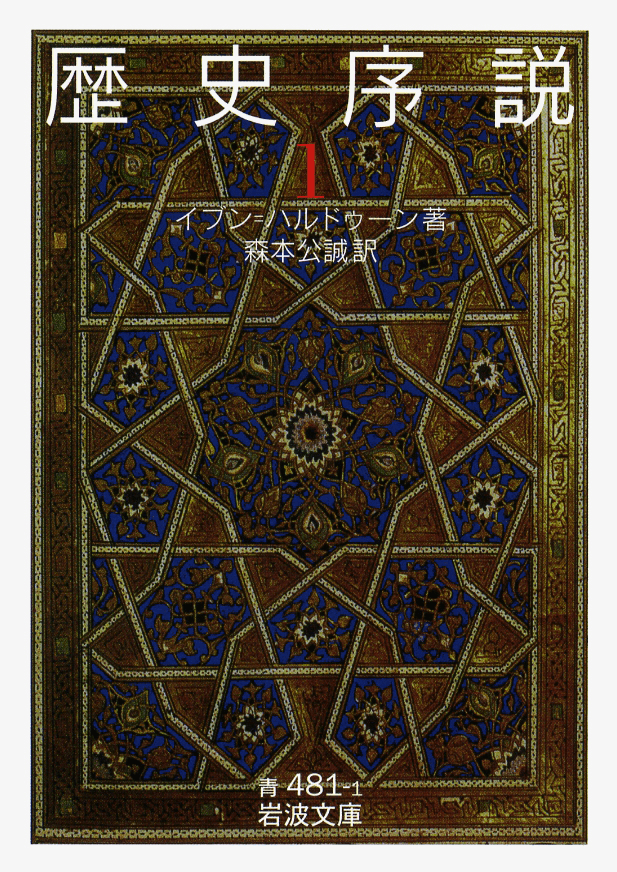

(イブン=ハルドゥーン 著、森本公誠翻訳、岩波文庫)