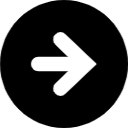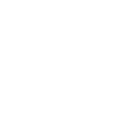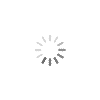西洋では逆境を神からの「試練」と捉えたが、神道では「祟り」と捉える。祟りに対しては下手の考え休むに似たり、儀式の中で和解するしかない。16世紀の哲学者モンテーニュは、ペストの流行や宗教戦争の中、たくましく生きる百姓たちに憧れを抱いた。そして彼は自分が固定観念にがんじがらめになっていると告白している。そこにあるのは「弱さの力」ではないだろうか。(全10話中第7話)
※インタビュアー:川上達史(テンミニッツ・アカデミー編集長)
≪全文≫
●信仰と哲学の関係、日本ではどうだったのか
―― ここで最初のお話に戻るのですが、「逆境は何の逆だろう」という話になったときに、板東先生のほうから、日本の神道においては神様が出てくるのがそういうシーンだというお話がありました。そして、これもまた前半のほうの話でしたけれども、超越者、全知全能、要するに創造主としての神がいる場合、特にプロテスタントなどの場合は「全てを神が決めている」と。だから試練があったとき、「この試練は神様が作ったものですから」と、本当に心の底から思えるかどうかというところがある。
本当に心の底からそう思っている方であれば、今ご指摘のあったネガティブ・ケイパビリティを多分持っているはずなんですよね。「それは神様がお作りになった試練ですから、それを感受するのが私の務めでございます」ということになるでしょう。あるいは日本の神道のように、そこに神がいるということになる場合には、その神様に来ていただいて、おもてなしで去っていただけるかどうかは分からないですが、何らかの対処をしなければいけない局面だという認識になってくるでしょう。
今日のお題は「逆境に対峙する哲学」ですが、逆境ということでみた場合に、自分で考えたり、何かする哲学の部分と、信仰的な部分というのでしょうか。日本の神様であれ全知全能の神様であれ、「それがあると、いわゆるネガティブ・ケイパビリティが持てます」ということになった場合、方法論はいろいろあるような気がします。その部分について哲学するとなると、信仰の部分と哲学の部分はどういう関係性になるのだろうか。ここのところを神道のほうから言うと、板東先生、いかがなものですか。
板東 そうですね。神道というか、「逆境と対峙する哲学」のテーマをいただいたときに私が思ったことです。逆境に陥ったときに哲学するというのが原理的に考え抜くということだとすると、何かの日常が破れて危機に陥ったときに、「考えることで救われることはあるのだろうか」という気がちょっとしました。つまり、逆境に陥ったときに哲学するべきなんだろうかということです。
「信じる」というのは、古典的には昔は信じていたわけです。逆境に陥ったらとりあえず、日本なら神仏ですし、別の宗教圏では別の神様でしょうが、心から信じることで救われる。それにより、逆境に対するある程度の対処ができる。...