テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
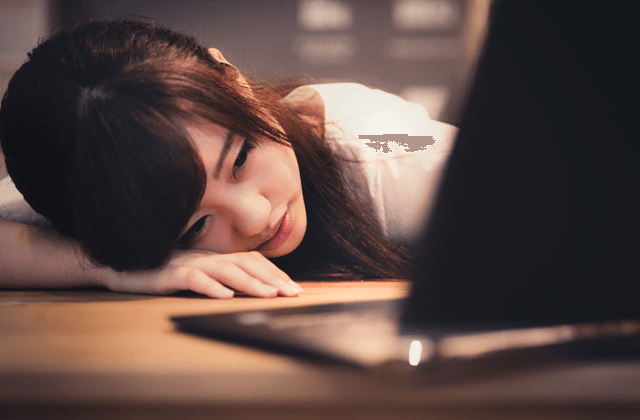
「残業」は何時間を超えると健康リスクが増すのか?
働き方改革やワークライフバランスの改善など、仕事との付き合い方、向き合い方に多くの人が悩み、国も動き出す時代です。長時間労働を強いられ、体を壊したり、うつ病を発症してしまう人も増え、最悪の場合は過労死や、過労自殺をするという事件もしばしば目にします。
しかし、いざ多忙な状況になり毎日何時間も残業が続いても、「まだ大丈夫」「まだできる」と、ついつい自分に厳しくなってしまったり、無理をしがちではありませんか? いったい、どのぐらいの残業をすると健康に害が出てくるのでしょうか?
具体的な健康被害としてあげられるのは、心臓病や脳卒中です。人は1日に8時間の睡眠を必要とするといわれていますが、残業時間が増えれば、その分睡眠時間は削られていきます。若い世代であれば、多少の無理はきくでしょうが、2時間、3時間などの短い睡眠が何か月も続いた場合、それは生死に関わるような事態に発展する可能性もあるのです。
また、1日に残業なしで7~8時間働く人がうつ病になる確率を1とすると、1日11~12時間働く人では、2倍以上に跳ね上がったというイギリスの研究結果もあり、過度の残業は、体だけでなく心にも深い傷を残しかねません。
海外の調査では、週の労働時間が36~40時間の場合の脳卒中を発症するリスクを1とすると、週の労働時間が55時間以上の場合は、1.33倍になりました。
長時間仕事をしたり、1週間で6日や7日も仕事にとられると、ストレスがたまります。そのストレスは、精神的な負荷だけではなく、暴飲暴食やタバコやアルコールの過剰摂取などにつながり、体を少しずつむしばんでいきます。自分がいったいどのくらい働いているのか、客観的に見つめ直すことも必要かもしれません。
とはいえ、日本では周囲に合わせ長時間仕事をしたり、もう仕事が終わっていても、切り上げると仕事をしていないように見られるといった風潮が根強くあります。今後は、こうした意識をひとりひとりが変えて行く必要性があるといえるでしょう。
また、「これくらいの残業当たり前だ」という人もいますし、実際にそうした労働環境でも問題なく働けている人がいるのも事実です。しかし、やりがいのある人の残業100時間と、精神的に追い詰められ、辛い仕事を押しつけられている人の残業100時間では、まったく意味合いが異なります。
ひとりひとりの形にあった仕事の環境を整えていくことや、お互いに理解しあい、仕事のバランスを変えていくことが、今後の社会の課題ともいえます。
しかし、いざ多忙な状況になり毎日何時間も残業が続いても、「まだ大丈夫」「まだできる」と、ついつい自分に厳しくなってしまったり、無理をしがちではありませんか? いったい、どのぐらいの残業をすると健康に害が出てくるのでしょうか?
労災認定のおりる基準は1か月100時間を超える残業
過労によって脳や心臓に疾患が引き起こされた場合、労災認定基準では、時間外労働が1か月で100時間超、2か月または6か月の平均で80時間超が基準とされています。これは、世界中の医学的根拠に基づく研究結果をまとめ、導き出された数値で、月45時間以内の残業であれば、健康障害を起こす危険性は低いと判断されています。逆に、時間外労働が月100時間を超え、継続して長時間の労働を行った場合、健康被害のリスクが高くなると考えられ、労災認定基準にはこの数値が使われているのです。具体的な健康被害としてあげられるのは、心臓病や脳卒中です。人は1日に8時間の睡眠を必要とするといわれていますが、残業時間が増えれば、その分睡眠時間は削られていきます。若い世代であれば、多少の無理はきくでしょうが、2時間、3時間などの短い睡眠が何か月も続いた場合、それは生死に関わるような事態に発展する可能性もあるのです。
また、1日に残業なしで7~8時間働く人がうつ病になる確率を1とすると、1日11~12時間働く人では、2倍以上に跳ね上がったというイギリスの研究結果もあり、過度の残業は、体だけでなく心にも深い傷を残しかねません。
残業をしていないからといってリスクが0ではない
しかし、残業が少なければ安心というわけでもありません。少ない残業時間でも、その分、別日に働いていたり、勤務日数が多くなると、やはり健康被害のリスクが高まるといわれています。海外の調査では、週の労働時間が36~40時間の場合の脳卒中を発症するリスクを1とすると、週の労働時間が55時間以上の場合は、1.33倍になりました。
長時間仕事をしたり、1週間で6日や7日も仕事にとられると、ストレスがたまります。そのストレスは、精神的な負荷だけではなく、暴飲暴食やタバコやアルコールの過剰摂取などにつながり、体を少しずつむしばんでいきます。自分がいったいどのくらい働いているのか、客観的に見つめ直すことも必要かもしれません。
仕事との関わり方を社会全体で考えていこう
現在、国は月に残業の上限を45時間、年間で360時間を基準に、残業を制限する方針で動いています。繁忙期は1か月でも100時間の残業、それを含めて、年間720時間までを認めるというものです。とはいえ、日本では周囲に合わせ長時間仕事をしたり、もう仕事が終わっていても、切り上げると仕事をしていないように見られるといった風潮が根強くあります。今後は、こうした意識をひとりひとりが変えて行く必要性があるといえるでしょう。
また、「これくらいの残業当たり前だ」という人もいますし、実際にそうした労働環境でも問題なく働けている人がいるのも事実です。しかし、やりがいのある人の残業100時間と、精神的に追い詰められ、辛い仕事を押しつけられている人の残業100時間では、まったく意味合いが異なります。
ひとりひとりの形にあった仕事の環境を整えていくことや、お互いに理解しあい、仕事のバランスを変えていくことが、今後の社会の課題ともいえます。
<参考サイト>
・1日何時間残業すると健康を害するのか
http://president.jp/articles/-/22452
・1日何時間残業すると健康を害するのか
http://president.jp/articles/-/22452
人気の講義ランキングTOP20










