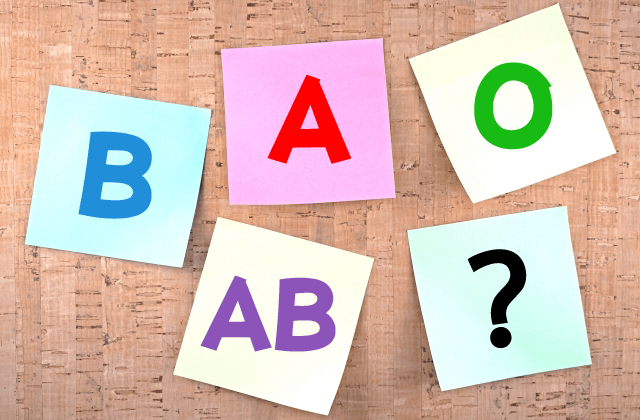
血液型って変わることがあるってホント?
私たち人間は両親から血液型の遺伝子を受けつぎ、基本的には一生変わることがありません。
しかし、どうやら血液型が変わってしまうという話があるようです。血液型が途中から変わったら人の体はどうなってしまうのでしょう。いったいどうしてそんなことが起きるのか、調べてみました。
ヒトの血液型は、それぞれ赤血球の表面に抗原をどう持つかで決まります。A型の人はA型抗原、B型の人はB型抗原、O型はどちらも持たず、AB型はどちらも持ちます。またそれぞれ、抗体というものを持ち、AはBへの抗体があり、BはAへの抗体、OはABどちらの抗体も持ち、ABはどちらも持ちません。
新生児には血漿内抗A型抗体、抗B型抗体がまだしっかりと作られていないため、検査しても反応が弱く、別の型として見られてしまう可能性があるというのです。この抗体が作られ、はっきりと血液型がわかるようになるのは4歳からと言われています。
また、このとき血球と反応させて血液型を調べる「オモテ試験」と血清(血液細胞以外の液体部分)と反応させる「ウラ試験」というものがあり、乳幼児のうちにするのは「オモテ試験」のみのため、血液型を判断する材料が少なく、間違って判定されてしまう場合があるのだそうです。
こうした事実を踏まえ、今では新生児は血液型の検査をしないと決めているところが多いそうです。
骨髄移植とは、骨髄提供者から採取した髄液を患者に移植する治療方法です。白血病や免疫不全症など、命にかかわる病気であり、また抗がん剤などの化学療法が使えない人に有効とされます。
骨髄液の中には、「造血幹細胞」というものが入っています。これは、血球成分を作る働きを持ち、血を作ります。そして移植の際には、「型が合う」ことが条件となってくるのですが、ここでの型は、血液型のことではなく、白血球(HLA)の型のことなのです。これが合えば、血液型は違っていても問題ないのです。
ドナーから提供された骨髄液により、血球成分が作られるようになると、患者の血液型は、ドナーと同じものになります。つまり、まったく別の血液型になってしまうということなのですね。
知っておいても良いかもしれませんが、知らなくても何ら問題はないということですね。
しかし、どうやら血液型が変わってしまうという話があるようです。血液型が途中から変わったら人の体はどうなってしまうのでしょう。いったいどうしてそんなことが起きるのか、調べてみました。
新生児の血液型はあやふや?
血液型は、赤ちゃんが生まれたとき、親に知らされることがあります。ここで親は我が子が何型かを知るわけですが、実はこのとき知らされる型は、不正確なものなのです。ヒトの血液型は、それぞれ赤血球の表面に抗原をどう持つかで決まります。A型の人はA型抗原、B型の人はB型抗原、O型はどちらも持たず、AB型はどちらも持ちます。またそれぞれ、抗体というものを持ち、AはBへの抗体があり、BはAへの抗体、OはABどちらの抗体も持ち、ABはどちらも持ちません。
新生児には血漿内抗A型抗体、抗B型抗体がまだしっかりと作られていないため、検査しても反応が弱く、別の型として見られてしまう可能性があるというのです。この抗体が作られ、はっきりと血液型がわかるようになるのは4歳からと言われています。
また、このとき血球と反応させて血液型を調べる「オモテ試験」と血清(血液細胞以外の液体部分)と反応させる「ウラ試験」というものがあり、乳幼児のうちにするのは「オモテ試験」のみのため、血液型を判断する材料が少なく、間違って判定されてしまう場合があるのだそうです。
こうした事実を踏まえ、今では新生児は血液型の検査をしないと決めているところが多いそうです。
本当に途中で変わる希有な例
非常にまれなケースですが、判定のあやふやさではなく、はっきりした型がわかっているにもかかわらず、血液型そのものが変わってしまうケースというものも存在します。それは、骨髄移植を受けた人に起こりえます。骨髄移植とは、骨髄提供者から採取した髄液を患者に移植する治療方法です。白血病や免疫不全症など、命にかかわる病気であり、また抗がん剤などの化学療法が使えない人に有効とされます。
骨髄液の中には、「造血幹細胞」というものが入っています。これは、血球成分を作る働きを持ち、血を作ります。そして移植の際には、「型が合う」ことが条件となってくるのですが、ここでの型は、血液型のことではなく、白血球(HLA)の型のことなのです。これが合えば、血液型は違っていても問題ないのです。
ドナーから提供された骨髄液により、血球成分が作られるようになると、患者の血液型は、ドナーと同じものになります。つまり、まったく別の血液型になってしまうということなのですね。
本当の血液型を知らないリスクはあるのか
自分が認識している血液型が違うのなら、いざというときに危ないのでは?と思われる方もいるかもしれません。結論から言うと、わからなくても問題はありません。輸血が必要なときには、ABO型以外にも、RH型、その他さまざまな要素が適合するかどうかを調べる必要がありますし、血液型がわからずに献血に行ったとしても、そこで調べることになります。知っておいても良いかもしれませんが、知らなくても何ら問題はないということですね。
ほとんどは思い違いだが、変わることは「ある」
以上のことから、血液型が変わったという経験のある人は、多くの場合、赤ちゃんのときに検査した結果が間違っていたということになります。もし、正確な血液型を知りたいのであれば、改めて検査してみることをおすすめします。
<参考サイト>
・ヘルスケア大学 血液型が変わる場合とは?
http://sp.skincare-univ.com/article/012678/
・JMDP 日本骨髄バンク 患者さんへ 移植が有効といわれる疾患について
http://www.jmdp.or.jp/recipient/info/effective.html
・神戸骨髄献血の和を広げる会 骨髄移植って骨を削るの?
http://www.marrow.or.jp/kobe/bmt.html
・ヘルスケア大学 血液型が変わる場合とは?
http://sp.skincare-univ.com/article/012678/
・JMDP 日本骨髄バンク 患者さんへ 移植が有効といわれる疾患について
http://www.jmdp.or.jp/recipient/info/effective.html
・神戸骨髄献血の和を広げる会 骨髄移植って骨を削るの?
http://www.marrow.or.jp/kobe/bmt.html
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部







