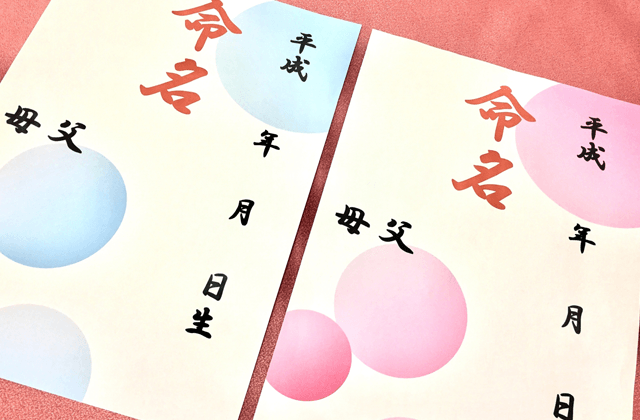
新たな流行は?親の子どもの「名づけ」事情
子どもは大切な授かりもの。親はすてきな名前をつけてあげたいとはりきりますよね。だけど中には、「この世にひとりだけの子どもには、名前もオンリーワンのものを」と意気込みすぎて、あまりに無理のある名づけをしてしまう親もいます。このような名前は「キラキラネーム」と呼ばれてTVやネットニュースで扱われることも多いので、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
一時期はブームのようになったこのキラキラネームですが、「親の常識が疑われる」、「いじめの原因になる」などの理由で最近は減少傾向にあります。子ども服の企画販売を手掛けるミキハウスの調査では、特に10代から20代の両親の52%が名づけの際にキラキラネームを避けるよう意識しているという結果が出ました。この年代だと自分自身や友人がキラキラネームという可能性もあるので、より重視されているのでしょう。
ミキハウスが現在と一世代前での名づけの主体を比較した調査では、どちらも両親が最も多い結果になりました。しかし父親は一世代前で64.2%だったのが現在は74.4%、母親は57.5%だったのが71.7%と、両親の名づけが大きく延びています。逆に減ったのは祖父母による名づけですが、母方の祖母の名づけは1.8%から2.8%に延びており、父方の祖父が4.6%から0.7%に減ったのと対照的な結果になりました。
また、医療技術の発展によって名づけのタイミングも大きく変わっています。かつては赤ちゃんが生まれてくるまで性別がわからなかったので、誕生してから名前をつけるのが主流でした。しかし近年は妊娠中の検査で赤ちゃんの性別がわかるようになったので、半数以上の両親が誕生前に名前をつけるようになりました。ミキハウスの調査では53.9%の両親が妊娠中に性別がわかった時点で名づけをしたと回答しています。
もちろん赤ちゃんの性別は生まれたときのお楽しみにしている両親もいるので、誕生後の名づけが少数派になったわけではなく、選択の幅が広がったといえるでしょう。
韓国では「胎名」と呼ばれる古くからの習慣で、芸能人のおめでた報道などでは必ずといっていいほど胎名にも触れられます。韓流ドラマの流行で日本でも知られるようになり、モデルの蛯原友里さんの妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里さんが、自身のおなかの中の子どもに「げんき」という胎児ネームをつけていることをブログで紹介すると一般的にも広まりました。
ミキハウスの調査では70.5%の両親が胎児ネームを知っており、56.2%の両親は実際に胎児ネームをつけていました。正式な名前ではないので気軽につけられることもあり、その由来はさまざま。妊娠が確定した日などの記念日や、おなかの中の赤ちゃんの様子にちなんだものなどがあります。
胎児ネームをつけることで誕生前から赤ちゃんに愛着がわき、夫婦間で赤ちゃんについて話す機会も増えるようです。親になる自覚が芽生えにくい父親も胎児ネームで呼ぶことで実感を得られるので、胎児ネームは今後いっそう一般的になっていきそうです。
最近の親が子どもの名づけで重視する点
キラキラネームに厳密な定義はありませんが、例えば、海外で使われている言葉や、アニメやゲームのキャラクターのものだったりする発音に、無理のある漢字で当て字をしているような名前を指したりします。たとえば「碧空」と書いて「みらん」、「光宙」と書いて「ぴかちゅう」、「今鹿」と書いて「なうしか」など。どれも簡単には読めませんよね。一時期はブームのようになったこのキラキラネームですが、「親の常識が疑われる」、「いじめの原因になる」などの理由で最近は減少傾向にあります。子ども服の企画販売を手掛けるミキハウスの調査では、特に10代から20代の両親の52%が名づけの際にキラキラネームを避けるよう意識しているという結果が出ました。この年代だと自分自身や友人がキラキラネームという可能性もあるので、より重視されているのでしょう。
こんなに変化した子どもの名づけの主流
実はキラキラネーム以外のところでも、子どもの名づけ事情は以前からかなり変化しています。ミキハウスが現在と一世代前での名づけの主体を比較した調査では、どちらも両親が最も多い結果になりました。しかし父親は一世代前で64.2%だったのが現在は74.4%、母親は57.5%だったのが71.7%と、両親の名づけが大きく延びています。逆に減ったのは祖父母による名づけですが、母方の祖母の名づけは1.8%から2.8%に延びており、父方の祖父が4.6%から0.7%に減ったのと対照的な結果になりました。
また、医療技術の発展によって名づけのタイミングも大きく変わっています。かつては赤ちゃんが生まれてくるまで性別がわからなかったので、誕生してから名前をつけるのが主流でした。しかし近年は妊娠中の検査で赤ちゃんの性別がわかるようになったので、半数以上の両親が誕生前に名前をつけるようになりました。ミキハウスの調査では53.9%の両親が妊娠中に性別がわかった時点で名づけをしたと回答しています。
もちろん赤ちゃんの性別は生まれたときのお楽しみにしている両親もいるので、誕生後の名づけが少数派になったわけではなく、選択の幅が広がったといえるでしょう。
新たな流行になっている胎児ネーム
また最近は、「胎児ネーム」をつけることが新たなブームになっています。胎児ネームとは読んで字のごとく、おなかの中の赤ちゃんにつける名前。戸籍に登録する名前ではなく、あくまで妊娠期間中だけの愛称です。韓国では「胎名」と呼ばれる古くからの習慣で、芸能人のおめでた報道などでは必ずといっていいほど胎名にも触れられます。韓流ドラマの流行で日本でも知られるようになり、モデルの蛯原友里さんの妹でチャイルドボディセラピストの蛯原英里さんが、自身のおなかの中の子どもに「げんき」という胎児ネームをつけていることをブログで紹介すると一般的にも広まりました。
ミキハウスの調査では70.5%の両親が胎児ネームを知っており、56.2%の両親は実際に胎児ネームをつけていました。正式な名前ではないので気軽につけられることもあり、その由来はさまざま。妊娠が確定した日などの記念日や、おなかの中の赤ちゃんの様子にちなんだものなどがあります。
胎児ネームをつけることで誕生前から赤ちゃんに愛着がわき、夫婦間で赤ちゃんについて話す機会も増えるようです。親になる自覚が芽生えにくい父親も胎児ネームで呼ぶことで実感を得られるので、胎児ネームは今後いっそう一般的になっていきそうです。
<参考サイト>
・ミキハウス出産準備サイト:ミキハウス「名づけ調査」から見えた「胎児ネーム」と「名づけ」に込めるママ・パパの想い
http://baby.mikihouse.co.jp/information/post-8898.html
・ミキハウス出産準備サイト:ミキハウス「名づけ調査」から見えた「胎児ネーム」と「名づけ」に込めるママ・パパの想い
http://baby.mikihouse.co.jp/information/post-8898.html
人気の講義ランキングTOP20







