テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
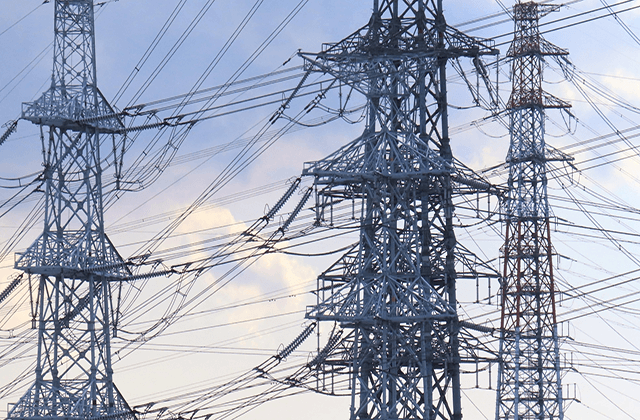
電気代に上乗せされている!?再エネの未来
電気代を払っている人なら、見守りたい
私たちの電気料金には、再生可能エネルギー(再エネ)を推進するための費用が上乗せされている。つまり、電気を使うすべての人にとって、再エネの進捗状況はヒトゴトではないのだ。三菱総合研究所理事長・小宮山宏氏(東京大学総長顧問)の見解では、再エネへの移行は2030年から2050年には確実に起こるという(『10MTV』収録「再生可能エネルギーの可能性―将来有望な中小水力発電」)。太陽光発電の買取拒否から半年、それに変わる方法は意外にも身近だ。
太陽の恵みは、想像を超えている
最初に再エネの原理と種類をおさらいしてみたい。現在利用できたり、30年以内に実用化できると小宮山氏が見込んでいる再エネは、風力、太陽光電池、水力、バイオマス、地熱の5種類である。これらはいずれも地球に降り注いでくる太陽エネルギーをもととしたものだ。あらためて意識することもないが、太陽から来るエネルギー量は人間がいま消費している総エネルギーの約1万倍に匹敵する。安定性や費用対効果など、バランスのとれた取り出し方さえ手にすれば、人類は枯渇することのないエネルギーを利用できる。
これからは「中小」水力発電に注目しよう
小宮山氏が率いる「プラチナ構想ネットワーク」では、いま進めるべき再エネとして中小規模の水力発電に注目している。黒四(黒部)ダムをはじめとする巨大ダムは開発され尽くした感があるが、地産地消型の小さな発電は手つかずの分野だからだ。「地域再生」がクローズアップされる現代日本で、水力発電に着目するメリットを順番に見ていこう。メリットその1 安定して良質
水力発電では、溜めた水が下に落ちる力で水車を回す。そこに発電機を付けておけば電力が取り出せるわけで、まったく環境に「わるさ」をしない。溜まった水を落とすタイミングも選べるため、エネルギーの質と安定性にかけては定評がある。メリットその2 自然の循環を邪魔しない
巨大ダムには自然破壊のイメージがついて回る。山から海へと自然に流れ込む水量が、ダムによる蒸発や農業用水への転用によって減っていくためだ。この点、中小水力発電では、流れている場所には手を加えず、ただ水車のような装置を差し込んでいくだけだ。このシステムが普及した将来には、現在の「ただ流れているだけ」にまかせる状況が「もったいない」と評される日も来るのではないかと小宮山氏は考えている。
メリットその3 普及するほど安くなる
良質で自然環境に優しい中小水力発電。しかし、これまで普及しなかったのにはやはり理由がある。コストの問題だ。単価というものは量産ができればどんどん安くなるのだが、本気で発電システムの改良に取り組まなかったのは、作っても売れないという思い込みがあったためだ。地域再生ブームが後押しとなり、このほどようやく採算の取れるシステム設計が出来上がってきた。後は適当な場所を探して設置すればよい。小宮山氏は農業用水路が規格化されている点に着目し、適切なタービンの取り付けを推奨している。
メリットその4 電気が地域の雇用をひらく
普及すればするほど安くなる中小水力発電は、地域経済の活性化に最適だ。工場が無人化している現代、人材が必要なのは現地での管理とメンテナンスである。田んぼの水車を見回り、地域のエネルギー状況を管理する仕事。そんな役割が脚光を浴びる日は遠くないのではないか。人気の講義ランキングTOP20
「大転換期の選挙」の前に見ておきたい名講義を一挙紹介
テンミニッツ・アカデミー編集部










