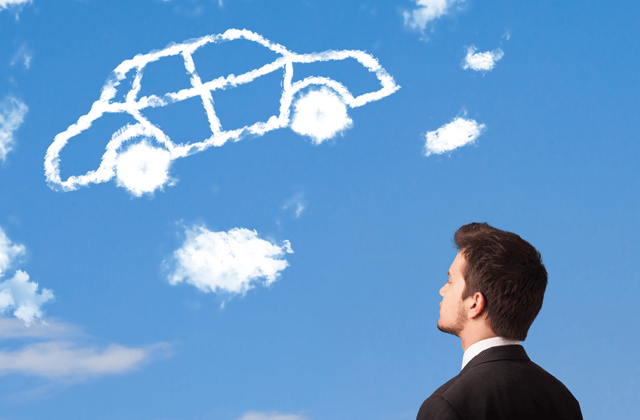
「空飛ぶクルマ」は実現するのか?
「空飛ぶクルマ」は、これまで映画やアニメなど様々なSFのジャンルで描かれてきました。それだけ私たちの夢を体現する存在と言えるでしょう。しかし、もはやこれは夢ではありません。経済産業省と国土交通省は、電動・自動で垂直離着陸して移動する「空飛ぶクルマ」の本格的な実証実験を2019年中にも始める方針です。すでに、国内メーカーだけでなく、欧州エアバス社、米国ボーイング社が参加を検討しています。経済産業省が2018年末にとりまとめたロードマップによると、2019年に試験飛行・実証実験、2023年を目標に事業スタート、2030年代から実用化をさらに拡大させていくという流れです。
これまでのヘリに使われるエンジンは複雑な仕組みでメンテナンスも大変でした。しかし、ドローンのような「空飛ぶクルマ」であれば、交換可能な「電気モーター」を用いるので大量生産でき、さらに自動運転技術を活用すれば操縦者も不要です。こういったところから、実用化されれば一気に普及するのではないかと考えられています。
従来の自動車メーカーや航空機メーカーもさまざまな方向から「空飛ぶクルマ」を作ろうとしています。イギリスの老舗自動車メーカー、アストンマーチンはSF映画に出てくるようなコンセプト機「Volante Vision」を発表しました。ポルシェも独自に開発に取り組んでいることが明らかになっています。また、アウディはエアバスなどと共に「Pop.Up Next」という空飛ぶタクシーのプロトタイプを発表しているほか、エアバスはまた独自で自動運転飛行機「Vahana」を開発中とのこと。日本ではトヨタ自動車が若手有志を中心としたプロジェクトに4000万円規模の資金を出資、2020年の東京オリンピックに向けて実用化を目指しています。
もちろんレジャーや高速移動、物流の手段としても魅力的です。また、新たな価値が生まれるかもしれません。たとえば、高層階のフロアに「空飛ぶクルマ」が発着できるホテルが出来れば、空港から直接チェックインが可能です。これまで空港に限定されていた「空」関連ビジネスが、日常に拡がることで、建設や広告といった業界の新たな需要が喚起される可能性があります。つまり「空飛ぶモビリティ関連マーケット」が拡大し、今後は、「発着場付き」が高級マンションの新たな象徴になるかもしれません。
肝心の技術についてはまだまだ改善の余地があります。問題の中心はバッテリーの重さと効率性にあるようです。Uber社によると、2018年の時点で最も優良なリチウムイオン電池はパナソニック製とのこと。しかし、Uberの考える「空飛ぶクルマ」を実用的に運用するには、まだまだ「重さに対するエネルギー密度」が足りないようです。また、充電をより早く行えること、かつ急速充電しても傷まないバッテリー、といった点でもさらなる質の向上が求められています。
「空飛ぶクルマ」は、電気推進技術(バッテリーを中心とした技術)の向上でその可能性が開けてきました。しかし、実用化に向けては、さらなる革新が必要です。ただ、バッテリーのテクノロジーは、社会の旺盛な需要に応じて猛スピードで進化しています。「空飛ぶクルマ」が一般的になる未来はそう遠くはないです。
大型ドローンに人が乗るイメージ
ロードマップでは、まず離島や山間部で事業を始め、2020年代に都市部へと飛行を拡大する方針です。実証試験は羽田空港周辺や大阪湾の舞洲(まいしま)、三重県志摩市の離島、福島県の福島ロボットテストフィールドなどで行うとのこと。経済産業省のサイトに示された画像や動画では、人を載せた大型ドローンという感じです。実際にここで想定されているものは、ドローン(小型無人機)やEV(電動自動車)の技術を応用し、複数のプロペラを電動で回転させて飛行するものです。これまでのヘリに使われるエンジンは複雑な仕組みでメンテナンスも大変でした。しかし、ドローンのような「空飛ぶクルマ」であれば、交換可能な「電気モーター」を用いるので大量生産でき、さらに自動運転技術を活用すれば操縦者も不要です。こういったところから、実用化されれば一気に普及するのではないかと考えられています。
海外の「空飛ぶタクシー」さまざまな形
海外でも、さまざまな会社が「空飛ぶクルマ」を開発しようとしています。主力は電力で動くEVTOL(Electric Vertical Take-Off and Landing = 電動垂直離着陸)式航空機と呼ばれるもので、無人運転を想定しているものが多い様子。Uberが提供する飛行車両サービス「UberAIR」では、EVTOL機を用いて、都心部にスカイポートを設置して乗客を乗降させるという形を想定しています。いわば、空飛ぶタクシー。飛行機をより小さな規模で運用するイメージでしょうか。従来の自動車メーカーや航空機メーカーもさまざまな方向から「空飛ぶクルマ」を作ろうとしています。イギリスの老舗自動車メーカー、アストンマーチンはSF映画に出てくるようなコンセプト機「Volante Vision」を発表しました。ポルシェも独自に開発に取り組んでいることが明らかになっています。また、アウディはエアバスなどと共に「Pop.Up Next」という空飛ぶタクシーのプロトタイプを発表しているほか、エアバスはまた独自で自動運転飛行機「Vahana」を開発中とのこと。日本ではトヨタ自動車が若手有志を中心としたプロジェクトに4000万円規模の資金を出資、2020年の東京オリンピックに向けて実用化を目指しています。
緊急時の活躍から新たなビジネスの創出まで
このように開発は急ピッチで進んでいますが、実際の需要はどういったものが見込めるでしょうか。もっとも大きな需要としては、救急車としての採用が考えられます。もちろん空を飛ぶので渋滞に捕まることはありません。また現状のドクターヘリではヘリポートの整備やフライトドクターの確保など運用面での負担が大きく、これが普及の足かせとなっています。これに対して、電動自動運転の「空飛ぶクルマ」が一般化すれば、簡単に、静かに、最短距離で自宅と目的地を往復することができるはずです。このことから僻地や離島における医療への貢献が考えられます。また比較的小規模のエアポートで対応可能なので、これまで空港や道路などといったインフラの巨額な維持費を圧縮できるかも知れません。もちろんレジャーや高速移動、物流の手段としても魅力的です。また、新たな価値が生まれるかもしれません。たとえば、高層階のフロアに「空飛ぶクルマ」が発着できるホテルが出来れば、空港から直接チェックインが可能です。これまで空港に限定されていた「空」関連ビジネスが、日常に拡がることで、建設や広告といった業界の新たな需要が喚起される可能性があります。つまり「空飛ぶモビリティ関連マーケット」が拡大し、今後は、「発着場付き」が高級マンションの新たな象徴になるかもしれません。
課題はバッテリーの軽量化と効率の向上
ただ、もちろん、何の障壁もなしにこの技術が実現する訳ではありません。「空飛ぶクルマ」はまだまだ開発段階です。日本での開発には1機100億円から300億円がかかるのではないか、という試算もあります。法律の整備も重要です。安全基準、運航の基準、離着陸をめぐる問題についてどのようなルールにしていくのかということもあります。またこの点は技術と制度両面から議論しなければうまくいかないので、技術が発展途上の今はまだまだ未知数ともいえます。肝心の技術についてはまだまだ改善の余地があります。問題の中心はバッテリーの重さと効率性にあるようです。Uber社によると、2018年の時点で最も優良なリチウムイオン電池はパナソニック製とのこと。しかし、Uberの考える「空飛ぶクルマ」を実用的に運用するには、まだまだ「重さに対するエネルギー密度」が足りないようです。また、充電をより早く行えること、かつ急速充電しても傷まないバッテリー、といった点でもさらなる質の向上が求められています。
「空飛ぶクルマ」は、電気推進技術(バッテリーを中心とした技術)の向上でその可能性が開けてきました。しかし、実用化に向けては、さらなる革新が必要です。ただ、バッテリーのテクノロジーは、社会の旺盛な需要に応じて猛スピードで進化しています。「空飛ぶクルマ」が一般的になる未来はそう遠くはないです。
<参考サイト>
・日本経済新聞:空飛ぶクルマ、19年にも全国4地域で実証 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40842430T00C19A2NN1000/
・経済産業省:“空飛ぶクルマ”の実現に向けたロードマップを取りまとめられている
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220007/20181220007.html
・Cnet Japan:Uber、「空飛ぶタクシー」の最新コンセプト仕様など披露
https://japan.cnet.com/article/35118926/
・日本経済新聞:空飛ぶクルマ、19年にも全国4地域で実証 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40842430T00C19A2NN1000/
・経済産業省:“空飛ぶクルマ”の実現に向けたロードマップを取りまとめられている
http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181220007/20181220007.html
・Cnet Japan:Uber、「空飛ぶタクシー」の最新コンセプト仕様など披露
https://japan.cnet.com/article/35118926/
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







