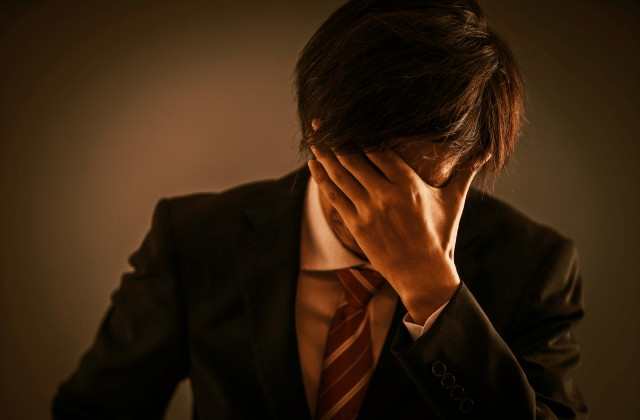
三日坊主はどうすれば克服できるのか?
健康のために毎日ジョギングをしよう。英会話のクラスに通ってスキルアップしよう。「よりよい自分」になるための目標をたて、そして三日坊主で挫折してしまう。こんな経験を持っている、いえ、繰り返している人も多いでしょう。
この悩ましくて身近な三日坊主問題はどう解決できるのか。そのヒントになりそうなのが、「行動分析学」です。行動分析学というのは心理学の一領域ですが、一般的な心理学とは異なり、人の行動の理由を「あの人はせっかちだから」「私には知識がないから」などと、心や性格、能力などで説明しません。人の行動と環境の関係性で考えてみようという学問なのです。
ここでは、三日坊主という問題を、行動分析学の観点から「目標を立てても長続きしない、達成できない」という行動とその背景となる環境の関係性から見てみます。
その1つは名づけて「ちりも積もれば山となる型」。これはいわば、毎日の行動の積み重ねが長期的な結果につながるタイプのことです。たとえば、健康のために毎日ジョギングをしよう。仕事のスキルアップのためにも英会話レッスンに通おう、と決心したのもどこへやら、続かなくなってしまったというのがこれに当たります。これらの行動の成果は、1回運動したから、1回練習したからといってすぐに現れるものではありません。毎日の行動がある程度の期間積み重なって初めて、本人がその成果を実感することができます。
もう1つは「天災は忘れた頃にやってくる型」です。たとえば、万一のパソコンのアクシデントに備えて、データバックアップはこまめに行おう、地震や台風などの防災対策は常日頃から心がけておこう、とアタマでは分かっていても、実際にパソコンがクラッシュしたり、大災害に遭遇するといった確率は低いため、ついつい常日頃の備えの行動はおろそかになってしまいます。
1つ目が、行動を記録に残し、かつその行動にほうびを与えるというもの。俗に言う「自分にごほうび」です。ちゃんとできたことを記録し、「1時間勉強したら10分コーヒーブレイク」といった簡単なほうびを与えることで、次の行動強化を促します。
2つ目が、行動を起こしやすい環境をつくること。行動分析学的には「行動コストを下げる」と言います。たとえば、教材は本棚にしまいこまない。いつでも開けるように手元に置く。当の島宗氏は興味を持って始めたウクレレの練習が進まないため、まず環境を見直しました。そして、ケースに入れて戸棚にしまっていたウクレレを、ケースから出してすぐそばに置くことで、気軽にいつでも練習できるようにしたと言います。また、これは作家の井上ひさし氏の話ですが、資料の読み込みに必要な本はいつでも読めるようにばらばらにして、手軽な形で持ち歩いていたとか。これも自ら環境を工夫した好例といえるのではないでしょうか。
要は、行動そのものではなく環境を行動が継続しやすくするように変えるのがポイントだということです。
三日坊主というのは、目標を達成できないというデメリットもさることながら、「また、挫折してしまった。なんて自分はだめなんだ」と自己嫌悪に陥ってしまう、という負の面も抱えています。そのうち「どうせ三日坊主で終わってしまうから」と何もやる気をなくしてしまうといった事態も招きかねません。そうなる前に、環境との関係で行動を変える行動分析学の考え方を取り入れてみてはどうでしょうか。
この悩ましくて身近な三日坊主問題はどう解決できるのか。そのヒントになりそうなのが、「行動分析学」です。行動分析学というのは心理学の一領域ですが、一般的な心理学とは異なり、人の行動の理由を「あの人はせっかちだから」「私には知識がないから」などと、心や性格、能力などで説明しません。人の行動と環境の関係性で考えてみようという学問なのです。
ここでは、三日坊主という問題を、行動分析学の観点から「目標を立てても長続きしない、達成できない」という行動とその背景となる環境の関係性から見てみます。
なぜ三日坊主になってしまうのか
まず、三日坊主になってしまう要因を分析すると2つの型が見えてくる、と行動分析学の研究者島宗理氏は言います。その1つは名づけて「ちりも積もれば山となる型」。これはいわば、毎日の行動の積み重ねが長期的な結果につながるタイプのことです。たとえば、健康のために毎日ジョギングをしよう。仕事のスキルアップのためにも英会話レッスンに通おう、と決心したのもどこへやら、続かなくなってしまったというのがこれに当たります。これらの行動の成果は、1回運動したから、1回練習したからといってすぐに現れるものではありません。毎日の行動がある程度の期間積み重なって初めて、本人がその成果を実感することができます。
もう1つは「天災は忘れた頃にやってくる型」です。たとえば、万一のパソコンのアクシデントに備えて、データバックアップはこまめに行おう、地震や台風などの防災対策は常日頃から心がけておこう、とアタマでは分かっていても、実際にパソコンがクラッシュしたり、大災害に遭遇するといった確率は低いため、ついつい常日頃の備えの行動はおろそかになってしまいます。
どうしたら三日坊主から脱却できるのか
では、どうしたら「やろうと思ったのに続かない」という三日坊主から脱却できるのでしょうか。島宗氏は、行動と環境の関係性から導き出す2つの方法を提案します。1つ目が、行動を記録に残し、かつその行動にほうびを与えるというもの。俗に言う「自分にごほうび」です。ちゃんとできたことを記録し、「1時間勉強したら10分コーヒーブレイク」といった簡単なほうびを与えることで、次の行動強化を促します。
2つ目が、行動を起こしやすい環境をつくること。行動分析学的には「行動コストを下げる」と言います。たとえば、教材は本棚にしまいこまない。いつでも開けるように手元に置く。当の島宗氏は興味を持って始めたウクレレの練習が進まないため、まず環境を見直しました。そして、ケースに入れて戸棚にしまっていたウクレレを、ケースから出してすぐそばに置くことで、気軽にいつでも練習できるようにしたと言います。また、これは作家の井上ひさし氏の話ですが、資料の読み込みに必要な本はいつでも読めるようにばらばらにして、手軽な形で持ち歩いていたとか。これも自ら環境を工夫した好例といえるのではないでしょうか。
要は、行動そのものではなく環境を行動が継続しやすくするように変えるのがポイントだということです。
三日坊主というのは、目標を達成できないというデメリットもさることながら、「また、挫折してしまった。なんて自分はだめなんだ」と自己嫌悪に陥ってしまう、という負の面も抱えています。そのうち「どうせ三日坊主で終わってしまうから」と何もやる気をなくしてしまうといった事態も招きかねません。そうなる前に、環境との関係で行動を変える行動分析学の考え方を取り入れてみてはどうでしょうか。
人気の講義ランキングTOP20
欧州では不人気…木村資生の中立説とダーウィンとの違い
長谷川眞理子







