テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
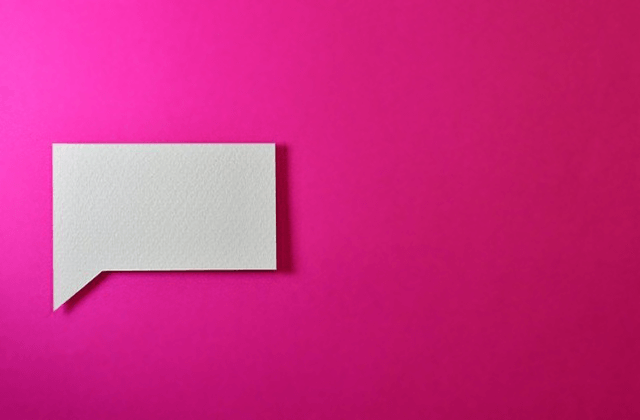
話が「面白い人」と「つまらない人」の違いとは?
話が面白い人には自然と人が集まり、ビジネスでも活躍している人が多いものです。一方で、自分の話はつまらない、と話すことに苦手意識を持っている人も意外と多いのではないでしょうか。
そこで今回は、話が「面白い人」と「つまらない人」の違いについて30人の男女にアンケート。話の「面白さ」に決定的な違いが出るポイントを見極め、聞く人が楽しく心地よく耳を傾けてくれるコツを分析していきます。
起承転結を意識して話すことは大切ですが、文章とは違い相手に直接語りかける時は、結果から伝えたり、大事な事を先に持って来たり、その組み立てをカスタマイズできると「面白い」と思われるよう。「何について話しているのか分からないと相手が聞く姿勢にならないから時系列ではダメ」、「やはり話が面白い人は相手が納得できる最短距離で話の順番を構成できる」など、伝える順序がいつも同じでは「つまらない」と思われてしまうようです。
・パンチラインがある⇔話が平坦で抑揚がない
「話が面白い友人はキーワード的な言葉を使うのが巧い。話が終わった後も、その言葉をつい皆が使っています」という方もいるように、話の内容を一言で印象づけるようなパンチライン、つまりパワーワードを使いこなすと「面白い」と感じるもの。色々話した後に「つまりこうゆうこと?」とまとめてしまわれるようなポイントのぼやけた話し方をすると、つまらない話だったということなのかもしれません。
・語彙力が豊富⇔同じ言葉ばかり繰り返す
「何を食べて美味しかった」というような話はよくありますが、ただ「美味しかった」「旨かった」ではなく、どんな味でどんな風に美味しかったのかを豊富な語彙力で伝えられると、聞く相手の想像力をかき立て「面白い」と感じるもの。「同じことを言うのでも、色んな言葉に置き換えられる人の話は新鮮に聞こえて飽きない」、「自分の話は、楽しかった、美味しかった、疲れたと単純な言葉しか出て来ないので話が膨らまない」など、言葉のバリエーションも話し上手の秘訣です。
・譬え話が巧い⇔譬えると余計分かりにくくなる
「ちょっと難しい話も譬え話ひとつで相手に理解させる人はすごい」「頑張って面白くしようとした譬え話で、相手を混乱させるつまらない先輩に困っている」と、譬え話は諸刃の剣。話が面白い人は、身近なことや相手の興味がある分野を引き合いに出して簡潔に伝えますが、つまらない人は装飾し過ぎたり、ウケを狙って突飛な例を挙げ、余計に話を複雑にさせてしまうのでは。何に譬えるかは、相手に合わせるべきものと意識したいですね。
・ストーリーで聞かせる⇔感情優先でひとりよがり
「愚痴のはずなのに、思わずもっと聞きたいと思ってしまう友人の話はワクワクドキドキのドラマ性がある」というように、単なる愚痴でも面白い、つまらないの差があるものです。一方、「つまらないのは、ひどい、辛い、許せないなど感情ばかりの愚痴」。愚痴に至るまでのストーリーや、エピソードなどがないと、聞いている方も「つまらない」を超えて「つらい」はず。聞く人を自分に引き寄せるには、シナリオのような物語も必要なのでは。
・臨場感がある⇔事実のみを伝える
聞いている人に、まるで目の前で起こっていることを見ているように感じさせるのが「臨場感」。相手が具体的に話を理解し引き込まれるには、この臨場感も欠かせないもの。「話上手の代表格の落語家さんは、オノマトペのような擬音語や擬態語、声のトーンや大きさ、スピードや間合いなどの緩急でも話を面白く演出している」という意見もありましたが、まさにその通り。直立不動で淡々と事実のみ伝えるのではなく、身振りや手振りも使って聞く人の心を掴むのも「面白い」のポイントです。
これから始まるドラマがあるとして、その内容が面白いこともさることながら、「こんなドラマが始まるよ!」「こんなテーマのドラマで、見所は…」といった、興味をそそる予告までできるのが、話が「面白い人」になれるかどうかの境界線なのかも。なんとなく着けたテレビで流し見されるだけのつまらないドラマにならないためにも、観る人=ここでは聞く人の興味や期待など、相手の立場を汲んだストーリーテラーになることを意識したいものですね。
そこで今回は、話が「面白い人」と「つまらない人」の違いについて30人の男女にアンケート。話の「面白さ」に決定的な違いが出るポイントを見極め、聞く人が楽しく心地よく耳を傾けてくれるコツを分析していきます。
「面白い」と「つまらない」の分かれ目、ここにあり!
・話しの組み立てが巧い⇔時系列でしか話せない起承転結を意識して話すことは大切ですが、文章とは違い相手に直接語りかける時は、結果から伝えたり、大事な事を先に持って来たり、その組み立てをカスタマイズできると「面白い」と思われるよう。「何について話しているのか分からないと相手が聞く姿勢にならないから時系列ではダメ」、「やはり話が面白い人は相手が納得できる最短距離で話の順番を構成できる」など、伝える順序がいつも同じでは「つまらない」と思われてしまうようです。
・パンチラインがある⇔話が平坦で抑揚がない
「話が面白い友人はキーワード的な言葉を使うのが巧い。話が終わった後も、その言葉をつい皆が使っています」という方もいるように、話の内容を一言で印象づけるようなパンチライン、つまりパワーワードを使いこなすと「面白い」と感じるもの。色々話した後に「つまりこうゆうこと?」とまとめてしまわれるようなポイントのぼやけた話し方をすると、つまらない話だったということなのかもしれません。
・語彙力が豊富⇔同じ言葉ばかり繰り返す
「何を食べて美味しかった」というような話はよくありますが、ただ「美味しかった」「旨かった」ではなく、どんな味でどんな風に美味しかったのかを豊富な語彙力で伝えられると、聞く相手の想像力をかき立て「面白い」と感じるもの。「同じことを言うのでも、色んな言葉に置き換えられる人の話は新鮮に聞こえて飽きない」、「自分の話は、楽しかった、美味しかった、疲れたと単純な言葉しか出て来ないので話が膨らまない」など、言葉のバリエーションも話し上手の秘訣です。
・譬え話が巧い⇔譬えると余計分かりにくくなる
「ちょっと難しい話も譬え話ひとつで相手に理解させる人はすごい」「頑張って面白くしようとした譬え話で、相手を混乱させるつまらない先輩に困っている」と、譬え話は諸刃の剣。話が面白い人は、身近なことや相手の興味がある分野を引き合いに出して簡潔に伝えますが、つまらない人は装飾し過ぎたり、ウケを狙って突飛な例を挙げ、余計に話を複雑にさせてしまうのでは。何に譬えるかは、相手に合わせるべきものと意識したいですね。
・ストーリーで聞かせる⇔感情優先でひとりよがり
「愚痴のはずなのに、思わずもっと聞きたいと思ってしまう友人の話はワクワクドキドキのドラマ性がある」というように、単なる愚痴でも面白い、つまらないの差があるものです。一方、「つまらないのは、ひどい、辛い、許せないなど感情ばかりの愚痴」。愚痴に至るまでのストーリーや、エピソードなどがないと、聞いている方も「つまらない」を超えて「つらい」はず。聞く人を自分に引き寄せるには、シナリオのような物語も必要なのでは。
・臨場感がある⇔事実のみを伝える
聞いている人に、まるで目の前で起こっていることを見ているように感じさせるのが「臨場感」。相手が具体的に話を理解し引き込まれるには、この臨場感も欠かせないもの。「話上手の代表格の落語家さんは、オノマトペのような擬音語や擬態語、声のトーンや大きさ、スピードや間合いなどの緩急でも話を面白く演出している」という意見もありましたが、まさにその通り。直立不動で淡々と事実のみ伝えるのではなく、身振りや手振りも使って聞く人の心を掴むのも「面白い」のポイントです。
話が「面白い人」は、聞かせる準備ができている?
30人の方からいただいたアンケートから抽出した6つの分かれ目は、いずれも「分かる!」というポイントだったのではないでしょうか。この6つの相違点を見てみると、話が「面白い人」とは、単にウケを狙えたり、笑えるオチをつけられるというのではなく、聞く相手の気持ちや、期待などを回収できる人だとも言えます。これから始まるドラマがあるとして、その内容が面白いこともさることながら、「こんなドラマが始まるよ!」「こんなテーマのドラマで、見所は…」といった、興味をそそる予告までできるのが、話が「面白い人」になれるかどうかの境界線なのかも。なんとなく着けたテレビで流し見されるだけのつまらないドラマにならないためにも、観る人=ここでは聞く人の興味や期待など、相手の立場を汲んだストーリーテラーになることを意識したいものですね。
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










