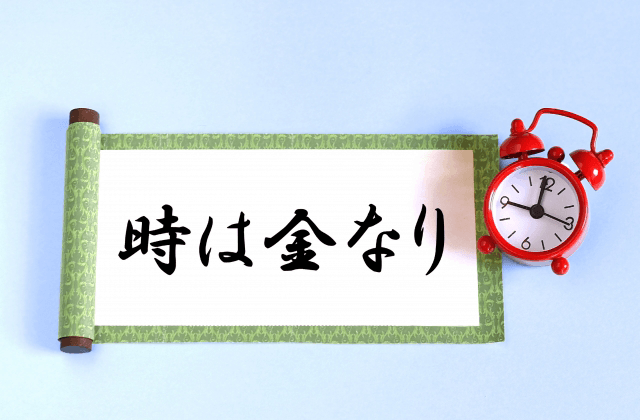
「時間をお金で買う」のは正解か?
「時間をお金で買う」と聞くと、「時は金なり」という言葉を連想する人も多いと思います。
「時は金なり」という格言は、アメリカの政治家・著述家・科学者であり、“すべてのヤンキーの父”とも称される、ベンジャミン・フランクリンの言葉「Time is Money」の翻訳です。
辞典では、「時間は貴重であり有効なものであるから、むだに費やしてはいけない。時間の尊さを教えた格言」(『日本国語大辞典』)、「時間は大切なものであり、金銭と同等の価値がある」(『デジタル大辞泉』)などとされています。
また日本では、修身の教科書などでフランクリンの成功談とともに掲載されたことにより、「時間を大切に刻苦勉励すれば成功し、富貴が得られる」という、日本独特の解釈も生まれたともいわれています。
しかし実は、フランクリンは今日の辞典的な意味で「Time is Money」と述べたわけではないようです。
今回は、フランクリンの提言した「Time is Money」=「時は金なり」の真意を考察しながら、「時間をお金で買う」のは正解か?を、めぐってみたいと思います。
「時はお金なりということを忘れないでください。一日働けば十シリング稼げる者が、半日出歩いたり、家の中で何もせず怠けていたりしたら、その気晴らしや怠惰に六ペンスしか使わなかったとしても、それだけが支払わされたと計算してはいけません。本当は、その他に五シリングのお金を使った、というよりむしろ捨てたということになるのです」
つまり、遊んだり怠けたりして無駄に過ごした時間の損失はその時間に浪費したお金だけでなく、“無駄に過ごした時間に働けば得られたはずのお金”をも損していること表しています。このことを経済学では、「機会費用」という用語で説明しています。「機会費用」は、「ある選択肢を選ぶことによって犠牲となる価値の最大値」を意味します。
例えば、一日のうち終日勤務であれば7時間労働で7,000円が、半日勤務であれば4時間労働で4,000円の収入が得られる仕事があるとします。Aさんは7時間労働を選択しましたが、Bさんは4時間労働を選択して3時間は休息にあてたとします。
この場合、Bさんの3時間働いていればもらえるはずの3,000円が「機会費用」といえます。Bさんは得られるはずの3時間分の収入3,000円の「機会費用」を支払って(フランクリンの言葉を借りれば「捨てて」)、休息の時間を買ったことになるのです。
さらに、Cさんは4時間労働を選択し、3時間は遊びに行って2,000円を使ったとします。その場合のCさんの「機会費用」は、5,000円になります。
アメリカの経済学者ポール・サミュエルソンは、弁護士事務所における弁護士と秘書の分業の問題にたとえて、「比較優位」の原理を以下のように説明しています。
「両者の間で、いま、弁護士の方が秘書よりも文書をタイプする能力が高かったとしよう。このようなとき、タイプについて弁護士が“絶対優位”を持つといえるが、両者の間における分業のパターンを決めるべきなのは絶対優位の基準ではない。なぜなら、もう一つの分野、つまり法律業務では、秘書に比べた弁護士の能力の優越がよりはっきりしていて、そのパフォーマンス格差を基準にして考える限りは、文書のタイプの分野ではむしろ秘書が“比較優位”を持つからである。比較優位に従って、弁護士が“法律業務”に、秘書が“文書のタイプ”に特化するのが正しい分業パターンである」
たとえ弁護士が法律業務にもタイプ能力にも秘書に対して「絶対優位」をもつ優秀な人物であったとしても、時間は有限です。そのため、弁護士はより多くの利益を上げることのできる法律業務に集中し、タイプを秘書に任せることによって、二人の利益の最大値を目指すことができます。この際、秘書は弁護士と比して、タイプに「比較優位」を持っていることになります。
「比較優位」を最大限に生かしてお金を儲けることによって、関わった人が儲けたお金でさらに「比較優位」の代理人に依頼し自分の時間を増やすことができる、つまり、電車・新幹線・タクシー・飛行機等を利用して移動時間を短縮したり、家事代行サービスを利用して余暇時間を獲得したりできる可能性が増えます。
以上のように、「機会費用」を最大限に考慮しながら「比較優位」にのっとると、「時間をお金で買う」行為は正解ということになります。
東京大学東洋文化研究所教授の中島隆博氏は、「資本主義の精神」を代表する一冊として1905年に出版されたマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(以下『プロ論』)を取り上げています。『プロ論』の中では「世俗内禁欲というプロテスタンティズムの倫理が、かえって資本主義の無際限の欲望を解放した」と述べられており、さらに世俗内禁欲という倫理の具体例として、先述したフランクリンの「時は金なり」を引用して挙げています。
中島氏は「ウェーバーは、世俗内禁欲という倫理とはこういうこと(フランクリンの「時は金なり」)だと言うのです。すごいですよね。気晴らしや怠惰をやっては駄目なのだ、働き続けなさい、と言うのです。時は金なりとは、恐ろしいですね。<中略>“休んではいけない。働き続けることによって、あなたは神に救われるということが定められていると確信できるかもしれない”と言うのです」と述べています。
「欲望」には、食欲に代表される「欲求」のように、生理的な充足はありません。そのため、無限に増大する危険性を秘めています。しかも、「ある選択肢を選ぶことによって犠牲となる価値の最大値」は厳密にはどんな選択をしたところで、絶対の正解を証明することができません。そのため、突き詰めると「時間を買う手段としてのお金儲け」の目的化が起こり、お金のために時間が消費されることも起こり得る、またすでに起こっている場合も多々あるようにも思います。
「時間をお金で買う」ためにより大きな集団で協力しあって利益を上げ、そのうえで個々人が自分にとって真に価値ある時間にお金を使えることは、とても素晴らしいことです。フランクリンやリカードといった先人の金言や優れた理論を援用しながら、多様な人々の時間とお金の関係をさらに進化させることが望まれます。
「時は金なり」という格言は、アメリカの政治家・著述家・科学者であり、“すべてのヤンキーの父”とも称される、ベンジャミン・フランクリンの言葉「Time is Money」の翻訳です。
辞典では、「時間は貴重であり有効なものであるから、むだに費やしてはいけない。時間の尊さを教えた格言」(『日本国語大辞典』)、「時間は大切なものであり、金銭と同等の価値がある」(『デジタル大辞泉』)などとされています。
また日本では、修身の教科書などでフランクリンの成功談とともに掲載されたことにより、「時間を大切に刻苦勉励すれば成功し、富貴が得られる」という、日本独特の解釈も生まれたともいわれています。
しかし実は、フランクリンは今日の辞典的な意味で「Time is Money」と述べたわけではないようです。
今回は、フランクリンの提言した「Time is Money」=「時は金なり」の真意を考察しながら、「時間をお金で買う」のは正解か?を、めぐってみたいと思います。
「時は金なり」の真意は「機会費用」への警句
「Time is Money」は、フランクリンの著書『若き商人への手紙』の中に、以下のように記されています。「時はお金なりということを忘れないでください。一日働けば十シリング稼げる者が、半日出歩いたり、家の中で何もせず怠けていたりしたら、その気晴らしや怠惰に六ペンスしか使わなかったとしても、それだけが支払わされたと計算してはいけません。本当は、その他に五シリングのお金を使った、というよりむしろ捨てたということになるのです」
つまり、遊んだり怠けたりして無駄に過ごした時間の損失はその時間に浪費したお金だけでなく、“無駄に過ごした時間に働けば得られたはずのお金”をも損していること表しています。このことを経済学では、「機会費用」という用語で説明しています。「機会費用」は、「ある選択肢を選ぶことによって犠牲となる価値の最大値」を意味します。
例えば、一日のうち終日勤務であれば7時間労働で7,000円が、半日勤務であれば4時間労働で4,000円の収入が得られる仕事があるとします。Aさんは7時間労働を選択しましたが、Bさんは4時間労働を選択して3時間は休息にあてたとします。
この場合、Bさんの3時間働いていればもらえるはずの3,000円が「機会費用」といえます。Bさんは得られるはずの3時間分の収入3,000円の「機会費用」を支払って(フランクリンの言葉を借りれば「捨てて」)、休息の時間を買ったことになるのです。
さらに、Cさんは4時間労働を選択し、3時間は遊びに行って2,000円を使ったとします。その場合のCさんの「機会費用」は、5,000円になります。
「機会費用」から「比較優位」へ
「機会費用」をさらに進めた理論に、「比較優位」があります。「比較優位」は「ある財・サービスの生産が他の人(あるいは国)より相対的に低い機会費用で可能であること」で、イギリスの経済学者デヴィッド・リカードが提唱した国際分業の原理です。アメリカの経済学者ポール・サミュエルソンは、弁護士事務所における弁護士と秘書の分業の問題にたとえて、「比較優位」の原理を以下のように説明しています。
「両者の間で、いま、弁護士の方が秘書よりも文書をタイプする能力が高かったとしよう。このようなとき、タイプについて弁護士が“絶対優位”を持つといえるが、両者の間における分業のパターンを決めるべきなのは絶対優位の基準ではない。なぜなら、もう一つの分野、つまり法律業務では、秘書に比べた弁護士の能力の優越がよりはっきりしていて、そのパフォーマンス格差を基準にして考える限りは、文書のタイプの分野ではむしろ秘書が“比較優位”を持つからである。比較優位に従って、弁護士が“法律業務”に、秘書が“文書のタイプ”に特化するのが正しい分業パターンである」
たとえ弁護士が法律業務にもタイプ能力にも秘書に対して「絶対優位」をもつ優秀な人物であったとしても、時間は有限です。そのため、弁護士はより多くの利益を上げることのできる法律業務に集中し、タイプを秘書に任せることによって、二人の利益の最大値を目指すことができます。この際、秘書は弁護士と比して、タイプに「比較優位」を持っていることになります。
「比較優位」を最大限に生かしてお金を儲けることによって、関わった人が儲けたお金でさらに「比較優位」の代理人に依頼し自分の時間を増やすことができる、つまり、電車・新幹線・タクシー・飛行機等を利用して移動時間を短縮したり、家事代行サービスを利用して余暇時間を獲得したりできる可能性が増えます。
以上のように、「機会費用」を最大限に考慮しながら「比較優位」にのっとると、「時間をお金で買う」行為は正解ということになります。
「時間を買う手段としてのお金儲け」の目的化
他方、フランクリン的「機会費用」に考えをめぐらせることによって、一つの仮説に至ります。それは、「“機会費用”の損失回避を突き詰めることは、“欲望”のように際限がないのでは?」ということです。東京大学東洋文化研究所教授の中島隆博氏は、「資本主義の精神」を代表する一冊として1905年に出版されたマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(以下『プロ論』)を取り上げています。『プロ論』の中では「世俗内禁欲というプロテスタンティズムの倫理が、かえって資本主義の無際限の欲望を解放した」と述べられており、さらに世俗内禁欲という倫理の具体例として、先述したフランクリンの「時は金なり」を引用して挙げています。
中島氏は「ウェーバーは、世俗内禁欲という倫理とはこういうこと(フランクリンの「時は金なり」)だと言うのです。すごいですよね。気晴らしや怠惰をやっては駄目なのだ、働き続けなさい、と言うのです。時は金なりとは、恐ろしいですね。<中略>“休んではいけない。働き続けることによって、あなたは神に救われるということが定められていると確信できるかもしれない”と言うのです」と述べています。
「欲望」には、食欲に代表される「欲求」のように、生理的な充足はありません。そのため、無限に増大する危険性を秘めています。しかも、「ある選択肢を選ぶことによって犠牲となる価値の最大値」は厳密にはどんな選択をしたところで、絶対の正解を証明することができません。そのため、突き詰めると「時間を買う手段としてのお金儲け」の目的化が起こり、お金のために時間が消費されることも起こり得る、またすでに起こっている場合も多々あるようにも思います。
「時間をお金で買う」ためにより大きな集団で協力しあって利益を上げ、そのうえで個々人が自分にとって真に価値ある時間にお金を使えることは、とても素晴らしいことです。フランクリンやリカードといった先人の金言や優れた理論を援用しながら、多様な人々の時間とお金の関係をさらに進化させることが望まれます。
<参考文献・参考サイト>
・「フランクリン」『日本国語大辞典』(小学館)
・「フランクリン ベンジャミン」『世界文学大事典』(渡辺利雄著、集英社)
・「ときは金なり」『日本国語大辞典』(小学館)
・「時は金なり」『デジタル大辞泉』(小学館)
・「時は金なり」『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
・『若き商人への手紙』(ベンジャミン・フランクリン著、ハイブロー武蔵訳・解説、総合法令出版)
・「機会費用」『イミダス2018』(安田洋祐著、集英社)
・「comparative advantage」『プログレッシブ ビジネス英語辞典』(小学館)
・「比較優位の理論」『イミダス2018』(竹森俊平著、集英社)
・『市場って何だろう』(松井彰彦著、ちくまプリマー新書)
・「フランクリン」『日本国語大辞典』(小学館)
・「フランクリン ベンジャミン」『世界文学大事典』(渡辺利雄著、集英社)
・「ときは金なり」『日本国語大辞典』(小学館)
・「時は金なり」『デジタル大辞泉』(小学館)
・「時は金なり」『故事俗信ことわざ大辞典』(小学館)
・『若き商人への手紙』(ベンジャミン・フランクリン著、ハイブロー武蔵訳・解説、総合法令出版)
・「機会費用」『イミダス2018』(安田洋祐著、集英社)
・「comparative advantage」『プログレッシブ ビジネス英語辞典』(小学館)
・「比較優位の理論」『イミダス2018』(竹森俊平著、集英社)
・『市場って何だろう』(松井彰彦著、ちくまプリマー新書)
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子
毛繕いを代行!?脳の大型化が可能にしたメンタライジング
長谷川眞理子







