テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
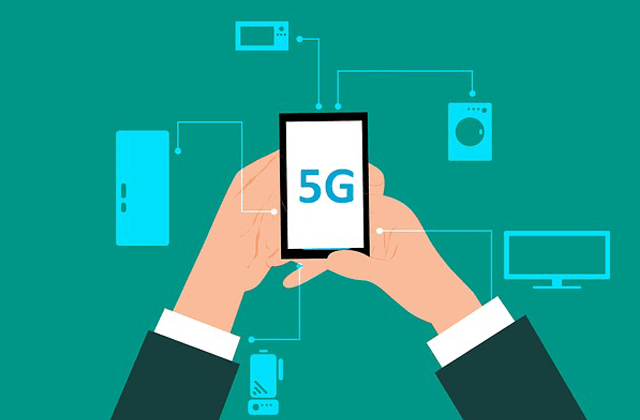
次世代通信「5G」時代到来で、何がどう変わる?
次世代の通信方式「5G」が、日本でもいよいよ2020年から商用開始となります。いったいこれまでとは何がどう違ってくるのでしょうか。
第5世代モバイル推進フォーラム(5GMF)ネットワーク委員会の委員長を務める東京大学大学院情報学環の中尾彰宏副学環長のお話を聞いてみました。
「10万倍でもまだ足りない?」と思われる方も多いでしょうが、2017年にCisco(シスコシステムズ)が発表した「ヴィジュアルネットワーキングインデックス」という予測では、2021年に全世界のモバイルユーザーが55億人になるとはじきだされました。これはモバイル対応のデバイス・接続数でいうと、約120億台(2018年末現在84億台)になるということです。
モバイルトラフィック量は、2017年に比べ7倍に増加し、月間では48EB(エグザバイト)が消費されると言われます。「EB」という単位は、「TB(テラバイト)」の10の6乗倍。標準的なノートPCの記憶容量が1TBですから、その100万台分ということになります。
世界には、グーグルやフェイスブック、アマゾン等が使っている「データセンター」と呼ばれる施設があります。何万台ものサーバーが設置されているのですが、ここに集まるトラフィック量は、2017年から2021年にかけて約3.3倍増えると言われています。これをデータ量に換算すると、年間15.3ZB(ゼッタバイト)という未知の数字を示しています。
「ZB」は「EB」の1000倍。インターネットが誕生して今までに流れたトラフィック総量が1ZBと言われます。世界で流れたトラフィック量の15倍近くが年間にデータセンターに流れる時代を、私たちは迎えようとしているのです。
なぜ日本が遅れているかというと、5Gがどのように使われるのか、言い換えればアプリケーションはどうなるのかを、実証実験によって慎重に検討してきたためです。
たとえば「ホロポーテーション」というアプリケーションをご紹介しましょう。この名前をつけたのはマイクロソフト社。遠隔地にいる相手をカメラにより360度の角度からキャプチャした映像を、通信によって、話者の環境に融合するというものです。話者の生活空間への投影は、ミックストリアリティー(MR)という技術を用いて行われますが、その効果はテレポーテーションかと思うほど。実際にはいない遠くの人が、すぐそばにいるかのような幻想が、5Gによってかなり実現できると期待されています。
5Gの特徴は「高速・大容量」「低遅延(リアルタイム)」「多数接続」の3ポイントと言われます。これらの特徴を十分活用した移動系サービスは、2020年春から本格展開。バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を生かしたコンテンツも、より身近になりそうです。
ソフトバンクが提供したのは不特定多数に対する「5Gプレサービス」という位置付け。これまで、限られた人でなければ実証実験の席に加わることはできなかったのが、今回はブースに立ち寄った人なら誰でもが5Gスマートフォン経由で配信される会場内の映像に接しました。お目当てのステージの混雑具合がモニターで確認できるので、効率よく参加するのに役立った模様です。
また、会場ブースと東京六本木の「テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭りSUMMER STATION」で、同時にVRコンテンツ「FUJI ROCK '19 EXPerience by SoftBank 5G」を提供。苗場と六本木でVR体験中のユーザー同士がアバターと音声で交流することも可能になり、初めてのコミュニケーションに今後の夢が広がりました。
一方NTTドコモは「ラグビーW杯2019日本大会」の開幕試合の映像を5Gで転送する「5Gライブビューイング」を実施。汐留のイベント会場では、400インチの大画面に4K超高画質で映し出される「日本vsロシア戦」の迫力のライブ映像に調布市の東京スタジアム同様の興奮と熱気が伝わりました。
大画面を観戦しつつ、ドコモが用意した5G対応スマホで多視点映像をチェックできる「マルチアングル視聴」を試験サービスできたのも、このイベントのメリット。全国8か所のスタジアム+ライブビューイングの行われた汐留会場で、多くの来場者が次世代のスポーツ観戦を体験しました。
第5世代モバイル推進フォーラム(5GMF)ネットワーク委員会の委員長を務める東京大学大学院情報学環の中尾彰宏副学環長のお話を聞いてみました。
世界が5Gに移行する必然的な流れ
「5G」は「5th Generation」の略で、「第5世代移動通信システム」を指します。最大通信速度がどう変化してきたかを見ると、1980年代の第1世代では10kbps、1秒間に1万bitの情報を配信していました。これが、2010年には1GBとなっています。1G(ギガ)は10の9乗ですから、30年間で最大通信速度は、約10万倍になったということです。「10万倍でもまだ足りない?」と思われる方も多いでしょうが、2017年にCisco(シスコシステムズ)が発表した「ヴィジュアルネットワーキングインデックス」という予測では、2021年に全世界のモバイルユーザーが55億人になるとはじきだされました。これはモバイル対応のデバイス・接続数でいうと、約120億台(2018年末現在84億台)になるということです。
モバイルトラフィック量は、2017年に比べ7倍に増加し、月間では48EB(エグザバイト)が消費されると言われます。「EB」という単位は、「TB(テラバイト)」の10の6乗倍。標準的なノートPCの記憶容量が1TBですから、その100万台分ということになります。
世界には、グーグルやフェイスブック、アマゾン等が使っている「データセンター」と呼ばれる施設があります。何万台ものサーバーが設置されているのですが、ここに集まるトラフィック量は、2017年から2021年にかけて約3.3倍増えると言われています。これをデータ量に換算すると、年間15.3ZB(ゼッタバイト)という未知の数字を示しています。
「ZB」は「EB」の1000倍。インターネットが誕生して今までに流れたトラフィック総量が1ZBと言われます。世界で流れたトラフィック量の15倍近くが年間にデータセンターに流れる時代を、私たちは迎えようとしているのです。
5Gの技術で、何をどうするか
気になる5Gのサービス開始時期ですが、米国では2019年4月から本格展開が始まり、中国でも11月に開始しました。日本は一番最後のサービスインを予定し、2020年東京オリンピック・パラリンピック前の実現のため、政策が進められています。なぜ日本が遅れているかというと、5Gがどのように使われるのか、言い換えればアプリケーションはどうなるのかを、実証実験によって慎重に検討してきたためです。
たとえば「ホロポーテーション」というアプリケーションをご紹介しましょう。この名前をつけたのはマイクロソフト社。遠隔地にいる相手をカメラにより360度の角度からキャプチャした映像を、通信によって、話者の環境に融合するというものです。話者の生活空間への投影は、ミックストリアリティー(MR)という技術を用いて行われますが、その効果はテレポーテーションかと思うほど。実際にはいない遠くの人が、すぐそばにいるかのような幻想が、5Gによってかなり実現できると期待されています。
5Gの特徴は「高速・大容量」「低遅延(リアルタイム)」「多数接続」の3ポイントと言われます。これらの特徴を十分活用した移動系サービスは、2020年春から本格展開。バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を生かしたコンテンツも、より身近になりそうです。
二つの「試験運用」、その評判は?
すでに7月の「FUJI ROCK FESTIVAL '19」ではソフトバンクが、9月の「ラグビーワールドカップ(W杯)2019」ではNTTドコモが、5G回線を試験運用を行いました。ソフトバンクが提供したのは不特定多数に対する「5Gプレサービス」という位置付け。これまで、限られた人でなければ実証実験の席に加わることはできなかったのが、今回はブースに立ち寄った人なら誰でもが5Gスマートフォン経由で配信される会場内の映像に接しました。お目当てのステージの混雑具合がモニターで確認できるので、効率よく参加するのに役立った模様です。
また、会場ブースと東京六本木の「テレビ朝日・六本木ヒルズ夏祭りSUMMER STATION」で、同時にVRコンテンツ「FUJI ROCK '19 EXPerience by SoftBank 5G」を提供。苗場と六本木でVR体験中のユーザー同士がアバターと音声で交流することも可能になり、初めてのコミュニケーションに今後の夢が広がりました。
一方NTTドコモは「ラグビーW杯2019日本大会」の開幕試合の映像を5Gで転送する「5Gライブビューイング」を実施。汐留のイベント会場では、400インチの大画面に4K超高画質で映し出される「日本vsロシア戦」の迫力のライブ映像に調布市の東京スタジアム同様の興奮と熱気が伝わりました。
大画面を観戦しつつ、ドコモが用意した5G対応スマホで多視点映像をチェックできる「マルチアングル視聴」を試験サービスできたのも、このイベントのメリット。全国8か所のスタジアム+ライブビューイングの行われた汐留会場で、多くの来場者が次世代のスポーツ観戦を体験しました。
人気の講義ランキングTOP20










