テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
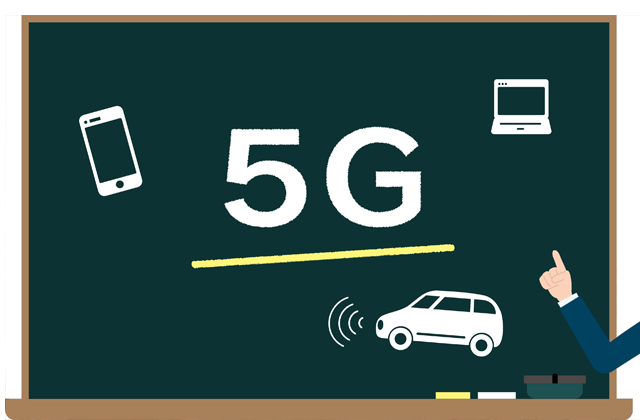
次世代ネットワーク「5G」で何が変わるのか?
2020年はオリンピックイヤーですが、日本において通称「5G」、第5世代移動通信サービスがスタートする年でもあります。世界レベルでは、2019年にサービスインしている国もあることから、日本は少し遅れてのスタートとなります。
ニュースなどでよく耳にする5Gですが、何が変わるのか、何ができるのか、どれだけ理解しているでしょうか。
これまで、10年周期で通信規格がアップデートされ、1980年代に登場した第1世代のアナログ回線から始まり、1990年代にはデジタル回線の2G、2000年代の3G、2010年代の4Gと世代更新とともに通信速度がUPし、ゲームや動画などの大容量データのコンテンツもスマホだけでストレス無く楽しめるようになりました。
第一の特徴は「高速性」です。
現行の通信規格・4Gは、受信時「最大1576Mbps」の速度です。実効値としては、数十~百数十Mbps程度になります。5Gの規格上の最大速度は、「20Gbps=2万Mbps」、桁違いの規格速度といってよいでしょう。すでにサービスを開始している他国での実効値が500Mbps~700Mbpsといった速度が確認されています。この数値だけでも、4Gの数倍の速度であることから、家庭などに引かれている光ファイバー回線と同等のパフォーマンスが移動通信サービスで実現することになります。
第二の特長は「低遅延性」です。
インターネットを介しての処理は、通信速度と距離、インフラの性能も関係して、応答に遅れ=遅延が発生します。固定回線に比べ、携帯電話回線などの移動通信は、処理の関係から遅延が大きく、4G規格で、十数ミリ秒、そうでない場合には百数十ミリ秒の遅延が発生します。5Gでは、この遅延が大幅に短くなります。理論上「1ミリ秒=1000分の1秒」になるため、遅延はかなり感じにくくなるでしょう。遅延があることで実現が難しかった、リアルタイムに近い通信も可能になるはずです。
第三の特長は「多数同時接続性」です。
初詣や花火大会など、多くの人が集まるイベントでは携帯がつながりにくく感じた経験は誰しもあるのではないでしょうか。それは、携帯電話基地局に同時多数接続の限界があるからです。5Gでは、100万件の同時接続が可能になります。これは、4Gの30~40倍のパフォーマンスとなり、これまでの30倍の混雑に耐えられることから、「つながりにくさ」の問題はかなりクリアされることが期待できます。
これまでに実現しているサービスがより充実すること以上に期待されるのは、これまでにないサービスやビジネスが創出される可能性にあります。4Gでは実現できなかった超高精細映像の高速伝送は、VR・AR技術と連動してスポーツやゲームといったコンテンツサービスを大きく変えることでしょう。
現段階で理想や期待で5Gを語ることは簡単ですが、現実的には個人が持てるスマホなどガジェット類や、パフォーマンスを最大化するためのインフラ基盤はまだまだこれからになります。実際には、わかりやすく体感できるエンタメ領域に先行して、目に見えない生活基盤の領域から徐々に革新的なサービスが実現していくことになりそうです。
ニュースなどでよく耳にする5Gですが、何が変わるのか、何ができるのか、どれだけ理解しているでしょうか。
5Gとは
「5G」のGとは「Generation」の頭文字であり、携帯電話などの通信に用いられる5世代目の通信規格になります。これまで、10年周期で通信規格がアップデートされ、1980年代に登場した第1世代のアナログ回線から始まり、1990年代にはデジタル回線の2G、2000年代の3G、2010年代の4Gと世代更新とともに通信速度がUPし、ゲームや動画などの大容量データのコンテンツもスマホだけでストレス無く楽しめるようになりました。
5Gの3つの特長
では、5世代目の通信規格は、速度を含めて、どんな特徴があるのでしょうか?第一の特徴は「高速性」です。
現行の通信規格・4Gは、受信時「最大1576Mbps」の速度です。実効値としては、数十~百数十Mbps程度になります。5Gの規格上の最大速度は、「20Gbps=2万Mbps」、桁違いの規格速度といってよいでしょう。すでにサービスを開始している他国での実効値が500Mbps~700Mbpsといった速度が確認されています。この数値だけでも、4Gの数倍の速度であることから、家庭などに引かれている光ファイバー回線と同等のパフォーマンスが移動通信サービスで実現することになります。
第二の特長は「低遅延性」です。
インターネットを介しての処理は、通信速度と距離、インフラの性能も関係して、応答に遅れ=遅延が発生します。固定回線に比べ、携帯電話回線などの移動通信は、処理の関係から遅延が大きく、4G規格で、十数ミリ秒、そうでない場合には百数十ミリ秒の遅延が発生します。5Gでは、この遅延が大幅に短くなります。理論上「1ミリ秒=1000分の1秒」になるため、遅延はかなり感じにくくなるでしょう。遅延があることで実現が難しかった、リアルタイムに近い通信も可能になるはずです。
第三の特長は「多数同時接続性」です。
初詣や花火大会など、多くの人が集まるイベントでは携帯がつながりにくく感じた経験は誰しもあるのではないでしょうか。それは、携帯電話基地局に同時多数接続の限界があるからです。5Gでは、100万件の同時接続が可能になります。これは、4Gの30~40倍のパフォーマンスとなり、これまでの30倍の混雑に耐えられることから、「つながりにくさ」の問題はかなりクリアされることが期待できます。
5Gの期待と現実
4Gから画期的に性能がアップしている3つの特長から期待されることは、ビッグデータを活用したAI・IoTの領域で、サーバーから即応した情報処理にあります。日常世界に敷設された多様なセンサーからの情報をリアルタイムに近い感覚で分析処理が可能になります。具体的には、光回線に依存しないロケーションでの、画像認証などID管理、自動運転支援、遠隔地医療支援、セキュリティ強化への貢献です。これまでに実現しているサービスがより充実すること以上に期待されるのは、これまでにないサービスやビジネスが創出される可能性にあります。4Gでは実現できなかった超高精細映像の高速伝送は、VR・AR技術と連動してスポーツやゲームといったコンテンツサービスを大きく変えることでしょう。
現段階で理想や期待で5Gを語ることは簡単ですが、現実的には個人が持てるスマホなどガジェット類や、パフォーマンスを最大化するためのインフラ基盤はまだまだこれからになります。実際には、わかりやすく体感できるエンタメ領域に先行して、目に見えない生活基盤の領域から徐々に革新的なサービスが実現していくことになりそうです。
<参考サイト>
・NTTdocomo:5Gでできること
https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/5g/
・KDDI loT:5Gとは?
https://iot.kddi.com/5g/
・NTTdocomo:5Gでできること
https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/5g/
・KDDI loT:5Gとは?
https://iot.kddi.com/5g/
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










