テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
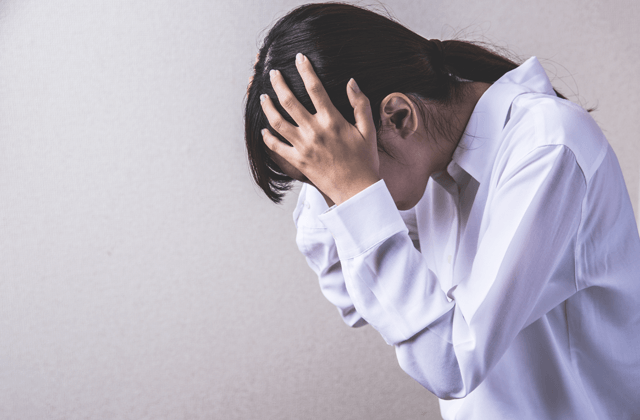
意外に身近な「感覚過敏」その症状とは?
「感覚過敏」とは、脳の感覚刺激の受け取り方がとても敏感で、日常生活に大きな不便や困難さを抱えている状態や症状を指します。
感覚を感じる器官、すなわち外界からの刺激を感受して神経系に伝える器官を「感覚器官」といい、視覚(目)・聴覚(耳)・嗅覚(鼻)・味覚(口)・触覚(皮膚)などがあります。感覚器官を通じて感じた感覚刺激、つまり入力された刺激は電気信号となって脳に送られ認識されます。
しかし、同じ感覚刺激であっても、それをどのように感じるかは脳の感覚刺激の受け取り方によって違い、個人差があります。そのため、人によっては「感覚過敏」という症状となって現れ、困難を来してしまうのです。
【視覚過敏】
視覚、すなわち目からの刺激に敏感な状態・症状を「視覚過敏」といいます。光や明るさに対する過敏(太陽光のまぶしさに耐えられない、蛍光灯のちらつきが気になる、LEDの光が目に刺さるように感じる、カメラのフラッシュが極端に苦手)、色に対する過敏(色の組み合わせで苦手なものがある、人ごみなど動くものの刺激がたくさん目に入ると極端に疲れる)などの特徴があります。
【聴覚過敏】
聴覚、すなわち耳からの刺激に敏感な状態・症状を「聴覚過敏」といいます。特定の音や特定の人の声への過敏、サイレンやアラームといった突然鳴る予測不能な音への過敏、時計の秒針や冷蔵庫の音といった一般的には気にならないような生活音がとても気になるなどの特徴があります。
【嗅覚過敏】
嗅覚、すなわち鼻からの刺激に敏感な状態・症状を「嗅覚過敏」といいます。特定のにおいが極端に苦手で(例えば洗剤、石鹸、花、化粧品、お香、食品、バスなどの乗り物)、そのにおいの発生源には近づくこともできないといった特徴があります。いわゆる臭気ばかりではなく、一般的には良い香りといわれるにおいが苦手な場合もあります。
【味覚過敏】
味覚、すなわち舌や口中からの刺激に敏感な状態・症状を「味覚過敏」といいます。特定の味への過敏だけでなく、味や触感がまじりあうことへの嫌悪といった特徴があります。また、口の中の感覚が過敏で特定の食品を口に入れることもできないなど、口中の過敏や食感への過敏も含まれています。
【触覚過敏】
触覚、すなわち皮膚からの刺激に敏感な状態・症状を「触覚過敏」といいます。服の着心地へのこだわりやセーターや衣類のタグなどの特定の触感への嫌悪、手がべたついたり濡れたりすることなどへの極端な不快感、他者に触られることや握手やハグなどが苦手(ただし、自分から触る場合は大丈夫な場合もある)といった特徴があります。
【その他の感覚過敏】
五感の他にもさまざまな感覚があります。それらの「感覚過敏」のある人には、例えば、平衡感覚(乗り物やエレベータですぐに酔ってしまう)、温度感(温度に敏感で極端に暑がりであったり寒がりであったりする)、痛覚(注射などの痛みに敏感で耐えられない)などといった特徴があります。
また、「感覚過敏」は、その時の体調や気分によっても大きく左右されるという特徴があります。
そのため、同じ感覚刺激であっても、体調が悪かったり、緊張・不安・イライラがあったりするときは「感覚過敏」が出やすくなったり、状態や症状が悪化しやすくなったりしてしまいます。
なお、ある感覚では「感覚過敏」があるものの、違う感覚では「感覚鈍麻」(感覚が鈍い)があるなど、違う状態や症状が併発している場合もあります。
しかし、取り除く・離れる・避けるが難しい場合は、例えば視覚過敏にはサングラス、聴覚過敏には耳栓、嗅覚過敏にはマスクなど、それぞれの「感覚過敏」にあったアイテムの活用が有効です。
また、「感覚過敏」には個人差があると述べてきたように、個々人の特性を自身が理解してそれに応じた対処をしたり、周りの人に理解や協力をしたりしてもらうことも大切です。
ただし、伝わりにくい課題でもあるため、例えば「感覚過敏研究所」の考案した各五感の苦手な状態を表現する「感覚過敏マーク」の活用などもオススメです。さらには、自身の特性の把握や周囲との相互理解への一助として、専門家に相談することも推奨されています。
厳禁は、原則の反対である「無理をする」「無理強いをする」ことです。無理にでも耐えようとしたり無理矢理にでも慣れさせようとしたりすることは解決に繋がらないだけでなく、さらに状態や症状を悪化させるリスクも高くなり非常に危険です。
誰しも得意や苦手があります。また感じ方や表現方法も人それぞれであるからこそ、豊かな恵みをもたらす多様性の源泉となっているのです。自身の特性を知り相手の特性を思いやる。一緒に暮らす環境について他者の立場になって考察をめぐらしてみる。よりよい世界や関係性のために、感覚を活用してみてください。
感覚を感じる器官、すなわち外界からの刺激を感受して神経系に伝える器官を「感覚器官」といい、視覚(目)・聴覚(耳)・嗅覚(鼻)・味覚(口)・触覚(皮膚)などがあります。感覚器官を通じて感じた感覚刺激、つまり入力された刺激は電気信号となって脳に送られ認識されます。
しかし、同じ感覚刺激であっても、それをどのように感じるかは脳の感覚刺激の受け取り方によって違い、個人差があります。そのため、人によっては「感覚過敏」という症状となって現れ、困難を来してしまうのです。
「感覚過敏」にはどんな種類があるの?
「感覚過敏」には、具体的にどんな症状があるのでしょうか。感覚器官別に分類すると、以下のようになります。【視覚過敏】
視覚、すなわち目からの刺激に敏感な状態・症状を「視覚過敏」といいます。光や明るさに対する過敏(太陽光のまぶしさに耐えられない、蛍光灯のちらつきが気になる、LEDの光が目に刺さるように感じる、カメラのフラッシュが極端に苦手)、色に対する過敏(色の組み合わせで苦手なものがある、人ごみなど動くものの刺激がたくさん目に入ると極端に疲れる)などの特徴があります。
【聴覚過敏】
聴覚、すなわち耳からの刺激に敏感な状態・症状を「聴覚過敏」といいます。特定の音や特定の人の声への過敏、サイレンやアラームといった突然鳴る予測不能な音への過敏、時計の秒針や冷蔵庫の音といった一般的には気にならないような生活音がとても気になるなどの特徴があります。
【嗅覚過敏】
嗅覚、すなわち鼻からの刺激に敏感な状態・症状を「嗅覚過敏」といいます。特定のにおいが極端に苦手で(例えば洗剤、石鹸、花、化粧品、お香、食品、バスなどの乗り物)、そのにおいの発生源には近づくこともできないといった特徴があります。いわゆる臭気ばかりではなく、一般的には良い香りといわれるにおいが苦手な場合もあります。
【味覚過敏】
味覚、すなわち舌や口中からの刺激に敏感な状態・症状を「味覚過敏」といいます。特定の味への過敏だけでなく、味や触感がまじりあうことへの嫌悪といった特徴があります。また、口の中の感覚が過敏で特定の食品を口に入れることもできないなど、口中の過敏や食感への過敏も含まれています。
【触覚過敏】
触覚、すなわち皮膚からの刺激に敏感な状態・症状を「触覚過敏」といいます。服の着心地へのこだわりやセーターや衣類のタグなどの特定の触感への嫌悪、手がべたついたり濡れたりすることなどへの極端な不快感、他者に触られることや握手やハグなどが苦手(ただし、自分から触る場合は大丈夫な場合もある)といった特徴があります。
【その他の感覚過敏】
五感の他にもさまざまな感覚があります。それらの「感覚過敏」のある人には、例えば、平衡感覚(乗り物やエレベータですぐに酔ってしまう)、温度感(温度に敏感で極端に暑がりであったり寒がりであったりする)、痛覚(注射などの痛みに敏感で耐えられない)などといった特徴があります。
「感覚過敏」の原因はわかっているの?
「感覚過敏」は研究段階にありますが、原因としては、1)脳の機能に関する、2)感覚器に関する、3)不安・ストレスなどの心因性・病気の前兆や原因不明――の大きくに3つに分類できるとされています。また、「感覚過敏」は、その時の体調や気分によっても大きく左右されるという特徴があります。
そのため、同じ感覚刺激であっても、体調が悪かったり、緊張・不安・イライラがあったりするときは「感覚過敏」が出やすくなったり、状態や症状が悪化しやすくなったりしてしまいます。
なお、ある感覚では「感覚過敏」があるものの、違う感覚では「感覚鈍麻」(感覚が鈍い)があるなど、違う状態や症状が併発している場合もあります。
「感覚過敏」の対処法はあるの?
「感覚過敏」の対応の原則は、「無理をしない」「無理強いをしない」です。まずは感覚刺激となる原因を取り除く・離れる・避けることが肝要です。しかし、取り除く・離れる・避けるが難しい場合は、例えば視覚過敏にはサングラス、聴覚過敏には耳栓、嗅覚過敏にはマスクなど、それぞれの「感覚過敏」にあったアイテムの活用が有効です。
また、「感覚過敏」には個人差があると述べてきたように、個々人の特性を自身が理解してそれに応じた対処をしたり、周りの人に理解や協力をしたりしてもらうことも大切です。
ただし、伝わりにくい課題でもあるため、例えば「感覚過敏研究所」の考案した各五感の苦手な状態を表現する「感覚過敏マーク」の活用などもオススメです。さらには、自身の特性の把握や周囲との相互理解への一助として、専門家に相談することも推奨されています。
厳禁は、原則の反対である「無理をする」「無理強いをする」ことです。無理にでも耐えようとしたり無理矢理にでも慣れさせようとしたりすることは解決に繋がらないだけでなく、さらに状態や症状を悪化させるリスクも高くなり非常に危険です。
誰しも得意や苦手があります。また感じ方や表現方法も人それぞれであるからこそ、豊かな恵みをもたらす多様性の源泉となっているのです。自身の特性を知り相手の特性を思いやる。一緒に暮らす環境について他者の立場になって考察をめぐらしてみる。よりよい世界や関係性のために、感覚を活用してみてください。
<参考文献・参考サイト>
・『発達凸凹なボクの世界』(プルスアルハ著、ゆまに書房)
・「感覚器官」『デジタル大辞泉』(小学館)
・感覚過敏とは | 感覚過敏研究所
https://kabin.life/kabin
・感覚過敏とは? どんな症状があるのか、日常生活や仕事をする際にできる対処法について紹介します
https://snabi.jp/article/236
・発達障害プロジェクト - NHK
https://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/
・【図表でわかる!】発達障害 × 感覚過敏・鈍麻 | 「我慢が足りない」わけじゃない!7つの感覚に分けて解説
https://www.teensmoon.com/chart/%E3%80%90%E5%9B%B3%E8%A1%A8%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%80%91%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3-x-%E6%84%9F%E8%A6%9A%E9%81%8E%E6%95%8F%E3%83%BB%E9%88%8D%E9%BA%BB/
・中学生が「感覚過敏マーク」を考案。感覚過敏がある人が暮らしやすい社会を目指す。【感覚過敏研究所】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000046913.html
・『発達凸凹なボクの世界』(プルスアルハ著、ゆまに書房)
・「感覚器官」『デジタル大辞泉』(小学館)
・感覚過敏とは | 感覚過敏研究所
https://kabin.life/kabin
・感覚過敏とは? どんな症状があるのか、日常生活や仕事をする際にできる対処法について紹介します
https://snabi.jp/article/236
・発達障害プロジェクト - NHK
https://www1.nhk.or.jp/asaichi/hattatsu/
・【図表でわかる!】発達障害 × 感覚過敏・鈍麻 | 「我慢が足りない」わけじゃない!7つの感覚に分けて解説
https://www.teensmoon.com/chart/%E3%80%90%E5%9B%B3%E8%A1%A8%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%80%91%E7%99%BA%E9%81%94%E9%9A%9C%E5%AE%B3-x-%E6%84%9F%E8%A6%9A%E9%81%8E%E6%95%8F%E3%83%BB%E9%88%8D%E9%BA%BB/
・中学生が「感覚過敏マーク」を考案。感覚過敏がある人が暮らしやすい社会を目指す。【感覚過敏研究所】
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000046913.html
人気の講義ランキングTOP20
ラマルクの進化論…使えば器官が発達し、それが子に伝わる
長谷川眞理子
島田晴雄先生の体験談から浮かびあがるアメリカと日本
テンミニッツ・アカデミー編集部










