テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
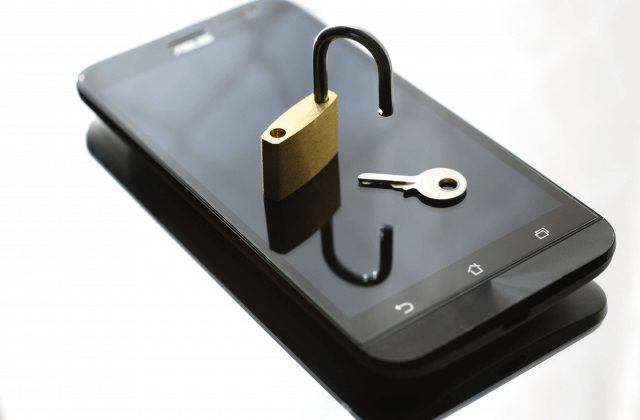
今どきの若者の「プライバシー」感覚とは?
インターネットが日本でも身近なものになり始めたのは90年代半ば、その技術・利便性は日進月歩で進化してきていました。現在では生まれた時から高速で繋がるインターネット環境に見知らぬ他人とも繋がることのできるSNSのあったいわゆるZ世代も二十歳を迎えています。
彼らの世代はかねてからSNSの危険な側面を熟知していてプライバシー保護意識が高いといわれてきましたが、近年それを覆す調査結果も出てきています。今回はZ世代の若者たちのプライバシー意識についてリポートします。
そんなTwitterを利用している高校生たちの5割が実名でアカウント登録し、かつ投稿の公開範囲を「全体」に設定しているのがその内の4割という調査結果が出ています。特に発言に注意を払っている様子もなく、学校名から行動範囲、今日はサボるというようなプライベートなことまで赤裸々にツイートしている子たちもいるようです。SNSにアップされた女性の自撮り写真の瞳に映り込んでいる建物から住居を特定されたストーキング事件も起こる昨今、あまりに無防備ではと心配になってきます。
彼らが実名でSNSのアカウントを作った理由は、「友達と繋がりやすい」「見つけてもらいやすい」からだったそうです。彼らはフルネームは危ない、個人を特定しやすい漢字は避けてローマ字で名前だけの登録が暗黙の了解と、個人情報流出に対しての用心はしていました。しかしお調子者がフルネームのアカウントでツイートを「全体公開」にしていたところ、先生に見つかり大目玉を食らったと知れ渡り、一斉に「一部にしか公開しない」ようロックをかけたそうです。
彼の言葉を借りるならば、「どういうやつが集まるコミュニティーに所属しているか」で、傾向も違ったということでした。フォロワー、イイね!の数がステータスになっているグループもあれば、普通に調べ物ツールとして以上の使い方をしない子たちも居たそうです。Z世代の子たちは親世代よりもずっと新しいツールを使いこなし楽しさを見出せるぶん、プレッシャーを受けているとも窺えます。
プライバシーが筒抜けなのは気にならないのか、やはり実際に使っている子に訊いてみたところ、子供の頃から登下校の見守りアプリが入れられていた、それを親とではなく友人間で使っているだけだから抵抗がないということでした。一緒に登下校や遊びに行くのに大変便利だそうです。ただ、プライバシーを気にする感覚には個人差があり、そこまで親しくない同級生に登録してよといわれると断るのに苦労するそうです。最終的には距離感についてのマナー感覚が問題になってくるといったところでしょうか。
同様に若者たちに使われている最新のコミュニケーションツールも当たり前になっていくのかもしれません。よく用いられる例えですが、ナイフは本来の目的どおりに使えば肉を切り分けたり果物を剥いたりすることができます。しかし、人を傷つけてしまえば凶器です。スマホのアプリも悪用されれば人を傷つけるものになります。新旧問わず、すべてのツールは取り扱いを間違うと危険であると親子で話し合うことが肝要になりそうです。
彼らの世代はかねてからSNSの危険な側面を熟知していてプライバシー保護意識が高いといわれてきましたが、近年それを覆す調査結果も出てきています。今回はZ世代の若者たちのプライバシー意識についてリポートします。
Z世代のTwitterアカウントは実名が主流?
ここ数年、SNS界隈の中ではTwitterが良くも悪くも注目されてきました。最近ではYouTubeに散見していますが、バイト先やコンビニで悪ふざけしている姿を投稿して炎上騒ぎを起こし、投稿者の本名から住所、学校、勤務先まで晒される騒動は何度となく起きています。また、匿名で投稿ができることから個人への誹謗中傷の温床となり、追い詰められた人が自死してしまう痛ましい事件が起きているのはご存知の通りです。そんなTwitterを利用している高校生たちの5割が実名でアカウント登録し、かつ投稿の公開範囲を「全体」に設定しているのがその内の4割という調査結果が出ています。特に発言に注意を払っている様子もなく、学校名から行動範囲、今日はサボるというようなプライベートなことまで赤裸々にツイートしている子たちもいるようです。SNSにアップされた女性の自撮り写真の瞳に映り込んでいる建物から住居を特定されたストーキング事件も起こる昨今、あまりに無防備ではと心配になってきます。
若者がSNSを実名でやるメリットとは?
基本的に従来のSNSはハンドルネームをつけてやるのが一般的でした。Facebookのように実名でやるところもありますが、そこは本名から経歴まで登録を義務付けることでお互いの言動に節度を持たせる役割もありました。また、芸能人やスポーツ選手、ビジネスマン、クリエイターなどは、名前を明かすことでファンとの交流ができたり、信頼性を高め広報活動をしたりできるというメリットがありますが、若者が実名でやる理由はなんでしょうか。実際にTwitterを実名アカウントでやっていたことのある二十歳の学生に訊いてみました。彼らが実名でSNSのアカウントを作った理由は、「友達と繋がりやすい」「見つけてもらいやすい」からだったそうです。彼らはフルネームは危ない、個人を特定しやすい漢字は避けてローマ字で名前だけの登録が暗黙の了解と、個人情報流出に対しての用心はしていました。しかしお調子者がフルネームのアカウントでツイートを「全体公開」にしていたところ、先生に見つかり大目玉を食らったと知れ渡り、一斉に「一部にしか公開しない」ようロックをかけたそうです。
彼の言葉を借りるならば、「どういうやつが集まるコミュニティーに所属しているか」で、傾向も違ったということでした。フォロワー、イイね!の数がステータスになっているグループもあれば、普通に調べ物ツールとして以上の使い方をしない子たちも居たそうです。Z世代の子たちは親世代よりもずっと新しいツールを使いこなし楽しさを見出せるぶん、プレッシャーを受けているとも窺えます。
あなたと私の位置情報共有アプリ
SNSとは別に、近年ティーンエイジャーに利用されているものにZenlyをはじめとした位置情報共有アプリがあります。アプリを登録しているメンバーが現在どこにいるか、どのような経路で移動しているか、居場所の情報を共有するのを目的としたものです。誰と誰がこの店で1時間お茶をしている……そんなことまでわかるようになっています。プライバシーが筒抜けなのは気にならないのか、やはり実際に使っている子に訊いてみたところ、子供の頃から登下校の見守りアプリが入れられていた、それを親とではなく友人間で使っているだけだから抵抗がないということでした。一緒に登下校や遊びに行くのに大変便利だそうです。ただ、プライバシーを気にする感覚には個人差があり、そこまで親しくない同級生に登録してよといわれると断るのに苦労するそうです。最終的には距離感についてのマナー感覚が問題になってくるといったところでしょうか。
望もうと望まなかろうとやってくる新しいツールに対して
携帯電話を持っているのが当たり前になった頃、首に鈴をかけられるみたいで嫌だと持たないようにしている方も一定数居ました。しかし、普及率が進むにつれて携帯を持っているのを前提とした社会になり、今では持っていないと非常に不便になっています。同様に若者たちに使われている最新のコミュニケーションツールも当たり前になっていくのかもしれません。よく用いられる例えですが、ナイフは本来の目的どおりに使えば肉を切り分けたり果物を剥いたりすることができます。しかし、人を傷つけてしまえば凶器です。スマホのアプリも悪用されれば人を傷つけるものになります。新旧問わず、すべてのツールは取り扱いを間違うと危険であると親子で話し合うことが肝要になりそうです。
<参考サイト>
・『高校生Twitter利用者の52.7%は「実名利用」、実名利用している高校生のうち41.1%は「すべての人」に情報を公開|MMD研究所
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1703.html
・『アプリ「Zenly」で居場所も移動経路も公開 今どき10代のプライバシー感』朝日新聞GLOBE
https://globe.asahi.com/article/13520464
・『デジタルストーカーの仰天手口 SNS写真の瞳に映る風景から自宅特定、ピース写真の指紋から不正ログイン』東京新聞TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/19171
・『高校生Twitter利用者の52.7%は「実名利用」、実名利用している高校生のうち41.1%は「すべての人」に情報を公開|MMD研究所
https://mmdlabo.jp/investigation/detail_1703.html
・『アプリ「Zenly」で居場所も移動経路も公開 今どき10代のプライバシー感』朝日新聞GLOBE
https://globe.asahi.com/article/13520464
・『デジタルストーカーの仰天手口 SNS写真の瞳に映る風景から自宅特定、ピース写真の指紋から不正ログイン』東京新聞TOKYO Web
https://www.tokyo-np.co.jp/article/19171
人気の講義ランキングTOP20
ソニー流「人材の活かし方」「多角化経営の秘密」を学ぶ
テンミニッツ・アカデミー編集部










