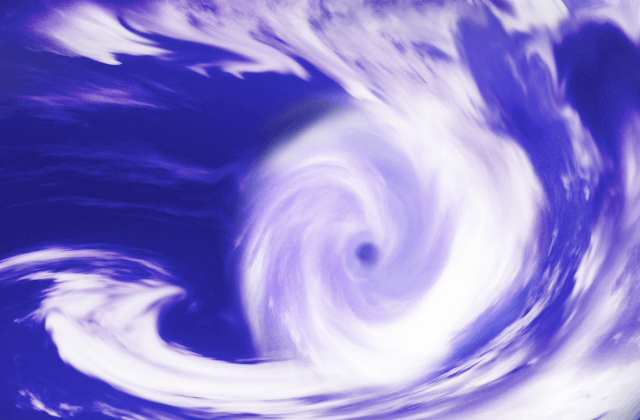
台風は毎年いくつ発生しているのか?
「台風」とは、「太平洋西部(赤道より北で東経180度より西の領域)や南シナ海に現れる熱帯低気圧のうち、最大風速(10分間平均)が17.2m/s以上になったもの」を指します。
そして、気象庁による《台風の強さ》と《台風の大きさ》の階級区分は、以下のようになっています。
《台風の強さ》
階級:最大風速
強い:33m/s(64ノット)以上~44m/s(85ノット)未満
非常に強い:44m/s(85ノット)以上~54m/s(105ノット)未満
猛烈な:54m/s(105ノット)以上
《台風の大きさ》
階級:風速15m/s以上の半径
大型(大きい):500km以上~800km未満
超大型(非常に大きい):800km以上
【台風の年間発生数(2010年代)】
年:年間発生数/発生月・月間発生数(最多発生月・最多月間発生数)
2010年:14
3月・1,7月・2,8月・5,9月・4,10月・2(8月・5)
2011年:21
5月・2,6月・3,7月・4,8月・3,9月・7,10月・1,12月・1(9月・7)
2012年:25
3月・1,5月・1,6月・4,7月・4,8月・5,9月・3,10月・5,11月・1,12月・1(8月10月・5)
2013年:31
1月・1,2月・1,6月・4,7月・3,8月・6,9月・7,10月・7,11月・2(9月10月・7)
2014年:23
1月・2,2月・1,4月・2,6月・2,7月・5,8月・1,9月・5,10月・2,11月・1,12月・2(7月9月・5)
2015年:27
1月・1,2月・1,3月・2,4月・1,5月・2,6月・2,7月・3,8月・4,9月・5,10月・4,11月・1,12月・1(9月・5)
2016年:26
7月・4,8月・7,9月・7,10月・4,11月・3,12月・1(8月9月・7)
2017年:27
4月・1,6月・1,7月・8,8月・5,9月・4,10月・3,11月・3,12月・2(7月・8)
2018年:29
1月・1,2月・1,3月・1,6月・4,7月・5,8月・9,9月・4,10月・1,11月・3(9月・9)
2019年:29
1月・1,2月・1,6月・1,7月・4,8月・5,9月・6,10月・4,11月・6,12月・1(9月11月・6)
秋の季語にもなっている台風ですが、データをみていくと7月~11月の夏から晩秋にかけて、特に9月に多く発生していることがわかります。とはいえ、1月から12月までどの月でも発生する可能性があることもみえてきます。
なお、統計が開始された1951(昭和26)年から最新統計確定年である2019(令和元)年の統計期間中において、最も発生数が多い年は1967(昭和42)年の39、最も発生数が少ない年は2010(平成22)年の14、となっています。
「台風番号」や「台風名」を付けている機関は、気象庁です。
まず「台風番号」の付け方は、「毎年1月1日以後に最も早く発生した台風を“第1号”とし、以後台風の発生順に番号を付ける」となっています。なお、一度発生した台風が衰えて熱帯低気圧になった後で再び発達して台風となった場合は、同じ番号を付けます。
ちなみに、気象庁では国内の一般向けの情報や刊行物において、「平成12年台風第1号」のように「元号・年数・台風番号」を並べて表記します。ただし、和暦ではなく西暦を用いる場合や年の表記を省略する場合もあります。
次に「台風名」の付け方です。以前台風にはアメリカが英語の人名を付けていましたが、2000(平成12)年からは、日本を含むアジアを中心に14の国と地域が加盟する「台風委員会」が提案した名前を割り当てています。
「台風番号」だけではなく「台風名」をつけるメリットには、複数の台風があってもより多くの人に情報を間違いなく伝えることができ、過去に大きな被害を受けた台風を思い出すときの助けにもなる、などが挙げられます。なお、140個のアジア名のうち、日本からは「Koinu(コイヌ)」「Yagi(ヤギ)」「Kammuri(カンムリ)」など、星座名に由来する10個の名前が提案されています。
その他にも、特に災害の大きかった台風については、被災地名や上陸地点名などを付した特別の名前が付けられる場合もあります。
例えば、昭和以降の台風の中で最大の被害をもたらしたといわれる1959(昭和34)年9月に発生した台風第15号こと「伊勢湾台風」や、1945(昭和20)年9月に九州から関東の各地に甚大な風水害をもたらした台風第16号こと「枕崎台風」、1934(昭和9)年9月に京阪神地方を襲った猛烈な台風「室戸台風」などが有名です。
それぞれ最大風速の基準に違いはありますが、実は“熱帯低気圧が存在する地域”によって、呼び方が違ってきます。
まず台風は、東経180度より西の北西太平洋および南シナ海で発生した際に使用される“日本の分類”です。
他方、「ハリケーン」は北大西洋・カリブ海・メキシコ湾および西経180度より東の北太平洋東部、「サイクロン」はベンガル湾・北インド洋および南半球――に存在する熱帯低気圧のうち最大風速が毎秒32.7メートル以上のもの、を指しています。
いかがでしたでしょうか。毎年多数の台風が発生し、また件数や被害も大きくなりやすい秋期が巡ってきています。過去の資料に学びつつ、未来への備えとしてください。
そして、気象庁による《台風の強さ》と《台風の大きさ》の階級区分は、以下のようになっています。
《台風の強さ》
階級:最大風速
強い:33m/s(64ノット)以上~44m/s(85ノット)未満
非常に強い:44m/s(85ノット)以上~54m/s(105ノット)未満
猛烈な:54m/s(105ノット)以上
《台風の大きさ》
階級:風速15m/s以上の半径
大型(大きい):500km以上~800km未満
超大型(非常に大きい):800km以上
台風の年間発生数(2010年代)
では早速、近年の台風の年間発生件数をみてみましょう。【台風の年間発生数(2010年代)】は、以下のとおりとなっています。【台風の年間発生数(2010年代)】
年:年間発生数/発生月・月間発生数(最多発生月・最多月間発生数)
2010年:14
3月・1,7月・2,8月・5,9月・4,10月・2(8月・5)
2011年:21
5月・2,6月・3,7月・4,8月・3,9月・7,10月・1,12月・1(9月・7)
2012年:25
3月・1,5月・1,6月・4,7月・4,8月・5,9月・3,10月・5,11月・1,12月・1(8月10月・5)
2013年:31
1月・1,2月・1,6月・4,7月・3,8月・6,9月・7,10月・7,11月・2(9月10月・7)
2014年:23
1月・2,2月・1,4月・2,6月・2,7月・5,8月・1,9月・5,10月・2,11月・1,12月・2(7月9月・5)
2015年:27
1月・1,2月・1,3月・2,4月・1,5月・2,6月・2,7月・3,8月・4,9月・5,10月・4,11月・1,12月・1(9月・5)
2016年:26
7月・4,8月・7,9月・7,10月・4,11月・3,12月・1(8月9月・7)
2017年:27
4月・1,6月・1,7月・8,8月・5,9月・4,10月・3,11月・3,12月・2(7月・8)
2018年:29
1月・1,2月・1,3月・1,6月・4,7月・5,8月・9,9月・4,10月・1,11月・3(9月・9)
2019年:29
1月・1,2月・1,6月・1,7月・4,8月・5,9月・6,10月・4,11月・6,12月・1(9月11月・6)
秋の季語にもなっている台風ですが、データをみていくと7月~11月の夏から晩秋にかけて、特に9月に多く発生していることがわかります。とはいえ、1月から12月までどの月でも発生する可能性があることもみえてきます。
なお、統計が開始された1951(昭和26)年から最新統計確定年である2019(令和元)年の統計期間中において、最も発生数が多い年は1967(昭和42)年の39、最も発生数が少ない年は2010(平成22)年の14、となっています。
台風の呼び方
ところで、天気予報やニュースなどでもよく耳にする台風の呼び方である「台風番号」や「台風名」は、どんな機関がどのように付けているのかをご存知でしょうか。「台風番号」や「台風名」を付けている機関は、気象庁です。
まず「台風番号」の付け方は、「毎年1月1日以後に最も早く発生した台風を“第1号”とし、以後台風の発生順に番号を付ける」となっています。なお、一度発生した台風が衰えて熱帯低気圧になった後で再び発達して台風となった場合は、同じ番号を付けます。
ちなみに、気象庁では国内の一般向けの情報や刊行物において、「平成12年台風第1号」のように「元号・年数・台風番号」を並べて表記します。ただし、和暦ではなく西暦を用いる場合や年の表記を省略する場合もあります。
次に「台風名」の付け方です。以前台風にはアメリカが英語の人名を付けていましたが、2000(平成12)年からは、日本を含むアジアを中心に14の国と地域が加盟する「台風委員会」が提案した名前を割り当てています。
「台風番号」だけではなく「台風名」をつけるメリットには、複数の台風があってもより多くの人に情報を間違いなく伝えることができ、過去に大きな被害を受けた台風を思い出すときの助けにもなる、などが挙げられます。なお、140個のアジア名のうち、日本からは「Koinu(コイヌ)」「Yagi(ヤギ)」「Kammuri(カンムリ)」など、星座名に由来する10個の名前が提案されています。
その他にも、特に災害の大きかった台風については、被災地名や上陸地点名などを付した特別の名前が付けられる場合もあります。
例えば、昭和以降の台風の中で最大の被害をもたらしたといわれる1959(昭和34)年9月に発生した台風第15号こと「伊勢湾台風」や、1945(昭和20)年9月に九州から関東の各地に甚大な風水害をもたらした台風第16号こと「枕崎台風」、1934(昭和9)年9月に京阪神地方を襲った猛烈な台風「室戸台風」などが有名です。
台風“以外”の名付け方
さらに世界にも目をむけてみると、台風以外にも「ハリケーン」「サイクロン」などの名称がありますが、台風との違いをご存知でしょうか。それぞれ最大風速の基準に違いはありますが、実は“熱帯低気圧が存在する地域”によって、呼び方が違ってきます。
まず台風は、東経180度より西の北西太平洋および南シナ海で発生した際に使用される“日本の分類”です。
他方、「ハリケーン」は北大西洋・カリブ海・メキシコ湾および西経180度より東の北太平洋東部、「サイクロン」はベンガル湾・北インド洋および南半球――に存在する熱帯低気圧のうち最大風速が毎秒32.7メートル以上のもの、を指しています。
いかがでしたでしょうか。毎年多数の台風が発生し、また件数や被害も大きくなりやすい秋期が巡ってきています。過去の資料に学びつつ、未来への備えとしてください。
<参考文献・参考サイト>
・気象庁|台風について
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/index.html
・気象庁|過去の台風資料
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/index.html
・「台風」『世界大百科事典』(山岬正紀著、平凡社)
・「台風」『デジタル大辞泉』(小学館)
・「台風名/ハリケーン名」[気象]『イミダス 2018』(住明正・青木孝著、集英社)
・台風〇号、号数や名称はどうやって決まる?台風に名前を付ける理由とは
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/30/typhoon-name_a_23546740/
・「伊勢湾台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「枕崎台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「室戸台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「室戸台風」『世界大百科事典』(中島暢太郎、平凡社)
・デジタル台風:過去の台風災害・被害
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/disaster/help/past.html.ja
・「熱帯低気圧」」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・台風、ハリケーン、タイフーン、サイクロンの違いとは
https://hp.otenki.com/2270/
・「ハリケーン」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「サイクロン」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「熱帯低気圧【2019】」『現代用語の基礎知識』(自由国民社)
・気象庁|台風について
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/typhoon/index.html
・気象庁|過去の台風資料
https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/typhoon/index.html
・「台風」『世界大百科事典』(山岬正紀著、平凡社)
・「台風」『デジタル大辞泉』(小学館)
・「台風名/ハリケーン名」[気象]『イミダス 2018』(住明正・青木孝著、集英社)
・台風〇号、号数や名称はどうやって決まる?台風に名前を付ける理由とは
https://www.huffingtonpost.jp/2018/09/30/typhoon-name_a_23546740/
・「伊勢湾台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「枕崎台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「室戸台風」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「室戸台風」『世界大百科事典』(中島暢太郎、平凡社)
・デジタル台風:過去の台風災害・被害
http://agora.ex.nii.ac.jp/digital-typhoon/disaster/help/past.html.ja
・「熱帯低気圧」」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・台風、ハリケーン、タイフーン、サイクロンの違いとは
https://hp.otenki.com/2270/
・「ハリケーン」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「サイクロン」『日本大百科全書』(饒村曜著、小学館)
・「熱帯低気圧【2019】」『現代用語の基礎知識』(自由国民社)
人気の講義ランキングTOP20







