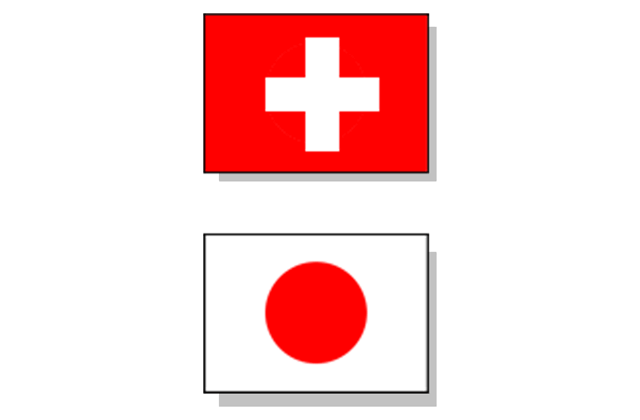
「永世中立国」は日本と何が違うのか?
永世中立国とは、他国に対して自国からは戦争を始めず、また他国間のどのような戦争にも加わらず中立を維持することを条約によって義務づけられている国です。
2021年1月現在、永世中立の地位を維持する国は、スイス(1815年以来)、オーストリア(1955年以来)、トルクメニスタン(1995年以来)の3カ国のみです。
今回は、3カ国の中で最も歴史が古く、また一般的にも永世中立国の代名詞ともいえるスイスを取り上げ、永世中立国の実態ならびに、日本との違いを考察してみたいと思います。
ヨーロッパのハブ的な存在であるスイスは重要な国である一方、建国以前から現代に至るまで、ゲルマン民族による征服、神聖ローマ帝国の支配、封建制度下によるハプスブルク家等有力諸侯による統治など、歴史に翻弄され苦難の歴史を重ねてきた国でもあります。
そのように、ある意味において地政学的な命運を担わざる得ないスイスが、中立国を経て永世中立国となる過程には、二度の大きな転換点がありました。
最初の転換点は、1618~48年の間ドイツを中心にヨーロッパ諸国を戦渦に巻き込み“最後で最大の宗教戦争”といわれる“三十年戦争”の末期に訪れます。1640年に国境保全のため国境防衛軍を創設したスイスは、さらに1647年にスイス各州で防衛軍事協定を結びます。この協定は事実上のスイス「武装中立」の出発点となりました。そして、1648年に三十年戦争を終結させた“ウェストファリア条約”の締結において、スイスは国際法的に独立を承認されることとなります。
しかしながらその裏では、特に17~18世紀のヨーロッパの戦乱期、各国の軍隊にスイス傭兵が働いていました。つまり、スイスは他国に血を売ることで、自国の中立を確保する歴史が続いていたともいえます。
ところが、1789年に起こったフランス革命の影響を受けスイス革命が起こり、さらにスイス革命を軍事的に援助したナポレオンによって、スイスにも中央集権的な政府が樹立されます。しかし、民族も宗教も文化も州によって大きく異なり、州自治を尊重していたスイスの伝統にあわず、ただちに混乱をきたします。ですが、結局はナポレオンの敗退と退位によって、二度目の転換点を迎えることとなります。
二度目の転換点は、1814~15年にナポレオン退位後のヨーロッパの政治的再編のために開かれた“ウィーン会議”によって、スイスは領土一部を与えられたうえで「武装永世中立国」となることが国際法的に承認されます。今日に続く永世中立国としてのスイスは、このときに誕生したといえます。
スイスの例からは、自国と他国(主に周辺地域国)の社会安定のため、政治的緩衝国家としての特性を生かしてどの国とも同盟関係を結ばない永世中立国であることが、かえって自国の安定を守りつつ他国の安定にも寄与するという、内外からの政学的戦略がうかがえます。
さて、冒頭でも述べたように、永世中立国は自衛の他は戦争をする権利を持ちません。そのうえ、他国と同盟を組むことなく自国を維持するためには、結果として「武装」が必須となることは否めません。
具体的には、永世中立国であるスイス・オーストリア・トルクメニスタンも自国の軍隊を所有し、軍事力を保持しています。特にスイスは“国民皆兵”といわれるほど軍事意識は高く、自国を守るために軍事力を活用しています。さらに、周辺国からしても、永世中立国は“他国にとられたくない国”ともいえます。そのため、例えばスイスが永世中立国となる際は「武装」が必須であり、ヨーロッパ各国、特に周辺国からの条件ですらありました。
ここに至ってようやく、永世中立国と戦争放棄国である日本の違いが明確なります。それは「武装」と「非武装」、つまりは「戦力の保持」と「戦力の不保持」にあります。日本は憲法においては「非武装国家」であり、また各国、特に周辺国からは「非武装」を要請されている国であるといえます(ただし、自衛権は戦争放棄国にも保証されていると考えられています)。
いかがでしたでしょうか。永世中立国の実態と、日本との違いを感じていただくことはできましたでしょうか。
ところで、ゲーム理論を応用した最適な国際戦略は、1)最初は協力する(つまり、自分からは手を出さない)、2)それ以降は、相手が前の回にとった行動を選択する(つまり、仮にやられた場合はやり返す)――といわれています。この戦略はまさに、永世中立国のあり方に通ずるものを感じます。
宗教改革の終わりを宣告したウェストファリア条約には、当時の英知と近代につながる平和への願いが込められていたように思います。世界中の人々が希求する未来永劫の恒久平和のためにも、歴史的現代の視野にたったよりよい国際戦略の実践、互いの尊重に基づく国家間交流などが、ますます求められています。
2021年1月現在、永世中立の地位を維持する国は、スイス(1815年以来)、オーストリア(1955年以来)、トルクメニスタン(1995年以来)の3カ国のみです。
今回は、3カ国の中で最も歴史が古く、また一般的にも永世中立国の代名詞ともいえるスイスを取り上げ、永世中立国の実態ならびに、日本との違いを考察してみたいと思います。
スイスの歴史からみる永世中立国の成り立ち
ヨーロッパ中部に位置し、現在はフランス・ドイツ・リヒテンシュタイン・オーストリア・イタリアに囲まれているスイスは、古くから国際交通の十字路として役割を有し、さらに国土の約6割をアルプスが占める山地の国といった地政学的条件を有する国です。ヨーロッパのハブ的な存在であるスイスは重要な国である一方、建国以前から現代に至るまで、ゲルマン民族による征服、神聖ローマ帝国の支配、封建制度下によるハプスブルク家等有力諸侯による統治など、歴史に翻弄され苦難の歴史を重ねてきた国でもあります。
そのように、ある意味において地政学的な命運を担わざる得ないスイスが、中立国を経て永世中立国となる過程には、二度の大きな転換点がありました。
最初の転換点は、1618~48年の間ドイツを中心にヨーロッパ諸国を戦渦に巻き込み“最後で最大の宗教戦争”といわれる“三十年戦争”の末期に訪れます。1640年に国境保全のため国境防衛軍を創設したスイスは、さらに1647年にスイス各州で防衛軍事協定を結びます。この協定は事実上のスイス「武装中立」の出発点となりました。そして、1648年に三十年戦争を終結させた“ウェストファリア条約”の締結において、スイスは国際法的に独立を承認されることとなります。
しかしながらその裏では、特に17~18世紀のヨーロッパの戦乱期、各国の軍隊にスイス傭兵が働いていました。つまり、スイスは他国に血を売ることで、自国の中立を確保する歴史が続いていたともいえます。
ところが、1789年に起こったフランス革命の影響を受けスイス革命が起こり、さらにスイス革命を軍事的に援助したナポレオンによって、スイスにも中央集権的な政府が樹立されます。しかし、民族も宗教も文化も州によって大きく異なり、州自治を尊重していたスイスの伝統にあわず、ただちに混乱をきたします。ですが、結局はナポレオンの敗退と退位によって、二度目の転換点を迎えることとなります。
二度目の転換点は、1814~15年にナポレオン退位後のヨーロッパの政治的再編のために開かれた“ウィーン会議”によって、スイスは領土一部を与えられたうえで「武装永世中立国」となることが国際法的に承認されます。今日に続く永世中立国としてのスイスは、このときに誕生したといえます。
永世中立国と日本の違い=武装・非武装
以上のように、スイスが永世中立国となった背景には、ヨーロッパの社会的安定、特にスイスの隣接国にとっては安全保障上に望まれたことがみえてきました。また、独自性が高く自治を重んじるスイスの各州(カントン)にとっても、地方自治を尊重する現状のスイス連邦の維持は、安定した生活の大前提でもある様子もうかがえます。スイスの例からは、自国と他国(主に周辺地域国)の社会安定のため、政治的緩衝国家としての特性を生かしてどの国とも同盟関係を結ばない永世中立国であることが、かえって自国の安定を守りつつ他国の安定にも寄与するという、内外からの政学的戦略がうかがえます。
さて、冒頭でも述べたように、永世中立国は自衛の他は戦争をする権利を持ちません。そのうえ、他国と同盟を組むことなく自国を維持するためには、結果として「武装」が必須となることは否めません。
具体的には、永世中立国であるスイス・オーストリア・トルクメニスタンも自国の軍隊を所有し、軍事力を保持しています。特にスイスは“国民皆兵”といわれるほど軍事意識は高く、自国を守るために軍事力を活用しています。さらに、周辺国からしても、永世中立国は“他国にとられたくない国”ともいえます。そのため、例えばスイスが永世中立国となる際は「武装」が必須であり、ヨーロッパ各国、特に周辺国からの条件ですらありました。
ここに至ってようやく、永世中立国と戦争放棄国である日本の違いが明確なります。それは「武装」と「非武装」、つまりは「戦力の保持」と「戦力の不保持」にあります。日本は憲法においては「非武装国家」であり、また各国、特に周辺国からは「非武装」を要請されている国であるといえます(ただし、自衛権は戦争放棄国にも保証されていると考えられています)。
いかがでしたでしょうか。永世中立国の実態と、日本との違いを感じていただくことはできましたでしょうか。
ところで、ゲーム理論を応用した最適な国際戦略は、1)最初は協力する(つまり、自分からは手を出さない)、2)それ以降は、相手が前の回にとった行動を選択する(つまり、仮にやられた場合はやり返す)――といわれています。この戦略はまさに、永世中立国のあり方に通ずるものを感じます。
宗教改革の終わりを宣告したウェストファリア条約には、当時の英知と近代につながる平和への願いが込められていたように思います。世界中の人々が希求する未来永劫の恒久平和のためにも、歴史的現代の視野にたったよりよい国際戦略の実践、互いの尊重に基づく国家間交流などが、ますます求められています。
<参考文献・参考サイト>
・「永世中立」『日本大百科全書』(石本泰雄著、小学館)
・「スイス」『日本大百科全書』(前島郁雄・森田安一著、小学館)
・「スイス」『世界大百科事典』(森田安一著、平凡社)
・「三十年戦争」『日本大百科全書』(中村賢二郎、小学館)
・「ウェストファリア条約」『日本大百科全書』(中村賢二郎、小学館)
・『スイスの歴史ガイド』(グレゴワールナッペイ著、藤野成爾訳、春風社)
・『目で見る世界の国々 63 スイス』(ロリ・コールマン著、吉野美耶子訳、国土社)
・集団的自衛権の議論の前に常識のあるリベラル派がまずやるべきこと[橘玲の日々刻々]
https://diamond.jp/articles/-/54702
・「永世中立」『日本大百科全書』(石本泰雄著、小学館)
・「スイス」『日本大百科全書』(前島郁雄・森田安一著、小学館)
・「スイス」『世界大百科事典』(森田安一著、平凡社)
・「三十年戦争」『日本大百科全書』(中村賢二郎、小学館)
・「ウェストファリア条約」『日本大百科全書』(中村賢二郎、小学館)
・『スイスの歴史ガイド』(グレゴワールナッペイ著、藤野成爾訳、春風社)
・『目で見る世界の国々 63 スイス』(ロリ・コールマン著、吉野美耶子訳、国土社)
・集団的自衛権の議論の前に常識のあるリベラル派がまずやるべきこと[橘玲の日々刻々]
https://diamond.jp/articles/-/54702
人気の講義ランキングTOP20
『種の起源』…ダーウィンとウォレスの自然淘汰の理論
長谷川眞理子







