テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
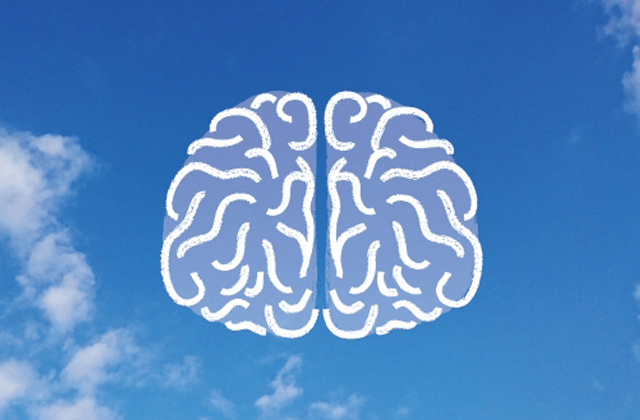
「脳が生きている」とは?『脳を司る「脳」』の正体
〝いま、あなたがこの本を手に取ったのは、脳のしわざです〟
お茶の水女子大学理学部助教である毛内拡先生の著書、『脳を司る「脳」 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』(ブルーバックス)は、この一文ではじまります。今、こうしてこのコラムを読んでいるということも、毛内先生の言葉を借りれば、〝脳のしわざ〟ということになるでしょう。
ふと見えた、〝脳〟の文字に興味を持ち、このコラムを読み始めた人もいれば、いろいろと検索していたら偶然出てきたのがこのコラムだった……という人もいるかもしれません。しかし、どこかで選択をしたということは、そこには〝脳〟が関わっています。このコラムを最後まで読んだとき、〝続きを読んでみよう〟〝この本を読んでみよう〟とこころが動くことも〝脳〟が判断し、呼び起こしている感情です。
どうして、そんな感情が浮かぶのでしょうか。わたしたちは何も考えずに生きることはできません。その原因や仕組みはどうなっているのでしょうか。脳の細胞のせい? あるいは遺伝? それとも何か別の物質が作用している?……。そんな脳のはたらきについて最前線の研究者が語った本書から、今回は〝脳の正体〟に迫ってみたいと思います。
本書ではまず、「脳が生きている」「脳が死んでいる」とはどのような状態のことかを説明しています。脳の活動は、電気的な活動であるため、脳が動いているときには、微弱な電流が生まれ、それは脳波として計測することができます。リラックスしているときにはアルファ波が出ている、ということは、よくテレビでも取り上げられていますね。
しかし、電流が生まれているからといって、それが「脳が生きている」とは必ずしもいえないのです。この本のなかでは、「一度死んでから蘇生された(ブタの)脳」、「試験管で培養された脳」、「コンピュータ上で再現された脳」の事例を並べ、それらを通して「脳が生きているということ」の定義を問い直しています。
中世ヨーロッパの時代、人の心は心臓にあるのではないかと考えられていましたが、現代を生きる多くの人は、〝こころ〟──つまり、人がどこでモノを考え、感情を生み出し、行動しているのかを問われたとき、それは〝脳〟であると答えるのではないでしょうか。「こころのはたらき」があるかどうかが、人間にとって欠かすことのできないヒトである要素の一つなのです。そして、電流だけで「こころのはたらき」は生まれません。本書のなかで、毛内先生は「これらのことを理解して納得してもらうためには、まず脳を構成する要素について一つ一つ理解していく必要があります」と語っています。
本書では、6章にわたって、これらの脳の複雑な仕組みを解説しています。情報を伝達するニューロンのはたらきや、それをつなぐシナプスの伝達の仕組み、脳の細胞の外にあるスペースがどう細胞同士に作用しているか、脳のなかを流れる水がどうやって脳から老廃物を排出しているのか、神経細胞の一種であるグリア細胞の割合についてなど……丁寧に説明がなされています。読み進めるうちに、次第に脳の仕組みがわかっていくと同時に、これだけ複雑な仕組みを、さらに外側から解き明かしていくだけの力が、人類の脳に備わっていることにも驚くのではないでしょうか。
さらに、本書ではどうしてヒトが「知性」や「ひらめき」を持つことができたのかにも言及してゆきます。
加えて、グリア細胞の一種であるアストロサイト(astrocyte)という細胞についても、ヒトの知性とのつながりが示唆されています。
このアストロサイトは、astronが古代ギリシア語で「星」を意味することからもお分かりの通り「星形」に近い姿をしています。本書では、アストロサイトを「星というよりは金ダワシのような」姿をしているとしています。ニューロンとニューロンのすきまを埋めるために存在している細胞と考えられ、注目されはじめたのは近年になってからだそうです。じつは多様な役割を担っているこのアストロサイトは、ヒトとマウスで比べても、よりヒトのほうが複雑で大きく、ヒトと同じようなアストロサイトはサルのような霊長類でしか観測できていない特殊なものです。
また、ヒトのアストロサイトをマウスに移植したところ、通常のマウスより高い学習能力を持つ可能性が実証されたという実例も紹介されています。つまり、アストロサイトの存在は、人類の知性に大きな影響を与えているかもしれないのです。
・知能とは、答えがあることに(素早く、正確に)答える能力
・知性とは、答えがないことに答えを出そうとする営み
コンピュータが得意なのは「知能」であり、人間の脳が得意なことは「知性」であると語ります。AIがヒトに取って代わる世界が夢物語でなくなりつつある現在、どうしてわたしたちに「知性」が備わっているのか、本書を通して考えてみるのはいかがでしょうか。生命の不思議に触れると同時に、人類の数千年にわたる発展は、未知のものを解き明かそうとする「知性」が支えてきたのだと感じられるはずです。
お茶の水女子大学理学部助教である毛内拡先生の著書、『脳を司る「脳」 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』(ブルーバックス)は、この一文ではじまります。今、こうしてこのコラムを読んでいるということも、毛内先生の言葉を借りれば、〝脳のしわざ〟ということになるでしょう。
ふと見えた、〝脳〟の文字に興味を持ち、このコラムを読み始めた人もいれば、いろいろと検索していたら偶然出てきたのがこのコラムだった……という人もいるかもしれません。しかし、どこかで選択をしたということは、そこには〝脳〟が関わっています。このコラムを最後まで読んだとき、〝続きを読んでみよう〟〝この本を読んでみよう〟とこころが動くことも〝脳〟が判断し、呼び起こしている感情です。
どうして、そんな感情が浮かぶのでしょうか。わたしたちは何も考えずに生きることはできません。その原因や仕組みはどうなっているのでしょうか。脳の細胞のせい? あるいは遺伝? それとも何か別の物質が作用している?……。そんな脳のはたらきについて最前線の研究者が語った本書から、今回は〝脳の正体〟に迫ってみたいと思います。
「脳が生きている」「脳が死んでいる」とはどういう状態か
一昔前、〝脳死は人の死か〟ということが頻繁にニュースに取り上げられた時代がありました。現在では、多くの先進国では〝脳死は人の死〟とされ、それによって臓器移植がなされる場合もあります。本書ではまず、「脳が生きている」「脳が死んでいる」とはどのような状態のことかを説明しています。脳の活動は、電気的な活動であるため、脳が動いているときには、微弱な電流が生まれ、それは脳波として計測することができます。リラックスしているときにはアルファ波が出ている、ということは、よくテレビでも取り上げられていますね。
しかし、電流が生まれているからといって、それが「脳が生きている」とは必ずしもいえないのです。この本のなかでは、「一度死んでから蘇生された(ブタの)脳」、「試験管で培養された脳」、「コンピュータ上で再現された脳」の事例を並べ、それらを通して「脳が生きているということ」の定義を問い直しています。
中世ヨーロッパの時代、人の心は心臓にあるのではないかと考えられていましたが、現代を生きる多くの人は、〝こころ〟──つまり、人がどこでモノを考え、感情を生み出し、行動しているのかを問われたとき、それは〝脳〟であると答えるのではないでしょうか。「こころのはたらき」があるかどうかが、人間にとって欠かすことのできないヒトである要素の一つなのです。そして、電流だけで「こころのはたらき」は生まれません。本書のなかで、毛内先生は「これらのことを理解して納得してもらうためには、まず脳を構成する要素について一つ一つ理解していく必要があります」と語っています。
脳の仕組みを理解しよう
脳を構成するものとして一般的に知られているのは、神経細胞であるニューロンや、それをつないでいるシナプスでしょう。しかし、たったそれだけのもので、他の生命体に類を見ないような発展──しかもいまだに宇宙空間にさえ同種の生命体が発見できていない──を遂げることはありません。人の脳はより複雑に、さまざまな物質がお互いに反応し合うことで、成り立っているのです。本書では、6章にわたって、これらの脳の複雑な仕組みを解説しています。情報を伝達するニューロンのはたらきや、それをつなぐシナプスの伝達の仕組み、脳の細胞の外にあるスペースがどう細胞同士に作用しているか、脳のなかを流れる水がどうやって脳から老廃物を排出しているのか、神経細胞の一種であるグリア細胞の割合についてなど……丁寧に説明がなされています。読み進めるうちに、次第に脳の仕組みがわかっていくと同時に、これだけ複雑な仕組みを、さらに外側から解き明かしていくだけの力が、人類の脳に備わっていることにも驚くのではないでしょうか。
さらに、本書ではどうしてヒトが「知性」や「ひらめき」を持つことができたのかにも言及してゆきます。
ヒトの知性を司っているのはグリア細胞?
脳細胞の一種であるグリア細胞は、ニューロンと同じか、それ以上の数、脳のなかに存在しているということがわかっています。じつは、このグリア細胞こそが、ヒトの知性の源になっている可能性があるのです。天才物理学者アルバート・アインシュタインの死後、彼の脳組織について研究が行われ、その結果、一般の人よりも「ひらめき」を司っている脳の部分にグリア細胞が多く見つかったという逸話もあるそうです。本書では、これを科学的な根拠として採用することは難しいとしながらも、「もしも本当にグリア細胞に天才的なひらめきを生む秘密が隠されていたらおもしろいと思いませんか」と語っています。加えて、グリア細胞の一種であるアストロサイト(astrocyte)という細胞についても、ヒトの知性とのつながりが示唆されています。
このアストロサイトは、astronが古代ギリシア語で「星」を意味することからもお分かりの通り「星形」に近い姿をしています。本書では、アストロサイトを「星というよりは金ダワシのような」姿をしているとしています。ニューロンとニューロンのすきまを埋めるために存在している細胞と考えられ、注目されはじめたのは近年になってからだそうです。じつは多様な役割を担っているこのアストロサイトは、ヒトとマウスで比べても、よりヒトのほうが複雑で大きく、ヒトと同じようなアストロサイトはサルのような霊長類でしか観測できていない特殊なものです。
また、ヒトのアストロサイトをマウスに移植したところ、通常のマウスより高い学習能力を持つ可能性が実証されたという実例も紹介されています。つまり、アストロサイトの存在は、人類の知性に大きな影響を与えているかもしれないのです。
「知能」と「知性」の違いが問いかける「生きていること」
本書は、「生きている」とはどういうことかという問いではじまり、脳の機能と、わたしたち人類の知性の根源について示唆をしたのち、再び「生きていること」についての問いを投げかけています。エピローグで毛内先生は、こう記述しています。・知能とは、答えがあることに(素早く、正確に)答える能力
・知性とは、答えがないことに答えを出そうとする営み
コンピュータが得意なのは「知能」であり、人間の脳が得意なことは「知性」であると語ります。AIがヒトに取って代わる世界が夢物語でなくなりつつある現在、どうしてわたしたちに「知性」が備わっているのか、本書を通して考えてみるのはいかがでしょうか。生命の不思議に触れると同時に、人類の数千年にわたる発展は、未知のものを解き明かそうとする「知性」が支えてきたのだと感じられるはずです。
<参考文献>
『脳を司る「脳」 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』(毛内拡著、ブルーバックス)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000347965
<参考サイト>
毛内拡先生の研究室
https://www-p.sci.ocha.ac.jp/bio-monai-lab/
『脳を司る「脳」 最新研究で見えてきた、驚くべき脳のはたらき』(毛内拡著、ブルーバックス)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000347965
<参考サイト>
毛内拡先生の研究室
https://www-p.sci.ocha.ac.jp/bio-monai-lab/
人気の講義ランキングTOP20










