テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
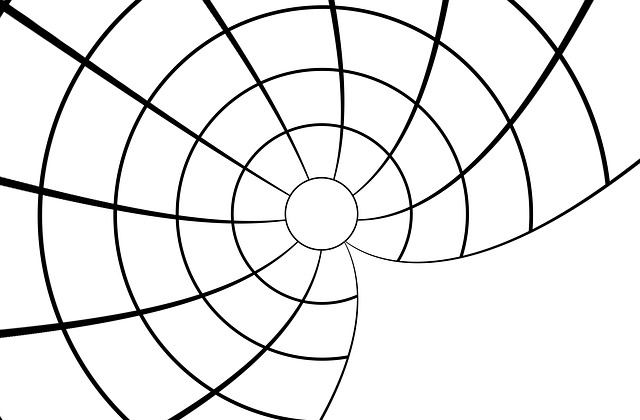
高次元の世界へ誘う魅惑の新書『多様体とは何か』
「現代数学・現代物理は、“多様体という舞台”で繰り広げられている」
はっとした後にドキドキとした胸の高まりを感じるような、素敵なフレーズだと思いませんか。数学者で作家、そして大学教員である小笠英志先生の『多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念』(講談社ブルーバックス)からの一説です。
多様体は図形の一種で、本書では「0次元多様体、1次元多様体・・・・・・、n次元多様体(nは非負整数)を合わせて多様体といいます」とされているように、正確な定義があります。
さらに、本書では0~3次元の多様体を、以下のように説明しています。
【0~3次元多様体の定義】
0次元多様体:点何個かのこと
1次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点はどの点も、その点のまわりは開区間になっているもの(円も1次元多様体)
2次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点はどの点も、その点のまわりは開円板となっているもの(開円板や球面も2次元多様体)
3次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点は、どの点も、その点のまわりは開球体になっているもの(開球体も3次元多様体)
ということですが、残念ながら多くの現代数学・現代物理学初心者にとって、こうした定義だけでは多様体を想像することは難しいのではないでしょうか。
そして、「2次元空間、3次元空間とは何か?」「開円板、閉円板とは何か?」「開球体、閉球体とは何か?」「貼り合わせるとはどういうことか?」「多様体を高次元にすると?」「なぜ我々は10次元に住んでいるのに気づかないのか?」等の魅惑的な問いが推進力となっています。
小笠先生の用意した“多様体に興味を持った初学者へ向けた本という舞台”を一幕から楽しむように、まずは読み飛ばすことなくPART1から順にページをめくり、さまざまな多様体を見て、感じていきましょう。
なお、本書は入門書ということですが、多様体の魅力や現代数学・現代物理学に目覚めた人がさらに楽しみながらさらに挑戦できるように、ポアンカレ予想や結び目と高次元多様体の問いなども用意されています。
冒頭では、多様体を現代数学や現代物理の舞台として紹介しました。つまり、現代数学や現代物理を学ぶ際には、多様体の理解が必須といえます。しかしながら、多様体をイメージできる能力を、現代数学や現代物理を専門に学ぶ人だけのものとするのは非常にもったいないことになります。
小笠先生は「頭の中で考えて、高次元が見えるときの精神状態や感動を表現するのに空想とか幻視などと言語表現しています」といいます。ただし、数学をきちんと学んだ者同士であれば、条件を限定して高次元の図形を思い描いた際に、同じ図形を頭に描けるといいます。そういった意味では、高次元の図形、ひいては多様体も曖昧模糊としたものではありません。
そのうえで、さらに続けて「新しい高次元の図形を発見したり、高次元の図形の新しい性質を発見したりするのは高次元への観照を要します。<中略>数学的に確固とした高次元のエキサイティングな図形を頭の中で思い描くこと、新発見することを空想、幻想、幻視などと感動をもって表現します」と述べています。
つまり、多様体や高次元をイメージしながら学ぶことによって、条件を限定した状態で空想、幻想、幻視できる能力、さらに学びあった者同士で頭に思い描いたイメージを共有できる能力を獲得できることになります。その能力は数学や物理を専門としない人にとっても、きわめて重要な能力であるといえます。
来るべきAI時代に人類に何よりも求められる能力は、想像力ともいわれています。小笠先生は「空手をやれば素手で岩が割れるようになります。数学をやれば高次元空間が見えるようになります」と高次元へと誘ってくれています。
空間と次元には限りないフロンティア(舞台)があること。空間と次元の舞台へのパスポートは多様体への直感力・想像力・空想力・幻想力であること。ぜひ本書を手に取って、多様体をイメージすることから始めてみてはいかがでしょうか。
はっとした後にドキドキとした胸の高まりを感じるような、素敵なフレーズだと思いませんか。数学者で作家、そして大学教員である小笠英志先生の『多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念』(講談社ブルーバックス)からの一説です。
多様体の定義
ところで、タイトルにもあるように「多様体」とはいったい何なのでしょうか。多様体は図形の一種で、本書では「0次元多様体、1次元多様体・・・・・・、n次元多様体(nは非負整数)を合わせて多様体といいます」とされているように、正確な定義があります。
さらに、本書では0~3次元の多様体を、以下のように説明しています。
【0~3次元多様体の定義】
0次元多様体:点何個かのこと
1次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点はどの点も、その点のまわりは開区間になっているもの(円も1次元多様体)
2次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点はどの点も、その点のまわりは開円板となっているもの(開円板や球面も2次元多様体)
3次元多様体:図形であって、その図形に含まれる点は、どの点も、その点のまわりは開球体になっているもの(開球体も3次元多様体)
ということですが、残念ながら多くの現代数学・現代物理学初心者にとって、こうした定義だけでは多様体を想像することは難しいのではないでしょうか。
空間・次元=舞台は多様
しかし本書では、定義や数式を使った説明だけではなく、「閉円板を貼り合わせて閉球体とする」「ドーナツの表面だけを描いたような2次元多様体のトーラス」「時計と長方形とトーラス」等のイメージ図が随所に掲載され、直感的に多様体のイメージを喚起できるようになっています。そして、「2次元空間、3次元空間とは何か?」「開円板、閉円板とは何か?」「開球体、閉球体とは何か?」「貼り合わせるとはどういうことか?」「多様体を高次元にすると?」「なぜ我々は10次元に住んでいるのに気づかないのか?」等の魅惑的な問いが推進力となっています。
小笠先生の用意した“多様体に興味を持った初学者へ向けた本という舞台”を一幕から楽しむように、まずは読み飛ばすことなくPART1から順にページをめくり、さまざまな多様体を見て、感じていきましょう。
なお、本書は入門書ということですが、多様体の魅力や現代数学・現代物理学に目覚めた人がさらに楽しみながらさらに挑戦できるように、ポアンカレ予想や結び目と高次元多様体の問いなども用意されています。
想像力を育む「多様体」直感力
ではどうして、多様体や高次元をイメージすることが大切なのでしょうか。冒頭では、多様体を現代数学や現代物理の舞台として紹介しました。つまり、現代数学や現代物理を学ぶ際には、多様体の理解が必須といえます。しかしながら、多様体をイメージできる能力を、現代数学や現代物理を専門に学ぶ人だけのものとするのは非常にもったいないことになります。
小笠先生は「頭の中で考えて、高次元が見えるときの精神状態や感動を表現するのに空想とか幻視などと言語表現しています」といいます。ただし、数学をきちんと学んだ者同士であれば、条件を限定して高次元の図形を思い描いた際に、同じ図形を頭に描けるといいます。そういった意味では、高次元の図形、ひいては多様体も曖昧模糊としたものではありません。
そのうえで、さらに続けて「新しい高次元の図形を発見したり、高次元の図形の新しい性質を発見したりするのは高次元への観照を要します。<中略>数学的に確固とした高次元のエキサイティングな図形を頭の中で思い描くこと、新発見することを空想、幻想、幻視などと感動をもって表現します」と述べています。
つまり、多様体や高次元をイメージしながら学ぶことによって、条件を限定した状態で空想、幻想、幻視できる能力、さらに学びあった者同士で頭に思い描いたイメージを共有できる能力を獲得できることになります。その能力は数学や物理を専門としない人にとっても、きわめて重要な能力であるといえます。
来るべきAI時代に人類に何よりも求められる能力は、想像力ともいわれています。小笠先生は「空手をやれば素手で岩が割れるようになります。数学をやれば高次元空間が見えるようになります」と高次元へと誘ってくれています。
空間と次元には限りないフロンティア(舞台)があること。空間と次元の舞台へのパスポートは多様体への直感力・想像力・空想力・幻想力であること。ぜひ本書を手に取って、多様体をイメージすることから始めてみてはいかがでしょうか。
<参考文献>
『多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念』(小笠英志著、ブルーバックス、講談社)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000351492
<参考サイト>
小笠英志先生のホームページ
http://ndimension.g1.xrea.com/
『多様体とは何か 空間と次元から学ぶ現代科学の基礎概念』(小笠英志著、ブルーバックス、講談社)
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000351492
<参考サイト>
小笠英志先生のホームページ
http://ndimension.g1.xrea.com/
人気の講義ランキングTOP20
高市政権の今後は「明治維新」の歴史から見えてくる!?
テンミニッツ・アカデミー編集部










