テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
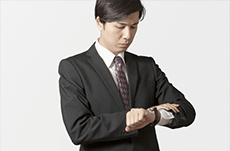
なぜ遅刻をしてはいけないのか?
「遅刻は欠席よりきらわれる」。民族学者の梅棹忠夫は、「遅刻論」で説きます。どうしてそれほどまでに遅刻はきらわれ、ひいては「遅刻はしてはいけない」と流布されているのでしょうか。
「なぜ遅刻はしてはいけないのか?」という問いに対する答えは、大別すると以下の2パターンに分類されるように思います。
つまり、「信用」に関わる社会の基本ルールであり、ひいては自己「信用」の損失となるため、「遅刻はしてはいけない」となっているといえます。
つまり、取り返しのつかない「時間」を奪う行為であり、その結果として他者の「時間」に損失を与えるため、「遅刻はしてはいけない」となっているといえます。
さらに、クリエイティブな結果や真に経済的な能率が求められるシビアな現場においては、遅刻しなかったからといって創造性や有益性が担保されるわけではないといった、ある意味でよりシビアな意見もあります。
本来、「時間」の流れ方や使い方は生活スタイルや人間関係によって異なっています。また、違う観点から捉えれば、一見すれば絶対的で平等な「時間」を使った社会ルールの基本設定が、そもそも万人に無理な設定であり、個人的な人間を省みない設定になっているともいえます。
状況から「遅刻」だけを取り出して考えることは本来できないし、意味がないともいえます。とくに現代のような加速度的に変化し、時間への価値観が相対的に高まっている社会では、ある一つの状況だけを取り出して画一的な判断をすること自体が、自他ともに許容しあえないゆとりのない状況を招きかねない危険性を多分にはらんでいるのではないでしょうか。
ジャーナリストでコラムニストのトーマス・フリードマン氏は、あるとき待ち合わせ相手の遅刻がちっとも気にならないことに、それどころか遅刻したことを謝罪する相手に「遅刻してくれて、ありがとう」と答えていたといいます。そして、その真意を、「あなたが遅れてきたおかげで、自分のための時間をつくることができたからだ」と、『遅刻してくれて、ありがとう』の中で述べています。
トーマス氏の言からは、最も大切な自分の「時間」が自分でコントロールできないぐらい、「時間」の価値が厳密になっている現実がうかがえてきます。さらに並行して、「信用」の価値観も多様化しており、明文化されない社会ルールでお互いを縛りあって窮屈にしている事実もあるように思います。
もちろん、遅刻が良いとされたり推奨されたりするという意味ではありません(そもそも、遅刻が良いのであれば、待ち合わせ時間や定刻を設定しなければよい)。
また、さまざまな状況が考慮されるとしても、前述したようにとりあえず現段階での社会ルールは「遅刻しない」のプライオリティが高いことは事実であり、遅刻が相手の時間を奪う行為であることももっともではあることからも、属しているコミュニティで「遅刻はしてはいけない」という価値の比重が高いのであればそれに応じた行動を取ることは、ある意味で戦略的にも正しい行動といえます。
しかしながら、加速化する現代では、ただ遅刻しなかったからといって、「信用」や「時間」の価値を担保することが、以前に比べて相対的に低くなっているように感じられます。
「自身に厳しく他者には優しく」。「遅刻」を通して、次世代型の自他の「信用」や「時間」の価値を高め合うことを、相対的にも絶対的にもあらためて考える時代を迎えているのかもしれません。
「なぜ遅刻はしてはいけないのか?」という問いに対する答えは、大別すると以下の2パターンに分類されるように思います。
「信用」に関わる社会の基本ルールだから?
パターン1は、(1)「約束の時間を守る=遅刻しない」は社会ルールである、(2)「約束の時間を守れない=遅刻する」はセルフコントロールができず「信用」をなくす、――以上より、自身の「信用」という価値を失する行為であるため遅刻はしてはいけない、です。つまり、「信用」に関わる社会の基本ルールであり、ひいては自己「信用」の損失となるため、「遅刻はしてはいけない」となっているといえます。
相手の「時間」を奪う行為だから?
一方、パターン2は、(1)「時間」は「命」ともいえる程に重要なものである、(2)「遅刻」は他者の「時間(命)」という損害できない権利を奪う愚行である、――以上より、他者の「時間」という権利を著しく失する行為であるため遅刻はしてはいけない、です。つまり、取り返しのつかない「時間」を奪う行為であり、その結果として他者の「時間」に損失を与えるため、「遅刻はしてはいけない」となっているといえます。
「遅刻」に画一的な評価をする社会こそ危険?
他方、「時間」と違ったものに価値や「信用」を置く社会やコミュニティも多数あります。そういった社会やコミュニティでは、例えば最近知り合ったビジネスパートナーに約束の時間に会うことよりも、偶然道で再会した昔なじみの恩師や導師に感謝や祈りを捧げる時間を十分に取ることの方が大切だったりします。さらに、クリエイティブな結果や真に経済的な能率が求められるシビアな現場においては、遅刻しなかったからといって創造性や有益性が担保されるわけではないといった、ある意味でよりシビアな意見もあります。
本来、「時間」の流れ方や使い方は生活スタイルや人間関係によって異なっています。また、違う観点から捉えれば、一見すれば絶対的で平等な「時間」を使った社会ルールの基本設定が、そもそも万人に無理な設定であり、個人的な人間を省みない設定になっているともいえます。
状況から「遅刻」だけを取り出して考えることは本来できないし、意味がないともいえます。とくに現代のような加速度的に変化し、時間への価値観が相対的に高まっている社会では、ある一つの状況だけを取り出して画一的な判断をすること自体が、自他ともに許容しあえないゆとりのない状況を招きかねない危険性を多分にはらんでいるのではないでしょうか。
「時間」の加速が「信用」の相対的価値を低下させている?
さらに、加速化が進む現代において、遅刻のハードルも加速度的に上がっているのではないでしょうか。ジャーナリストでコラムニストのトーマス・フリードマン氏は、あるとき待ち合わせ相手の遅刻がちっとも気にならないことに、それどころか遅刻したことを謝罪する相手に「遅刻してくれて、ありがとう」と答えていたといいます。そして、その真意を、「あなたが遅れてきたおかげで、自分のための時間をつくることができたからだ」と、『遅刻してくれて、ありがとう』の中で述べています。
トーマス氏の言からは、最も大切な自分の「時間」が自分でコントロールできないぐらい、「時間」の価値が厳密になっている現実がうかがえてきます。さらに並行して、「信用」の価値観も多様化しており、明文化されない社会ルールでお互いを縛りあって窮屈にしている事実もあるように思います。
もちろん、遅刻が良いとされたり推奨されたりするという意味ではありません(そもそも、遅刻が良いのであれば、待ち合わせ時間や定刻を設定しなければよい)。
また、さまざまな状況が考慮されるとしても、前述したようにとりあえず現段階での社会ルールは「遅刻しない」のプライオリティが高いことは事実であり、遅刻が相手の時間を奪う行為であることももっともではあることからも、属しているコミュニティで「遅刻はしてはいけない」という価値の比重が高いのであればそれに応じた行動を取ることは、ある意味で戦略的にも正しい行動といえます。
しかしながら、加速化する現代では、ただ遅刻しなかったからといって、「信用」や「時間」の価値を担保することが、以前に比べて相対的に低くなっているように感じられます。
「自身に厳しく他者には優しく」。「遅刻」を通して、次世代型の自他の「信用」や「時間」の価値を高め合うことを、相対的にも絶対的にもあらためて考える時代を迎えているのかもしれません。
<参考文献>
・『おろか者たち(中学生までに読んでおきたい哲学4)』(松田哲夫編、南伸坊案内人、あすなろ書房)※(梅棹忠夫「遅刻論」掲載)
・『お金持ちが肝に銘じているちょっとした習慣』(菅原圭著、河出書房新社)
・『小学生になったらどうするんだっけ』(辰巳渚著、朝倉世界一まんが、毎日新聞出版)
・『遅刻してくれて、ありがとう』(トーマス・フリードマン著、伏見威蕃訳、日本経済新聞出版社)
・『おろか者たち(中学生までに読んでおきたい哲学4)』(松田哲夫編、南伸坊案内人、あすなろ書房)※(梅棹忠夫「遅刻論」掲載)
・『お金持ちが肝に銘じているちょっとした習慣』(菅原圭著、河出書房新社)
・『小学生になったらどうするんだっけ』(辰巳渚著、朝倉世界一まんが、毎日新聞出版)
・『遅刻してくれて、ありがとう』(トーマス・フリードマン著、伏見威蕃訳、日本経済新聞出版社)
人気の講義ランキングTOP20










