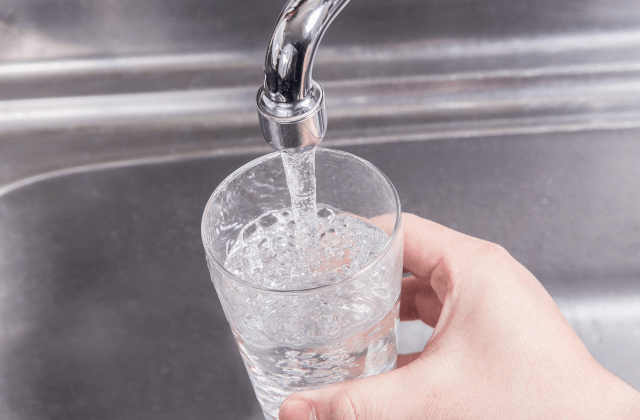
「水道水」が飲める国はたった○カ国!
私たち日本人にとって水道水は、蛇口をひねれば当たり前に飲めるものという認識です。しかしこれはかなり希有な例で、世界では水道水をまともに口にできない国がほとんどだということをご存じでしょうか。
今回は世界の水事情について、調べてみました!
<水道水をそのまま飲める国>
・日本
・オーストリア
・アイスランド
・アイルランド
・デンマーク
・オランダ
・フィンランド
・ノルウェー
・スウェーデン
・ニュージーランド
・モンテネグロ
そのほか、オーストラリアのシドニーが水道水をそのまま飲める都市となっています。
この11か国のうち9か国がヨーロッパの国で、アジアでは日本だけ。また「飲めるけれども注意が必要な国」もあり、こちらは29か国となっています。
水道水が安全に飲める国は非常に珍しいということがお分かりいただけたと思います。
【1】水源を確保できない
飲み水を汲むために、毎日片道数キロ歩く……そんな映像を見たことがある人も多いでしょう。実際、アジアやアフリカ、オーストラリアなどの乾燥地帯では、干ばつによって水源を確保できないということがあります。
2014年3月の国連世界水アセスメント計画(WWAP)の報告によると、世界の一人あたりの水資源賦存(ふぞん)量は平均6,148m3/年(2010年)ですが、北アフリカでは一人あたり284m3/年と1割にも満たないといい、今後、特に中東やアフリカ地域での水不足はより深刻な状況になるとしています。
【2】水質が悪く不衛生
そもそも河川の水質が悪すぎるため、浄水施設を通しても浄化しきれないというパターンがあります。河川へのごみの大量放棄や未処理の生活・工場排水、農薬の汚染などが原因です。
今後の世界の水質について経済協力開発機構(OECD)がまとめた報告(2012年)によると「2050年までに、大部分のOECD諸国では農業の生産性や排水処理への投資により安定した水質での還元が進む一方で、その他の地域では、農業と排水処理の不備による栄養塩の流入により、今後数十年で表層水の水質が悪化し、富栄養化の増大と、生物多様性の破壊をもたらすと予測されている(前述の国土交通省『水資源に関する国際的な取組み』より引用)」とあります。世界中で“水質の格差”が広がりつつあるのでしょう。
【3】水道設備が整っていない
貧しいためにインフラを整えられないという国はともかく、アメリカなどの先進国で、まともに水道水が飲めないということに違和感を感じる人も多いかもしれません。しかし実は人が住む地域にまんべんなく水道を敷く、上下水道処理施設をつくるというのは、想像以上に大変なこと。特にアメリカや中国のように国土の広い国は水道管を通すだけでも莫大なコストがかかりますし、さらにそのすべての水道管を管理・点検するのは容易ではありません。現実的な面から、水道施設を整備しきれない事情があるのです。
こうした理由から、水道水が飲めない国ではそもそも飲み水は店でミネラルウォーターを買う(または浄水器を使う)という習慣が根付いているため、水道を整備するまでに至らないということもあります。
日本の場合、「水質基準(51項目)」「水質管理設定目標項目(27項目)」「要検討項目(46項目)」の基準値を設定し、日々管理を続けています。自治体によっては国の基準よりも厳しくしているところも。安全面に関しては、万全の態勢を整えているといえるでしょう。
水道水を安心して口にできるのは、当たり前のようで実はとても幸せなこと。恵まれた環境に感謝しながら、これからも大切に水を使っていきたいですね。
今回は世界の水事情について、調べてみました!
水道水をそのまま飲める国は、わずか10か国のみ!
国土交通省が発表した『令和5年版 日本の水資源の現況について 第7章 水資源に関する国際的な取組み』等によると、水道水をそのまま飲用できるのは日本を含め11か国のみとなっています。<水道水をそのまま飲める国>
・日本
・オーストリア
・アイスランド
・アイルランド
・デンマーク
・オランダ
・フィンランド
・ノルウェー
・スウェーデン
・ニュージーランド
・モンテネグロ
そのほか、オーストラリアのシドニーが水道水をそのまま飲める都市となっています。
この11か国のうち9か国がヨーロッパの国で、アジアでは日本だけ。また「飲めるけれども注意が必要な国」もあり、こちらは29か国となっています。
水道水が安全に飲める国は非常に珍しいということがお分かりいただけたと思います。
世界のほとんどの国が水道水を飲めない理由
なぜ水道水が飲めない国がこれほど多いのでしょうか。その理由は大きく分けて3つあります。【1】水源を確保できない
飲み水を汲むために、毎日片道数キロ歩く……そんな映像を見たことがある人も多いでしょう。実際、アジアやアフリカ、オーストラリアなどの乾燥地帯では、干ばつによって水源を確保できないということがあります。
2014年3月の国連世界水アセスメント計画(WWAP)の報告によると、世界の一人あたりの水資源賦存(ふぞん)量は平均6,148m3/年(2010年)ですが、北アフリカでは一人あたり284m3/年と1割にも満たないといい、今後、特に中東やアフリカ地域での水不足はより深刻な状況になるとしています。
【2】水質が悪く不衛生
そもそも河川の水質が悪すぎるため、浄水施設を通しても浄化しきれないというパターンがあります。河川へのごみの大量放棄や未処理の生活・工場排水、農薬の汚染などが原因です。
今後の世界の水質について経済協力開発機構(OECD)がまとめた報告(2012年)によると「2050年までに、大部分のOECD諸国では農業の生産性や排水処理への投資により安定した水質での還元が進む一方で、その他の地域では、農業と排水処理の不備による栄養塩の流入により、今後数十年で表層水の水質が悪化し、富栄養化の増大と、生物多様性の破壊をもたらすと予測されている(前述の国土交通省『水資源に関する国際的な取組み』より引用)」とあります。世界中で“水質の格差”が広がりつつあるのでしょう。
【3】水道設備が整っていない
貧しいためにインフラを整えられないという国はともかく、アメリカなどの先進国で、まともに水道水が飲めないということに違和感を感じる人も多いかもしれません。しかし実は人が住む地域にまんべんなく水道を敷く、上下水道処理施設をつくるというのは、想像以上に大変なこと。特にアメリカや中国のように国土の広い国は水道管を通すだけでも莫大なコストがかかりますし、さらにそのすべての水道管を管理・点検するのは容易ではありません。現実的な面から、水道施設を整備しきれない事情があるのです。
こうした理由から、水道水が飲めない国ではそもそも飲み水は店でミネラルウォーターを買う(または浄水器を使う)という習慣が根付いているため、水道を整備するまでに至らないということもあります。
ヨーロッパ、そして日本の水道水は水質基準が厳しい
ヨーロッパや日本の水道水が飲用できる理由は、もともと自然が多く水源が豊富である、国土が狭くインフラを整備しやすいなど、上記に挙げた問題をすべてクリアできているうえ、飲み水の安全性に関して厳格な基準を定めていることが挙げられます。日本の場合、「水質基準(51項目)」「水質管理設定目標項目(27項目)」「要検討項目(46項目)」の基準値を設定し、日々管理を続けています。自治体によっては国の基準よりも厳しくしているところも。安全面に関しては、万全の態勢を整えているといえるでしょう。
水道水を安心して口にできるのは、当たり前のようで実はとても幸せなこと。恵まれた環境に感謝しながら、これからも大切に水を使っていきたいですね。
<参考サイト>
・令和5年版 日本の水資源の現況について│国土交通省
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr2_000050.html
・『令和5年版 日本の水資源の現況について 第7章 水資源に関する国際的な取組み』│国土交通省
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/content/001720113.pdf
・水道水質基準について│厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/index.html
・そのまま水を飲める国は何%?海外の飲料水事情とは│Kirala Water
https://www.kirala.jp/special/knowhow/742/
・海外で水道水は飲める?│ジェイアイ傷害火災保険株式会社
https://tabiho.jp/insurance-guide/information/water.html
・令和5年版 日本の水資源の現況について│国土交通省
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_fr2_000050.html
・『令和5年版 日本の水資源の現況について 第7章 水資源に関する国際的な取組み』│国土交通省
https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/content/001720113.pdf
・水道水質基準について│厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/index.html
・そのまま水を飲める国は何%?海外の飲料水事情とは│Kirala Water
https://www.kirala.jp/special/knowhow/742/
・海外で水道水は飲める?│ジェイアイ傷害火災保険株式会社
https://tabiho.jp/insurance-guide/information/water.html
人気の講義ランキングTOP20
科学は嫌われる!? なぜ「物語」のほうが重要視されるのか
長谷川眞理子







