テンミニッツ・アカデミーでおすすめの講義
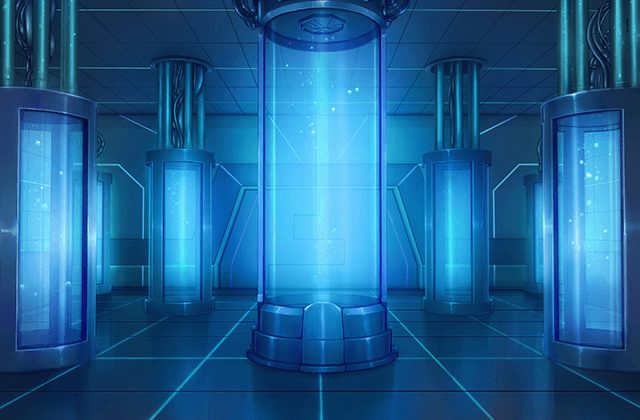
『人類冬眠計画』が描く近未来の世界とその可能性
SFの世界でたびたび登場する〝コールドスリープ〟──人の体を冷凍保存し、人工的な冬眠状態にするという近未来技術です。コールドスリープが登場する代表的な映画作品に、映画『2001年宇宙の旅』や『エイリアン』、『パッセンジャー』などがあげられます。そこでは、コールドスリープを行うためのカプセルに入り、睡眠状態のまま、肉体老化を防ぎ、数十年から数百年単位の惑星間飛行を行うという場面がよく描かれますが、目覚めたときには時間が経過しているため、一種のタイムトラベルの方法とも考えられています。
これらのお話はあくまで夢物語。人を冷凍保存するなんて技術的に無理である……というのが一般的な認識だと思います。しかし、コールドスリープ──「人工冬眠」は絵空事でも何でもなく、実際に実現可能かもしれない新しい技術として研究が進んでいるのです。今回は、そんな人工冬眠を研究している理化学研究所生命機能科学研究センター上級研究員・砂川玄志郎先生の著書『人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む』(岩波科学ライブラリー)をもとに話を進めていきます。
そんな折、ついに砂川先生は1つの論文と出会いを果たします。それはマダガスカル島で冬眠をするキヅネザルが見つかったというもの。マダガスカル島はアフリカの東に位置する熱帯の島です。そんな場所でも冬眠をする哺乳類がいる──。「小さなサルとはいえ、人間と同じ霊長類が冬眠できるのであれば、人間も冬眠できるんじゃないか」と考えたという砂川先生。「患者さんの死が近いときに冬眠を誘導できれば、本格的な治療が始まるまでの時間をかなり稼ぐことはできるだろうと思った」そうです。
何時間でも意識をなくし痛みを感じなくさせることができる麻酔と、途切れさせることのできない酸素供給や、わずかな揺れで命を落としてしまうこともある、重症患者の搬送についての問題。センターで学んだ2つのことが、この論文をきっかけに1つの研究テーマへと結実します。それが「人工冬眠」だったのです。
しかし、すべての生物は冬眠をするわけではなく、人間は冬眠をしない生き物です。また、人間は体温の上下に敏感な生き物でもあります。平熱から1度上昇しただけで体に影響が出ることはみなさんもご存じだと思います。逆に、平熱より低くなるとどうかというと、35度でふるえが起こるようになり、32度になると命の危機に瀕するのです。これでは、人工冬眠を実際に行うことは困難であると感じます。そこで、砂川先生は冬眠する生物が、何を起因に冬眠するのかという研究を行いました。その研究の様子や事例は、2章から4章にかけて順を追って説明がなされます。
そして、マウスの実験で発見されたのが、視床下部にある神経細胞群を興奮させることで、マウスの動きを抑制し、体温の低下を誘導するというものでした。つまり、脳の一部を興奮させることで、冬眠しない生物でも、実際に冬眠状態に導くことができたのです。砂川先生の研究チームは、この冬眠状態のことを「QIH(Q neuron-induced hypometabolism)」と名付けました。これにより、人も冬眠できるという可能性を得たのです。
砂川先生は、人工冬眠が実現する可能性として、4つの根拠をあげています。1つめは、研究のきっかけにもなった「冬眠する霊長類」がいること。2つめは、体の大きなクマなどの動物も冬眠をすることができること。3つめは、雪山で遭難し、奇跡的に助かった方の存在。これは、冬眠に近い低代謝状態でないと説明がつかない事例です。4つめは、現存している哺乳類はすべて最後の氷河期を生き抜いた動物の子孫であること。これらの可能性を踏まえ、人工冬眠の技術を確立させるには、「実際に冬眠する動物を詳しく研究し、実際に冬眠しない動物を冬眠できるように研究を進めていく必要がある」としています。
また、人工冬眠を手に入れた人類は、SF映画のように地球を離れて宇宙に旅立つようになるのではないかとも、砂川先生は語っています。そうした夢のあるビジョンが広がる一方、人工冬眠がもたらす社会の変化についても興味深い考察が続きます。冬眠を選択する人々の人権問題。寿命や時間といった概念がなくなること。それは、すべての生命が持つ「生と死」という逃れがたい真実にさえ、人の手が介入し、生でも死でもない「休」という新たな状態が生まれること。人工冬眠が現実になった暁には、人の生のあり方が問われることとなるのかもしれません。
「昔の人間には為す術もなかったことで、医学の進歩により人間が克服した病気や状態は無数にある。抗生剤の発明により克服できた致死性の感染症、全身麻酔の発明により可能になった腫瘍の摘出…(中略)冬眠も研究開発によっていずれできるようになると思っている」
現代では当たり前になっている技術や医療法のなかには、発明当時、大きな反発や反対という事態が起こるということも少なくありませんでした。人工冬眠も、そうした紆余曲折を経ながら、やがて人類にとって重要な技術として用いられる日が来るのでしょうか。
科学技術が飛躍的に進歩している現代、わたしたちはSFの世界に近づこうとしています。この機会に本書を開き、近未来の世界、「人工冬眠」の可能性を感じてみてください。
これらのお話はあくまで夢物語。人を冷凍保存するなんて技術的に無理である……というのが一般的な認識だと思います。しかし、コールドスリープ──「人工冬眠」は絵空事でも何でもなく、実際に実現可能かもしれない新しい技術として研究が進んでいるのです。今回は、そんな人工冬眠を研究している理化学研究所生命機能科学研究センター上級研究員・砂川玄志郎先生の著書『人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む』(岩波科学ライブラリー)をもとに話を進めていきます。
1つの論文がきっかけで「人工冬眠」研究へ
本書は、人工冬眠の本題に入る前に、著書である砂川先生がどのように人工冬眠と出会い、研究の道へと進んだのかという、出会いのエピソードからはじまります。砂川先生は、もともと小児科医として、医療に従事していました。勤務していたのは、日本でもっとも小児の重症例が集まる国立成育医療センター(現在の国立成育医療研究センター)の手術集中医療部で、ここで「麻酔の重要性」と、「重症患者の搬送の困難さ」を学んだと述べています。この頃、砂川先生はまだ「人工冬眠」の世界とは出会っていませんでした。そんな折、ついに砂川先生は1つの論文と出会いを果たします。それはマダガスカル島で冬眠をするキヅネザルが見つかったというもの。マダガスカル島はアフリカの東に位置する熱帯の島です。そんな場所でも冬眠をする哺乳類がいる──。「小さなサルとはいえ、人間と同じ霊長類が冬眠できるのであれば、人間も冬眠できるんじゃないか」と考えたという砂川先生。「患者さんの死が近いときに冬眠を誘導できれば、本格的な治療が始まるまでの時間をかなり稼ぐことはできるだろうと思った」そうです。
何時間でも意識をなくし痛みを感じなくさせることができる麻酔と、途切れさせることのできない酸素供給や、わずかな揺れで命を落としてしまうこともある、重症患者の搬送についての問題。センターで学んだ2つのことが、この論文をきっかけに1つの研究テーマへと結実します。それが「人工冬眠」だったのです。
冬眠が必要ない生物も冬眠状態に導ける
「哺乳類を含めた動物が冬にいなくなることを冬眠(hibernation)と表現したのは、紀元前300年代のアリストテレスが最古だといわれている」と、本書のなかで紹介されていますが、冬眠は古くから知られる現象でした。16世紀からは冬眠を題材にした科学論文が発表されるなど、冬眠の研究は数百年から行われていたのです。近年、心電図や脳波などの生体情報を機械で計測できるようになり、代謝の低下が冬眠に大きく関わっているということがわかりました。しかし、すべての生物は冬眠をするわけではなく、人間は冬眠をしない生き物です。また、人間は体温の上下に敏感な生き物でもあります。平熱から1度上昇しただけで体に影響が出ることはみなさんもご存じだと思います。逆に、平熱より低くなるとどうかというと、35度でふるえが起こるようになり、32度になると命の危機に瀕するのです。これでは、人工冬眠を実際に行うことは困難であると感じます。そこで、砂川先生は冬眠する生物が、何を起因に冬眠するのかという研究を行いました。その研究の様子や事例は、2章から4章にかけて順を追って説明がなされます。
そして、マウスの実験で発見されたのが、視床下部にある神経細胞群を興奮させることで、マウスの動きを抑制し、体温の低下を誘導するというものでした。つまり、脳の一部を興奮させることで、冬眠しない生物でも、実際に冬眠状態に導くことができたのです。砂川先生の研究チームは、この冬眠状態のことを「QIH(Q neuron-induced hypometabolism)」と名付けました。これにより、人も冬眠できるという可能性を得たのです。
人工冬眠の可能性と社会変化
本書の最終章(5章)では、実際に人工冬眠が実現するのか、また実現した場合の社会の変化について語られます。砂川先生は、人工冬眠が実現する可能性として、4つの根拠をあげています。1つめは、研究のきっかけにもなった「冬眠する霊長類」がいること。2つめは、体の大きなクマなどの動物も冬眠をすることができること。3つめは、雪山で遭難し、奇跡的に助かった方の存在。これは、冬眠に近い低代謝状態でないと説明がつかない事例です。4つめは、現存している哺乳類はすべて最後の氷河期を生き抜いた動物の子孫であること。これらの可能性を踏まえ、人工冬眠の技術を確立させるには、「実際に冬眠する動物を詳しく研究し、実際に冬眠しない動物を冬眠できるように研究を進めていく必要がある」としています。
また、人工冬眠を手に入れた人類は、SF映画のように地球を離れて宇宙に旅立つようになるのではないかとも、砂川先生は語っています。そうした夢のあるビジョンが広がる一方、人工冬眠がもたらす社会の変化についても興味深い考察が続きます。冬眠を選択する人々の人権問題。寿命や時間といった概念がなくなること。それは、すべての生命が持つ「生と死」という逃れがたい真実にさえ、人の手が介入し、生でも死でもない「休」という新たな状態が生まれること。人工冬眠が現実になった暁には、人の生のあり方が問われることとなるのかもしれません。
SFの世界を実現していく科学技術の可能性
ただ、新しい技術の可能性に胸を躍らせる人もいれば、人の命の価値観や、生命や人類のあり方に変化をもたらすかもしれないということに、一抹の不安を感じる人もいるかもしれません。本書のなかで砂川先生は次のように記しています。「昔の人間には為す術もなかったことで、医学の進歩により人間が克服した病気や状態は無数にある。抗生剤の発明により克服できた致死性の感染症、全身麻酔の発明により可能になった腫瘍の摘出…(中略)冬眠も研究開発によっていずれできるようになると思っている」
現代では当たり前になっている技術や医療法のなかには、発明当時、大きな反発や反対という事態が起こるということも少なくありませんでした。人工冬眠も、そうした紆余曲折を経ながら、やがて人類にとって重要な技術として用いられる日が来るのでしょうか。
科学技術が飛躍的に進歩している現代、わたしたちはSFの世界に近づこうとしています。この機会に本書を開き、近未来の世界、「人工冬眠」の可能性を感じてみてください。
<参考文献>
『人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む』(砂川玄志郎著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b603062.html
<参考サイト>
「冬眠チーム@理研BDR」の砂川玄志郎先生のページ
https://retina.sakura.ne.jp/ht/?page_id=418&lang=ja
『人類冬眠計画 生死のはざまに踏み込む』(砂川玄志郎著、岩波科学ライブラリー)
https://www.iwanami.co.jp/book/b603062.html
<参考サイト>
「冬眠チーム@理研BDR」の砂川玄志郎先生のページ
https://retina.sakura.ne.jp/ht/?page_id=418&lang=ja
人気の講義ランキングTOP20
2025年のテンミニッツ・アカデミーを振り返る
テンミニッツ・アカデミー編集部










